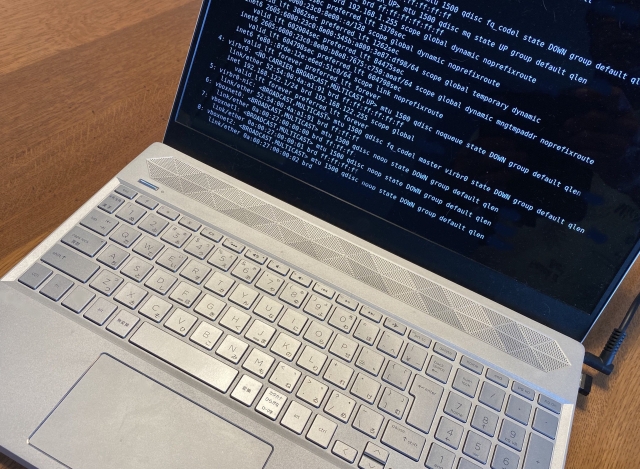マイクロソフトは、旧型PCにWindows 11をインストールする「公式」回避策をサポートページから削除した。この変更は、Windows 11最新アップデート「24H2」の公開直後に行われ、同社が今後も厳格なハードウェア要件を維持する姿勢を示している。
Windows 11のリリース当初、マイクロソフトは一定の制約下で非対応PCへの導入を許可していた。しかし、公式な手段が撤廃されたことで、古いPCを利用し続けるための道は狭まることになる。一方で、サードパーティ製ツールを活用した非公式なインストール手段は依然として存在しており、多くのユーザーがこれに頼る可能性がある。
Windows 10の公式サポートは2025年10月に終了する予定であり、企業や個人ユーザーは今後の対応を迫られる。マイクロソフトは最新機能を活用するには新しいPCの購入が必要だと強調しているが、移行の進捗は同社の想定通りに進んでいないのが実情だ。
Windows 11のハードウェア要件強化と24H2アップデートの影響

マイクロソフトは、Windows 11の導入要件を当初から厳格に設定していたが、公式の回避策を削除したことで、旧型PCでの運用がより困難になった。この変更は最新の「24H2」アップデートがリリースされた直後に行われ、特に非対応デバイスへの影響が顕著となった。
Windows 11は、Trusted Platform Module(TPM)2.0の搭載や特定世代以上のCPUを必須要件とし、セキュリティとパフォーマンスの向上を目的としている。24H2ではこれらの制約が再確認され、今後も緩和される可能性は低い。ハードウェアの要件を満たさないPCでは、更新プログラムの適用が困難となり、長期的には安定した運用ができなくなるリスクがある。
企業や個人ユーザーの多くは、現在もWindows 10を利用している。マイクロソフトはWindows 10のサポート終了を明言しており、新OSへの移行を促しているが、実際の導入率は想定より低調だ。ハードウェア要件の厳格化は、新PCの販売促進につながるが、特に企業ではコスト負担が大きく、OSのアップグレードが進まない一因となっている。
非公式なインストール手段が依然として存在 サードパーティツールの役割
マイクロソフトが公式の回避策を削除したにもかかわらず、非公式な方法によるWindows 11のインストール手段は依然として利用可能である。特に、RufusやVentoyといったサードパーティ製ツールは、ハードウェア要件を回避してOSを導入できるため、多くのユーザーが利用していると考えられる。
これらのツールを使用すると、公式サポートの対象外となるリスクがあるが、古いPCを延命する手段としては有効である。実際に、多くの企業では旧型ハードウェアを活用するために、このような回避策を用いているとみられる。特に、ソフトウェアの互換性を重視する業界では、最新OSへの移行が遅れることが多く、非公式な方法による導入が進められる可能性が高い。
しかし、マイクロソフトはこのような回避策を推奨しておらず、今後のアップデートでさらなる制約を加える可能性がある。Windows 11のインストールに関する制限は、OSのセキュリティ向上と安定性確保を目的としているが、ユーザーにとっては選択肢の縮小につながる。一方で、オープンソースコミュニティや技術者の間では、こうした制限を回避する新たな手法が模索され続けるだろう。
Windows 10サポート終了が迫る中、移行戦略はどう変化するか
Windows 10の公式サポート終了が2025年10月に予定されていることから、企業や個人ユーザーは今後の対応を迫られている。特に、大規模なシステム更新が必要な企業では、新PCの調達コストや互換性の問題が課題となる。一方で、Windows 11の導入が進まない現状を踏まえ、マイクロソフトが移行を促進する新たな施策を講じる可能性も考えられる。
現在、Windows 10を使用する企業向けには「長期サービスチャネル(LTSC)」の選択肢があるものの、追加費用が発生するため、すべての組織が利用できるわけではない。マイクロソフトは、新OSの導入を前提としたビジネスモデルを推進しているが、実際の市場動向とは乖離が生じている。
このため、今後の焦点は、Windows 10ユーザーの移行支援策がどのように展開されるかにある。マイクロソフトが現行の戦略を維持し、強制的な移行を推し進めるのか、それとも柔軟な対応を模索するのかが注目される。企業やユーザーにとっては、短期間での移行が難しい場合もあり、サポート終了後の選択肢を慎重に見極める必要がある。
Source:TechSpot