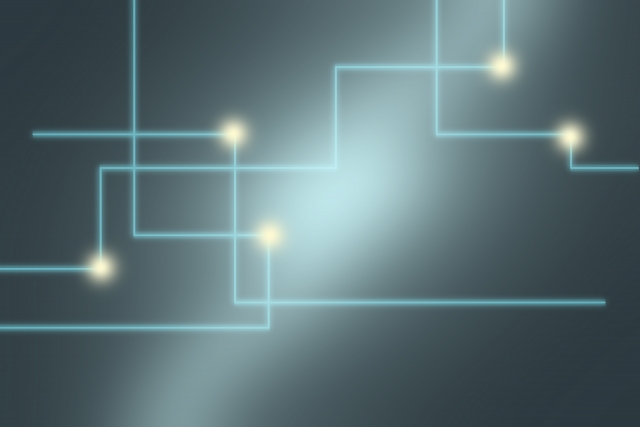サムスン電子の李在鎔会長が経営陣に対し、「生きるか死ぬかの時(do or die time)」と発言し、業界内外で大きな注目を集めている。半導体事業の苦戦や米国の関税問題、中国メーカーの台頭など、厳しい経営環境が背景にある。
主力の半導体部門は、高帯域幅メモリ(HBM)の供給遅延や競争力低下により、NVIDIA向け製品の品質検証が難航。加えて、ファウンドリー事業の赤字も深刻で、TSMCとの差が拡大している。スマートフォン市場でもAppleや中国勢との競争が激化し、シェア減少が続く。
こうした状況を打破するため、サムスンは大規模な企業買収を検討。経営幹部の発言からも、成長戦略の一環として積極的な投資が進められる可能性が高い。特に米国の保護主義強化により、海外事業の最適化も急務となっている。
サムスンの半導体事業が直面する課題 HBM供給遅延とTSMCとの差

サムスン電子の半導体部門は、競争が激化する中で大きな試練に直面している。特に、高帯域幅メモリ(HBM)の供給遅延が深刻な問題となっており、NVIDIA向けの第5世代HBM3Eの品質検証が難航。1年以上にわたるテストの末、いまだ合格通知を得られていないという。この遅れは、AI市場の拡大による需要急増に対応できていないことを示しており、競争相手に対して大きなハンデを抱えている。
さらに、半導体受託製造(ファウンドリー)事業では、最大のライバルである台湾TSMCとの格差が拡大。市場調査会社TrendForceによると、昨年第4四半期のファウンドリー市場シェアはTSMCが67.1%、サムスンはわずか8.1%にとどまる。サムスンは最新のGAA(ゲート・オール・アラウンド)技術による3nmプロセスで巻き返しを狙うが、量産の安定性が課題とされている。
これらの状況は、ユーザーにとっても影響が大きい。HBMの供給が遅れれば、NVIDIAの最新AIチップの生産も停滞し、高性能GPUの供給不足や価格高騰につながる可能性がある。また、サムスンのファウンドリー競争力が低下すれば、最新スマートフォンやPC向けのチップ供給にも影響を及ぼし、選択肢の減少や価格上昇を引き起こしかねない。
折りたたみスマホや家電での戦略転換は可能か
サムスン電子はスマートフォン市場でも苦境に立たされている。プレミアム市場ではAppleが圧倒的なブランド力を誇り、中国メーカーはコストパフォーマンスで攻勢をかける。特に、2023年の市場シェアは19.7%だったが、昨年は18.3%にまで低下。AppleのiPhoneやXiaomi、Oppo、Vivoといった中国勢との競争がますます激しくなっている。
サムスンが差別化の鍵とするのが、折りたたみスマートフォンだ。同社のGalaxy Zシリーズは業界をリードしてきたが、市場全体での成長は期待ほどではない。特に価格が高いことが普及のネックとなり、一般ユーザーにはまだ広がりきれていない。一方、家電部門では、AI家電やスマートホーム連携を強化し、シェア維持を狙うが、テレビ市場ではシェアが30.1%から28.3%に減少している。
こうした状況を打開するためには、価格戦略や技術革新だけでなく、サービスの充実も重要になる。例えば、折りたたみスマホをより身近な存在にするために、サブスクリプション型の販売や下取りプログラムを拡充することが求められる。また、家電分野では、スマート家電の統合プラットフォームを強化し、エコシステムの一部としての価値を高めることで、ユーザーの囲い込みが可能になるだろう。
大規模買収は競争力強化につながるのか
サムスン電子の韓宗熙(ハン・ジョンヒ)共同CEOは、成長を加速させるために大規模な買収を検討していると明言した。これは、同社が直面する厳しい状況を打破するための一手と考えられる。特に、半導体事業やAI分野において、買収を通じた技術力強化が狙いとみられる。
過去の例を見ても、大規模な買収は企業にとってリスクとチャンスの両面を持つ。例えば、2020年にNVIDIAがArmの買収を試みたが、各国の規制当局の反発で頓挫。一方で、AMDはXilinxを買収し、AI分野での競争力を強化することに成功している。サムスンが買収を実施する場合、米国や欧州の規制当局の承認を得ることが課題となる可能性がある。
また、買収戦略が成功すれば、半導体やAI分野での競争力が向上し、ユーザーにとっても新たな技術や製品の恩恵が期待できる。一方、失敗した場合には巨額の投資が無駄になり、事業全体の停滞を招くリスクもある。サムスンの動向次第では、スマートフォンや半導体市場に大きな影響を及ぼすことになりそうだ。
Source:Patently Apple