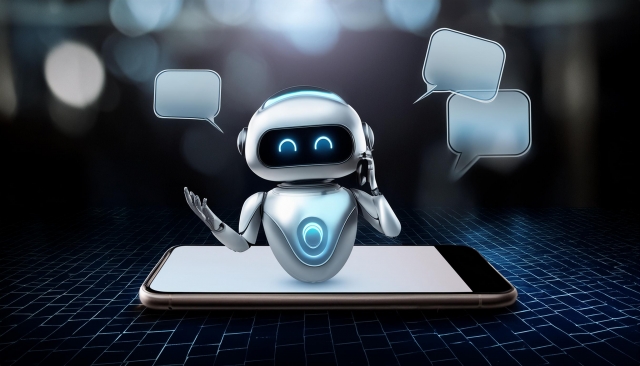OpenAIのChatGPTが世界を席巻した直後、GoogleはAI開発チームに対し、100日以内に競合製品を構築するよう厳命した。Gemini開発の指揮を執ったシシー・シャオ副社長は「全速力でマラソンを走るようだった」と語り、品質とスピードの両立を強いられた開発の実情を明かす。
一時は誤回答による失点もあったが、Geminiは改名を経て性能でChatGPTに肉薄、画像生成機能の不備にも対応しながら地位を確立。現在は「エージェント的能力」を次なる進化と位置づけ、Google全体を巻き込んだ本格的なAI戦略へと舵を切っている。
Alphabetは750億ドル規模の設備投資を今後実施する計画であり、Geminiは同社のAIファースト方針の中核として、再び覇権を狙う立場にある。
「品質優先、だが迅速に」Googleが直面した開発方針の矛盾

GoogleがGeminiの前身であるBardを開発した際、求められたのは「品質を犠牲にせず、なおかつ迅速に」という二律背反の目標であった。シシー・シャオ副社長の言葉を借りれば、それは「全速力でマラソンを走る」ような体力と精神力を要する工程だった。ChatGPTの登場によってAIの主導権を失う危機感が、かつて業界をリードしていたGoogleを急き立てた。
2023年2月の初公開時には、Bardが広告で誤情報を示したことで批判を浴びたが、同年12月にはGeminiとして改名し、開発の再構築に踏み切った。
この一連の対応は、Googleの意思決定における柔軟性と危機対応力を示しているが、一方で拙速な展開の代償として信頼性に傷を負ったことも事実である。Geminiがベンチマークで高評価を得た後も、ユーザーの目には初期の失敗が残像として残る可能性がある。
特に、生成AIに対する社会的信頼の構築には、単なる技術的優位性以上の慎重な情報管理が求められる局面に入っている。
歴史認識を問われた画像生成AI Geminiの失策と回復戦略
2024年2月、Geminiの画像生成機能が示した歴史的不正確さは、AIの訓練データと倫理観の管理がいかに複雑な課題であるかを象徴する事例となった。ナチス時代のドイツ兵を多民族の姿で描写するなど、事実誤認のある出力がSNS上で拡散され、Googleは機能の再リリースを8月に延期する決定を下した。
これは生成AIが歴史的文脈に無自覚であることが引き起こすリスクを顕在化させた格好であり、アルゴリズムの調整と監視体制の強化が不可避であることを意味する。
一方、迅速に機能の停止と再設計を判断した姿勢は、企業としてのリスクマネジメント能力を示す結果ともなった。Geminiが「エージェント的能力」を備えた次世代AIを志向する以上、単なる出力精度ではなく、歴史的・文化的背景を踏まえた判断力の組み込みが避けて通れない。
AIが個人に代わって意思決定を補助する未来像を描くのであれば、単なる情報処理の枠を超えた倫理的整合性がその中核に据えられる必要がある。
750億ドル投資とフルスタック戦略 GoogleのAI覇権への布石
Alphabetのサンダー・ピチャイCEOは、2024年度にAI事業へ750億ドル規模の設備投資を行う方針を明示した。Geminiを中核とするこの取り組みは、単なるチャットボット開発にとどまらず、Google検索や各種アプリと連携した「AIファースト」の企業構造を完成させるための布石といえる。
シャオ氏が言及した「AIは必須であり、あれば良いものではない」という発言は、マーケティング、営業、開発など全社的なAI統合の既定路線を象徴する。
注目すべきは、GoogleがAIイノベーションにおいて「フルスタックアプローチ」を掲げている点である。基盤モデルからサービス展開までを垂直統合し、外部依存を極力排した体制は、他のAI企業と一線を画す。特に検索事業における「AIオーバービュー」機能は、ユーザー体験を再定義し得る試みであり、Geminiの進化が同社の競争力を根底から再構築する可能性を秘める。
ただし、その優位性が持続するかどうかは、今後の実装スピードと市場反応に左右される。
Source:Quartz