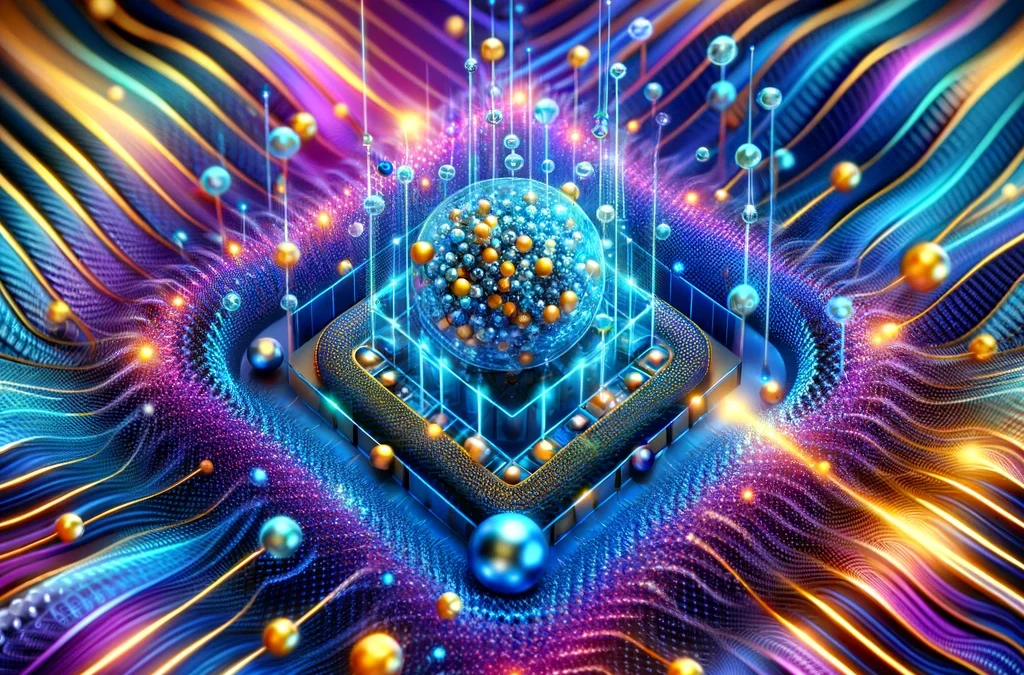米半導体大手マイクロン・テクノロジー(MU)は、AI関連需要の急増を背景に、2025会計年度第2四半期の業績でデータセンター向けDRAMの過去最高売上を達成し、HBM(高帯域幅メモリ)の収益も前四半期比で50%超増加した。HBM3Eの供給先にはNVIDIAが含まれ、2026年にはHBM4の市場投入も予定されている。
加えて、極端紫外線リソグラフィ技術を活用した「1-gamma」DRAMの導入や、シンガポールおよびアイダホ州での生産拠点拡充により、供給能力と競争優位性のさらなる強化が見込まれる。これにより、短期的な株価調整局面を中長期の成長機会と捉える動きが広がりつつある。
PC更新需要や次世代車両向け市場の拡大も追い風となっており、ウォール街では引き続きMU株に対し「強く買い推奨」の評価が継続されている。
HBMとAI需要が牽引するマイクロンの業績拡大

マイクロン・テクノロジーは2025会計年度第2四半期において、データセンター向けDRAM売上で過去最高を記録し、HBMの四半期売上も10億ドルに達した。特にHBM分野では、前四半期比50%超の成長という著しい実績を示し、AIワークロードの拡大が同社の事業成長を直接的に押し上げたことが明白である。NVIDIAのGB200およびGB300にマイクロンのHBM3Eが採用されたことも、同社の技術的信頼性を裏付ける要素となっている。
また、マイクロンはHBM4を2026年に市場投入予定としており、帯域幅の60%超の向上を実現する計画である。これは今後のAI処理需要の爆発的な増加に対し、供給体制の整備と製品力強化が先手を打って進められていることを示す。同社は低消費電力型DRAMの唯一の大量供給企業でもあり、この点がデータセンター市場における競争優位性を支えている。
短期的な株価調整があったとはいえ、HBMやAI分野での明確な成果と戦略的製品展開は、今後数四半期の業績を支える土台となり得る。需要の先行きを見極めた技術投資が奏功しており、株価反発の可能性は十分に含まれている。
技術革新と設備投資が支える中長期成長戦略
マイクロンは「1-gamma」ノードを活用した次世代DRAMの開発において、極端紫外線(EUV)リソグラフィを導入し、消費電力20%削減、性能15%向上、ビット密度30%向上という飛躍的な性能改善を実現した。こうした革新的な製造プロセスは、コスト競争力と供給安定性を両立させる技術的優位性として際立っている。
さらに同社は2026年に向けた旺盛な需要に対応すべく、グローバルな生産体制の強化にも注力している。シンガポールでは先進的HBMパッケージング施設の建設が進み、米アイダホ州では新たなDRAM製造プラントが建設中である。既存施設の能力拡張と合わせて、これらの取り組みが中長期的な収益成長の基盤を築く。
こうした動きは、競合との技術差を拡げるだけでなく、サプライチェーンの安定化や顧客との契約交渉を優位に進める要因となり得る。供給リスクの高まる中で、生産インフラへの先行投資が、マイクロンに対する市場の評価を下支えしている側面も無視できない。
PC市場と自動車分野がもたらす新たな成長機会
2025年10月に予定されているWindows 10のサポート終了に伴い、PC市場では大規模な更新サイクルが到来する見通しである。これにより、高容量DRAMおよびSSDへの需要が一時的に加速することが想定され、その波に乗るかたちでマイクロンの製品出荷量にもプラスの影響が及ぶ可能性が高い。特に企業ユーザーの一斉更新が集中することが、需要の底上げに直結する。
また、自動車分野では次世代車両の複雑化と自動運転技術の進化により、車載メモリ需要が飛躍的に増加している。マイクロンは自動車向けDRAMおよびストレージ製品において業界をリードしており、複数のグローバルOEMと既に供給関係を築いている点が成長の追い風となる。
こうした異なる分野にまたがる需要の多様化は、業績の変動リスクを抑え、収益構造を安定化させる働きも持つ。マイクロンが複数の市場トレンドを的確に捉えたポートフォリオを構築できている点は、競合と比較しても優位性が際立つ。継続的な需要の取り込みが、株価の持続的な上昇を支える背景となり得る。
Source:Barchart.com