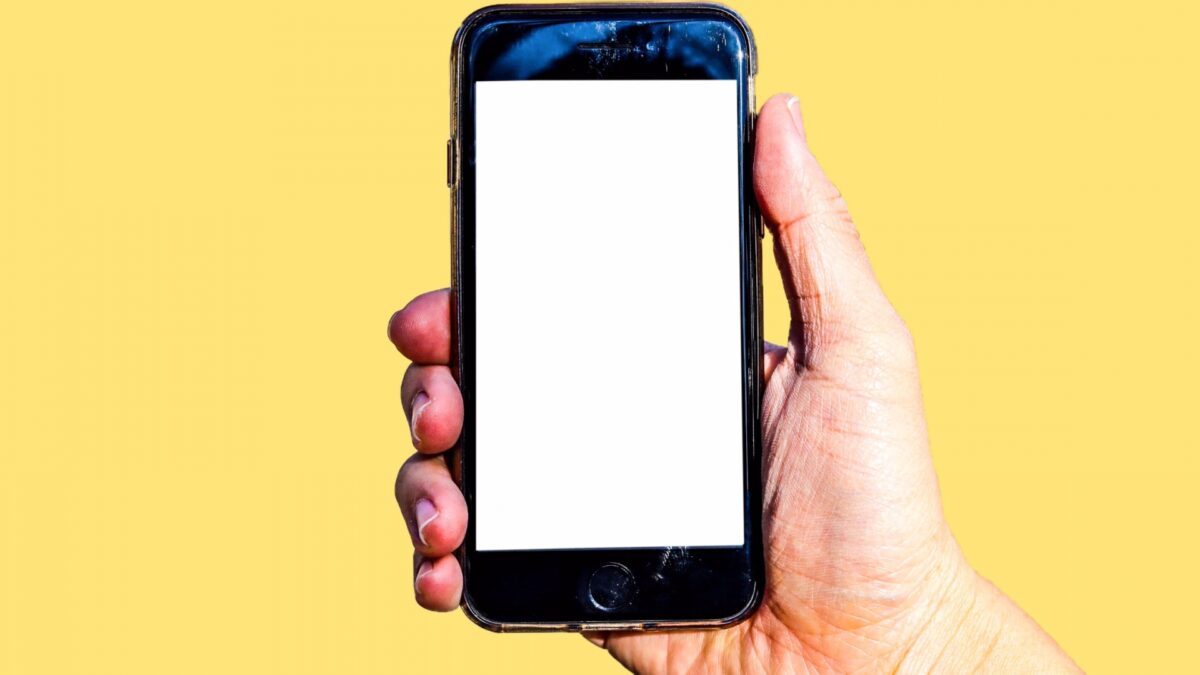Xiaomiがミッドサイクルモデル「Xiaomi 15S Pro」の発表に向けて動いていることが、リーク画像により明らかとなった。モデル番号「25042PN24C」、コードネーム「dijun」としてIMEIデータベースに出現していた本機は、XiaomiソフトウェアディレクターによるWeibo投稿から存在が判明。投稿は削除されたものの、リーカーKartikey Singh氏が画像付きで拡散した。
登場は4月第2週と予測されており、同時に14インチの大型タブレット「Xiaomi Pad 7 Max」も公開される可能性がある。注目すべきは、Qualcomm製ではなくXiaomi自社開発のXRING SoCを採用する可能性で、Leica監修カメラは15 Proから引き継がれる見込み。さらに、90W急速充電対応が3C認証で確認されており、今後の正式発表に期待が高まっている。
Xiaomi 15S Proの存在を裏付けたリーク情報とスペックの鍵

Xiaomi 15S Proの存在は、IMEIデータベース上の登録とWeiboでの画像投稿という複数のルートから明らかになった。モデル番号「25042PN24C」として先月確認されたこの端末は、コードネーム「dijun」を持ち、Xiaomiのソフトウェアディレクターの投稿によりそのビジュアルも一部露出している。現在その投稿は削除されているが、著名リーカーKartikey Singh氏による拡散によって話題が広がった。
設計面では、現行のXiaomi 15 Proと共通点が多いとされ、大幅な外観変更ではなく内部強化に重きが置かれている。注目は、Qualcomm製ではなくXiaomi独自開発とされるXRING SoCの搭載可能性だ。これが事実であれば、チップセットの自社化が進む中での大きな一歩となる。加えて、中国の3C認証を通過し、90Wの高速充電に対応している点も明らかになっている。
これらの情報から判断すると、15S Proは従来モデルの延長線上にありながらも、処理性能と電源周りに独自性を加えた中間モデルと位置づけられそうだ。完全な新シリーズというよりは、15 Proの完成度をさらに引き上げた上位互換的な存在となる可能性がある。
XRING SoC採用の可能性が示すXiaomiの方向性とその影響
Snapdragon 8 Eliteチップの投入時期が2025年10月と見られる中で、4月に登場するXiaomi 15S Proに関しては、同シリーズの他機種と性能バランスを維持しながらも、異なるチップを搭載することで差別化を図る動きがうかがえる。現時点ではQualcomm製ではなく、Xiaomiが開発するXRING SoCが選ばれる可能性が報じられており、これが実現すれば同社にとって戦略的な転換点となる。
XRING SoCは、性能や省電力性の詳細は不明ながらも、他社に依存しないアーキテクチャの構築を意味する。この流れは、近年AppleやGoogleが採用している方向性と一致し、Xiaomiも独自最適化によるUI体験や長期サポートを強化する可能性を持っている。ただし、完全に自社設計ではなく、外部IPの統合による半独自仕様である可能性も否定できない。
今後XRING SoCがXiaomiの主要機種に順次展開されるようであれば、同社の製品設計哲学は一段と変化し、ハードウェアとソフトウェアの統合が強まることになる。15S Proはその先駆けとなる存在として注目を集めるだろうが、最終的な評価は実機のパフォーマンス次第となる。
Pad 7 Maxの同時発表が意味する大型タブレット市場への本格参入
Xiaomi 15S Proと同時期に、14インチの大型タブレット「Xiaomi Pad 7 Max」が登場する可能性が伝えられている。タブレットとしては比較的珍しいサイズ感で、動画視聴やゲーム、マルチタスクを重視するユーザーに訴求する構成となりそうだ。従来のPadシリーズよりもさらに高性能かつハイエンドな仕様が期待され、15S Proとの同時発表が示すように、Xiaomiは春モデルでの製品ライン拡充を狙っている。
Pad 7 Maxの具体的なスペックはまだ公開されていないが、これまでのPadシリーズ同様、キーボードやスタイラスなどのアクセサリ対応が想定される。また、Snapdragon系の高性能チップセットや大容量バッテリーの採用がなされる可能性がある。Androidタブレット市場において、これほどの大画面を標準展開するブランドは限られており、Xiaomiが新たなポジションを築く契機にもなり得る。
同時発表という戦略は、スマートフォンとタブレットをセットで展開することでブランド体験を強化する狙いがあるようにも映る。特に自社SoCを搭載する15S Proと並べて発表されることで、Xiaomi製品全体のエコシステム構築がさらに進むのではないかという期待も高まっている。
Source:Gizmochina