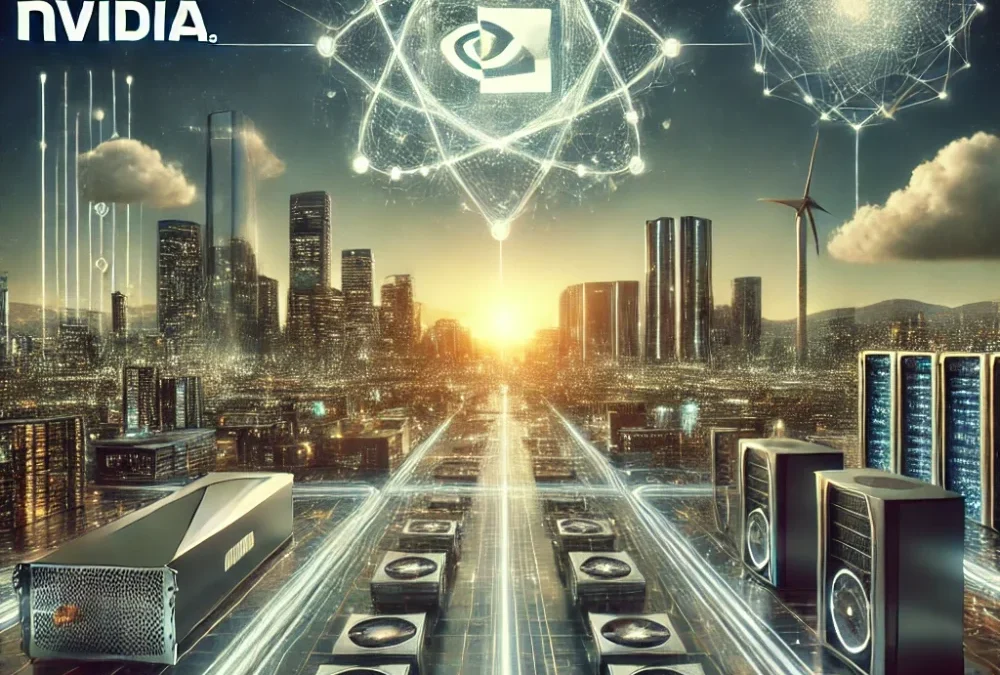NVIDIAはAI製品の刷新サイクルを半年単位に短縮し、2025年下半期にBlackwell Ultra GB300、2026年前半には次世代Vera Rubinの投入が視野に入る。これはGTC 2025での発表を皮切りに急加速しており、既にBlackwell GB200では歩留まり問題による供給遅延も発生している。
アナリストのDan Nystedt氏は、こうした強硬な製品展開がサプライチェーン全体の疲弊を招く可能性を指摘。HBM4メモリを製造するSK Hynixの生産スケジュールとも連動し、NVIDIAは業界標準を牽引する一方で、持続可能性への疑念も浮上している。
AMDを含む競合を突き放す意図があるとされるが、自社の供給網を圧迫するリスクは拭えない。CEOジェンスン・フアン氏の強気な姿勢の裏で、NVIDIAのAI支配戦略は転機を迎えている。
Blackwell GB200の歩留まり問題とサーバーメーカーへの波及
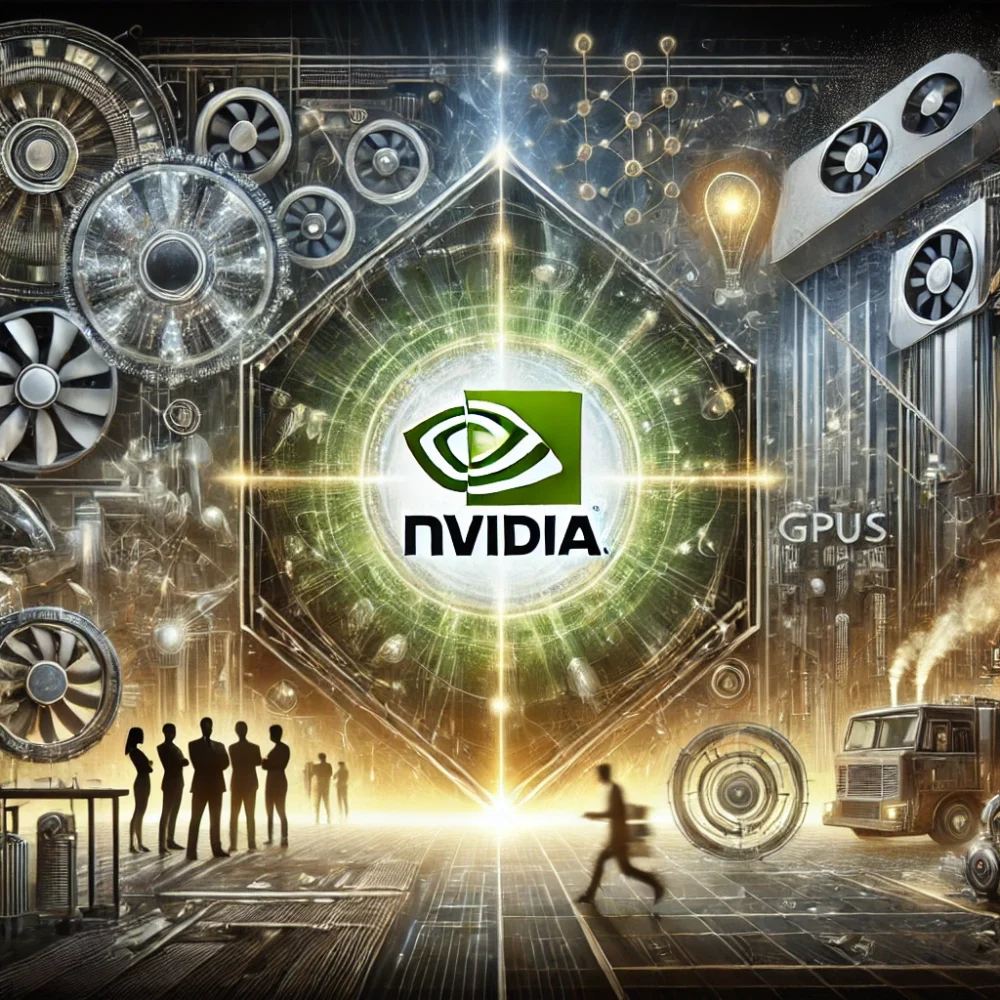
2024年第4四半期にNVIDIAが投入したBlackwell GB200は、限定的な数量でのリリースとなったが、その背景には生産効率の深刻な問題があった。
歩留まりの低さがサプライチェーン全体に影響を与え、Foxconnなど主要なサーバーメーカーの量産体制も2025年第1四半期後半にまで遅延を余儀なくされた。これは、NVIDIAが市場を主導する一方で、製品開発と供給網の調整が追いついていないことを露呈する事例となった。
ジェンスン・フアンCEOがこの歩留まり問題の存在を公式に認めたことは、異例であるといえる。通常、製品の不備に関する情報は表に出にくいが、今回の対応は事態の深刻さを物語っている。短期間でのアーキテクチャ刷新は、性能向上の期待と引き換えに、製造面での負担とリスクを抱え込む構造となっている。これは、高性能化を最優先する戦略がもたらす代償ともいえる。
サーバー事業者やクラウド企業にとって、こうした供給不安定は戦略的リスクに直結する。技術革新と供給のバランスが揺らぐ中、パートナー各社がNVIDIAとの関係性をどのように維持・調整していくのかが今後の焦点となる。
Vera Rubinの前倒しとHBM4メモリ供給の交錯が示す戦略的意図
GTC 2025にて発表された次世代アーキテクチャ「Vera Rubin」は、当初2026年末のリリース予定とされていたが、HBM4の量産スケジュールと連動し、最大で1年の前倒しが取り沙汰されている。
SK Hynixが2025年第3~第4四半期にHBM4の本格供給を開始する見込みであり、NVIDIAはこれにあわせて2026年第1四半期、あるいは2025年内にも一部製品を市場投入する可能性が指摘されている。HBM4という新規格を即時活用する企業は現時点でNVIDIAのみであり、その攻勢の姿勢は際立つ。
この動きは単なる技術進化ではなく、競争の土台を塗り替える試みと見なされる。AMDのInstinct MI300シリーズなど競合の追い上げに対し、NVIDIAは供給速度とアーキテクチャの更新頻度で優位性を確保しようとしている。市場に常に“次”を提供し続けることで、顧客の選択肢を事実上NVIDIA製品に固定化させ、競争の余地を削ぎ取る構図が生まれつつある。
ただし、半年単位の更新が常態化すれば、ユーザー側は安定性やROIの観点から導入を躊躇する可能性もある。NVIDIAにとって、革新の速度と市場の吸収力の均衡をどう保つかが次なる試練となる。
Source:Wccftech