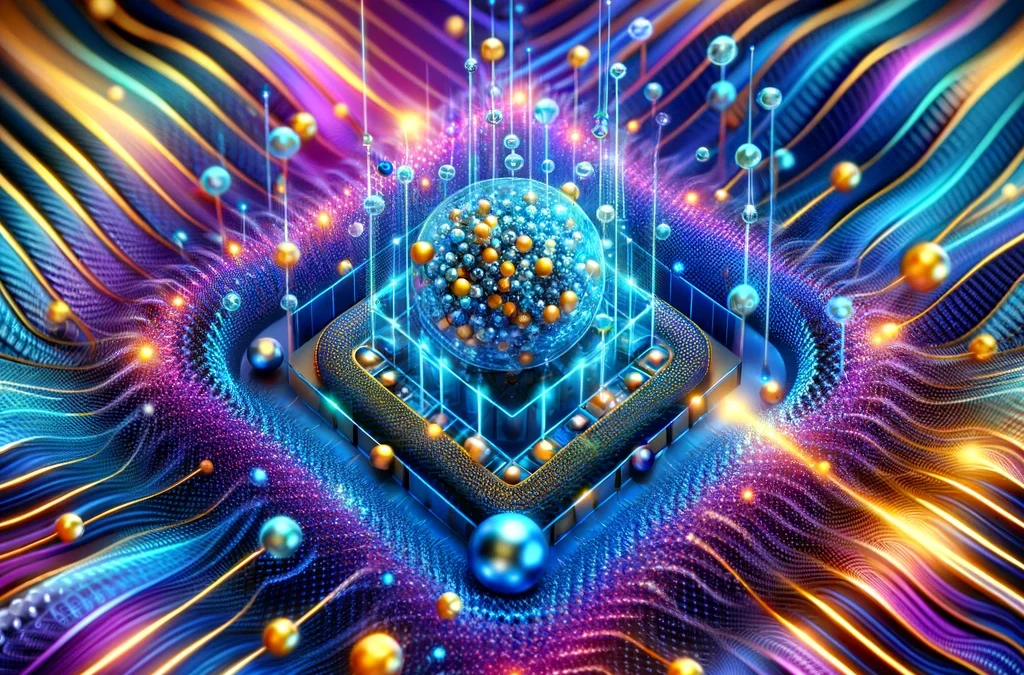Googleの次期フラッグシップPixel 10シリーズに搭載予定のTensor G5チップは、台湾TSMC製造による完全内製化とともに、Imagination Technologies製のDXT GPUを採用する可能性が高まっている。これにより、従来のSamsung製Arm Mali GPUからの転換が図られる見込みである。
この高性能GPUは、未発表のXiaomi 15S Proにも搭載されると噂され、両端末は同一アーキテクチャを共有する可能性がある。レイトレーシングや電力効率、描画性能の大幅な向上が予測され、ゲーミングやAI処理領域での競争力が一段と強化される見通しだ。
Xiaomiは4月第2週の発表が見込まれており、同GPUの採用は同社のグラフィック戦略における転換点となる可能性がある。
Tensor G5が示すGoogleの戦略転換とImagination Technologiesの台頭

Pixel 10シリーズに搭載される予定のTensor G5は、Samsung製造からTSMC製造への移行に加え、GPUにImagination TechnologiesのDXTシリーズを採用する可能性が報じられている。前世代のTensor G4がSamsungのArm Mali GPUを採用していた点と比較すると、今回の変更はGoogleの半導体設計思想の大幅な刷新を意味する。Imagination製GPUは、レイトレーシング処理や高負荷時の電力効率、描画の滑らかさといった分野で競争力があるとされる。
この変更は単なる性能向上にとどまらず、AI演算や高精細ディスプレイ表示、映像処理といった領域における体験向上をGoogleが重視している姿勢の現れと捉えられる。特にTSMCによる製造体制の確立は、安定したチップ供給や発熱・消費電力管理の最適化に繋がるため、ハードウェアの持続性や端末寿命にも関わってくる。これは、長期的にPixelブランドの差別化に寄与する可能性がある。
一方で、Imagination Technologiesの復権という側面も見逃せない。かつてAppleとの関係で注目された同社だが、モバイルGPU市場では長らく表舞台から遠ざかっていた。今回の動向は、再び主要プレイヤーとしての存在感を取り戻す契機になるかもしれない。
Xiaomi 15S Proが描くMali依存からの脱却と競争の次元上昇
Xiaomi 15S Proに関するリーク情報によれば、同端末もImagination Technologies製DXT GPUを搭載する可能性が高まっている。これが事実であれば、Xiaomiは従来のArm Mali GPU路線を脱却し、グラフィックス性能における新たなステージに踏み出すことになる。具体的には、レイトレーシングによるリアルな光表現や影の処理、レンダリング効率の向上によるバッテリー消費の最適化が挙げられる。
Xiaomiはこれまでハイエンドモデルにおいてもコストパフォーマンスを重視する戦略を取ってきたが、今回のGPU選定はプレミアム機としての付加価値創出を狙う動きと考えられる。カメラにLeicaレンズを採用するなど、映像体験への注力姿勢とあわせ、グラフィック性能を軸とした製品力強化は、フラッグシップ市場での競争構造に変化をもたらす要素となる。
中国メディアではXiaomi 15S Proが4月第2週に登場するとの観測もあるが、同時発表とされる14インチのタブレット「Xiaomi Pad 7 Max」との連携や、同社独自のXRINGプロセッサーとの組み合わせが、どこまで一貫性のあるユーザー体験を提示できるかが焦点となる。プラットフォームとしての完成度が問われる局面にある。
PixelとXiaomiの共通GPUが示唆するモバイルグラフィックスの転機
Google Pixel 10シリーズとXiaomi 15S Proという、設計思想の異なる2社の次世代端末が、同一のGPUを搭載する可能性が浮上している。Imagination Technologies製のDXT-48-1536は、高い描画性能に加え、レイトレーシングやAI処理との親和性を兼ね備えており、これまでスマートフォン市場を牽引してきたMaliやAdrenoといったGPUとは異なるアプローチをとる。
この共通項の出現は、モバイルグラフィックスの技術的転換点を象徴する兆候とも読める。端末メーカー間での明確な差別化が難しくなる中、ソフトウェア最適化やAIとの連携、処理効率の細部が最終的なUXに大きく影響する段階へと進化している。特にアニメーション処理やゲーミング、コンピュテーショナルフォトグラフィーといった分野では、GPUが体験の質を決定づける要素となりつつある。
市場全体としても、従来の定番GPUに代わる選択肢が現実味を帯びたことは、チップサプライチェーンの多様化にも繋がる可能性を含む。今後は、単一ブランドではなく、用途特化型や最適化指向のGPU戦略が評価されるフェーズに入るだろう。これにより、モバイル端末開発における重心が「CPU優位」から「GPU重視」へと移行する動きも加速することが予測される。
Source:PhoneArena