AppleはMacBook Air M4を発表し、2022年登場のM2モデルを基盤としつつ、最新のApple Silicon「M4」チップを搭載して性能の大幅な向上を果たした。GeekbenchスコアではM2の約1.5倍に達し、メモリ帯域幅や最大構成容量も強化されている。
両モデルは13インチと15インチの2サイズ展開、デザインやディスプレイ仕様は共通だが、M4では新色スカイブルーが加わり、外部ディスプレイ2台接続や12MPカメラ対応、追加マイクモードなど差別化要素が存在する。
ただし、M2の完成度も依然高く、多くの機能が共有されている点を踏まえると、価格と用途のバランスが選定の鍵となり、単純な上位互換とは言い難い側面も残る。
M4チップがもたらす処理能力の飛躍と冷却設計の限界
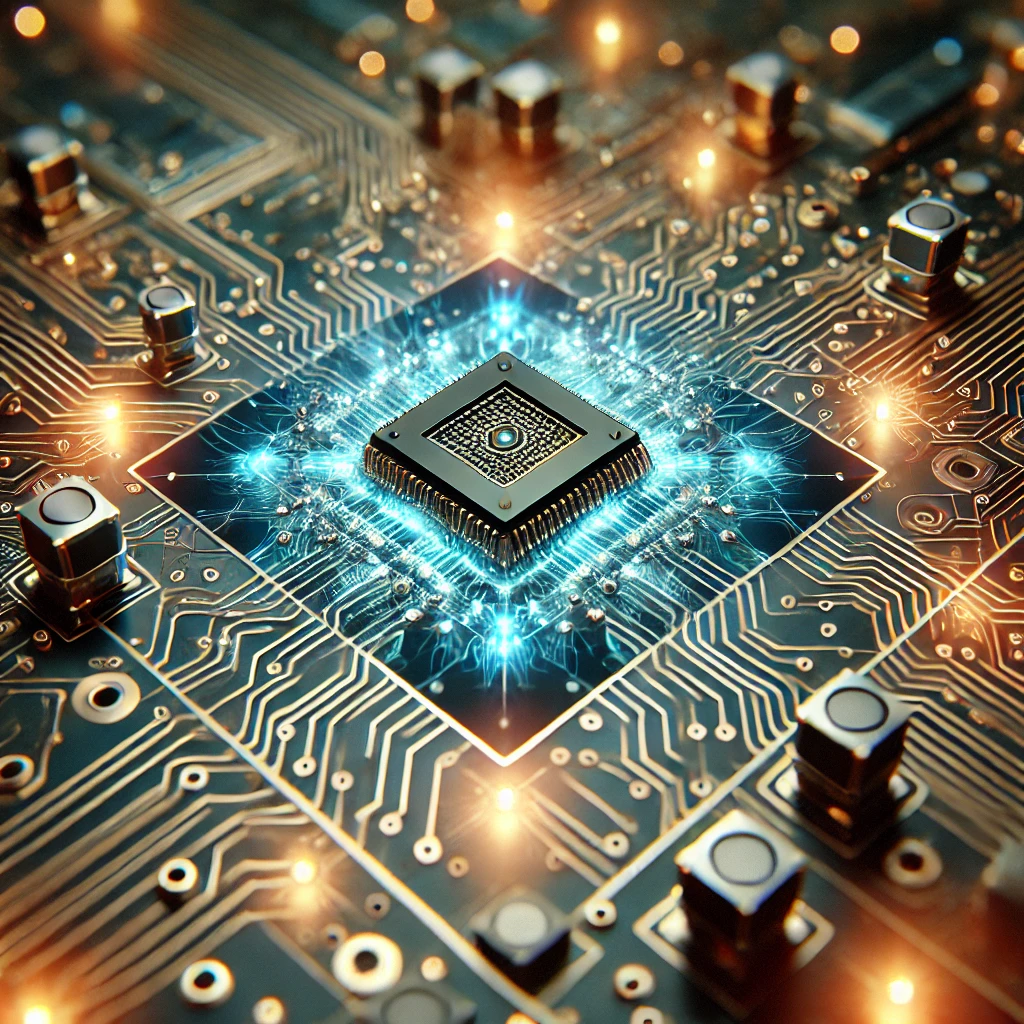
AppleがMacBook Air M4に搭載した最新のApple Silicon「M4」チップは、3nmプロセスで製造され、28億トランジスタ、10コアCPU構成、120GB/sのメモリ帯域幅を備える。Geekbenchマルチコアスコアでは14,819を記録し、M2の9,728に対して圧倒的な処理能力を示した。Eコアの増加と高クロック化により、マルチタスクやAI演算において顕著な性能差を見せている。
一方で両モデルともファンレス設計である点は、長時間の高負荷処理時にサーマルスロットリングを招く要因ともなる。M4の処理能力を完全に引き出すには、冷却面でのハードウェア的制約が付きまとう。ハードウェア進化の速度に対し、設計思想がそれに追随しきれていない構図が浮かび上がる。
つまり、M4は確かにパフォーマンス面で大幅な前進を遂げたが、Airシリーズに固有の静音性と軽量性を守るため、あえて冷却機構に制限を課したことが、性能発揮の持続性という観点で一つの課題となり得る。処理能力と設計哲学の折り合いが、ユーザーの用途選定に影響を及ぼす構造となっている。
外部ディスプレイ対応や新機能が示すプロ用途への接近
MacBook Air M4は、外部ディスプレイを最大2台まで(最大6K出力)サポート可能となり、これは従来のAirモデルでは見られなかった明確な進化である。M2では外部モニターは1台のみに制限されており、複数画面による作業環境の構築を前提とする層にとっては制約となっていた。この点において、M4はより本格的な制作・開発環境に耐えうる仕様へと接近している。
加えて、M4では12MPカメラやVoice Isolation/Wide Spectrumなどの音声処理モードが導入され、Web会議や収録品質にも配慮が見られる。これらの要素は、Airシリーズの“軽量ラップトップ”という枠組みを超え、クリエイティブ用途やビジネスコミュニケーションにおける実用性向上を目指したものと捉えられる。
ただし、本体デザインやポート構成、バッテリー性能、ディスプレイ輝度はM2とほぼ共通であるため、利用シーンの変化が必ずしも購入動機に直結するとは限らない。拡張性やマルチディスプレイ対応に重きを置くユーザーにはM4が魅力となるが、軽作業中心の利用にはM2でも十分な機能を提供している。
Source:PhoneArena

