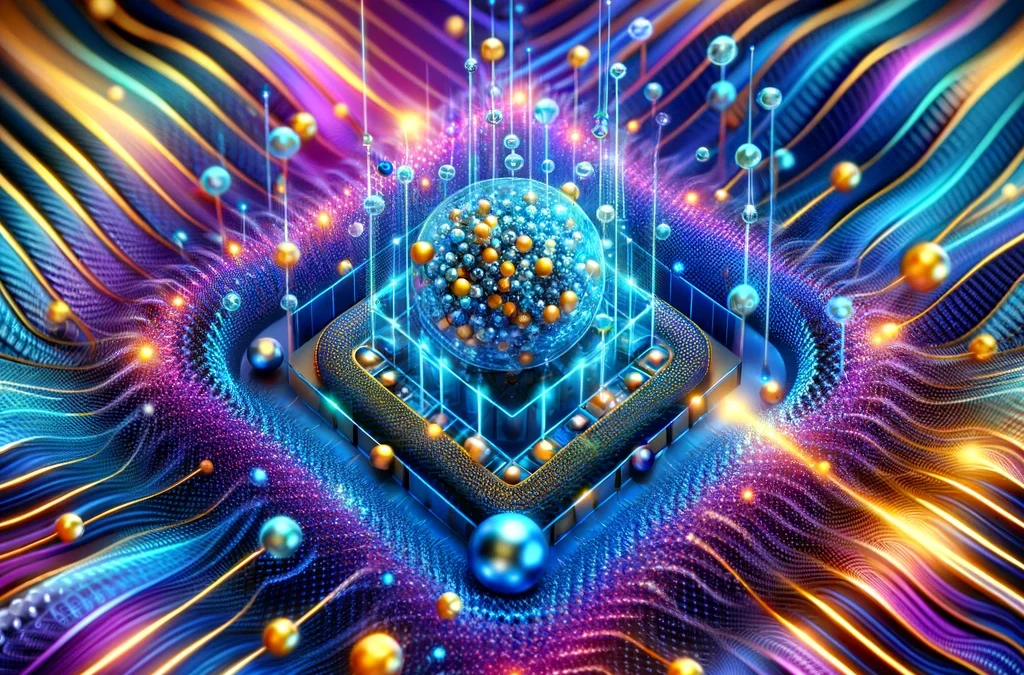米Intelが開発中の次世代プロセスノード「18A」に対し、Nvidiaが製造委託先として関心を示している。UBSのアナリスト、ティモシー・アーキュリ氏の報告によれば、IntelとNvidiaはBroadcomよりも進んだ交渉段階にあり、ゲーミングGPUへの適用も視野に入るという。
インテルはTSMCに対抗すべく、自社ファウンドリ事業に注力してきたが、「18A」はその中核であり、Microsoftや米国防総省との契約も進行中。新CEOリップ・ブー・タン氏の下、ファブレス企業との連携が加速する可能性がある。
Nvidiaが国内製造を模索する背景には、中国経由の部材への関税リスクや米国市場での価格安定化があるとされ、TSMCのアリゾナ工場に加え、Intelとの協業も戦略的選択肢の一つとみられている。
Intelの18Aノードが狙うファウンドリ戦略の核心

インテルが現在最重要視しているプロセスノード「18A」は、1.8nm相当の微細化技術を特徴とし、同社の半導体製造再建の要として位置づけられている。2025年内の量産開始が予告されており、Microsoftや米国防総省との契約を通じてその実用性はすでに市場に示され始めている。
TSMCのN2と同世代であるが、18Aはトランジスタ密度および電力効率の点で競争優位に立つ可能性があるとされ、Samsungを含む他の競合とともに次世代製造技術の主導権を争う構図が鮮明になりつつある。
2023年に「20A」ノードの開発を中止したことにより、インテルは経営資源を18Aに一本化し、製造技術の確立とファウンドリ事業の信頼回復に集中してきた。その結果、NvidiaやBroadcomといったファブレス企業との交渉においても、一定の存在感を発揮できる状況が整ってきたといえる。ただし、量産が本格化するまでの信頼確立には課題が残されており、顧客にとっては製造能力だけでなく供給の安定性が重要な判断基準となる。
こうした中、製造受託の拡大は、インテルにとって自社製品依存からの脱却を図る好機でもある。とりわけ米国内製造へのシフトという地政学的要因が、同社の競争戦略に新たな意味をもたらしている。
Nvidiaの動向が映す米中テック冷戦と製造地リスクの再構築
NvidiaがIntelの18Aノードを採用する可能性が報じられた背景には、単なる技術的な要因にとどまらず、国際的な供給網に対する再評価の動きがある。これまで同社はTSMCを主たる製造パートナーとしてきたが、RTX 30シリーズではSamsungを採用するなど、製造地の多様化を図ってきた。特に中国経由の部材に対する米国の関税措置を受け、台湾を経由しない調達経路を確保することは、Nvidiaにとって価格安定と供給安全の両面でリスクヘッジとなる。
NvidiaのCEOがTSMCのアリゾナ新工場を視察対象としている事実も、同社が今後の製造を米国内に取り込むことに本腰を入れている証左といえる。インテルの18Aが量産体制に入れば、国内調達を実現するもう一つの有力候補として台頭する可能性は否定できない。これにより、TSMCへの依存度が相対的に低下することになれば、半導体業界の供給構造にも一定の変化が生じる。
もっとも、NvidiaとIntelの協業は、技術的な選好だけでなく、価格交渉や製造体制の柔軟性といった経済的要素にも左右される。現時点ではまだ正式合意には至っていないものの、もし提携が現実となれば、ファブレスとファウンドリの力関係を揺るがす象徴的な事例となる可能性がある。
Source:XDA