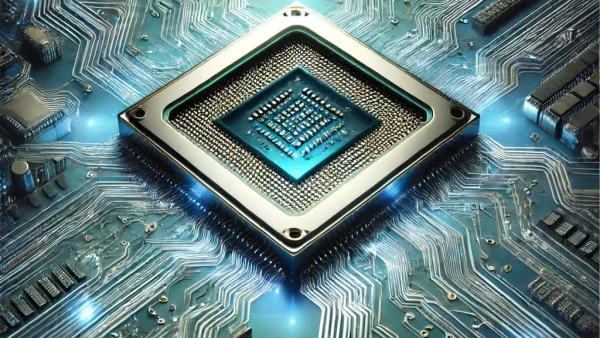AMDは韓国での技術イベントにおいて、ノートPC向けCPUの新たな展開として「Gorgon Point」の存在を明らかにした。これはRyzen AI 300(Strix Point)のリフレッシュ版にあたり、最大12コアとRDNA 3.5 GPUを維持しつつ、クロック向上とAI演算性能の強化を特徴とする。製品名はRyzen AI 400として登場し、一部モデルでは55TOPSのNPU性能も確認されている。
このGorgon Pointは、2026年まで段階的に展開される見通しで、低価格帯にはKrackan Pointが、Copilot+対応では上位構成がそれぞれ充当される。AMDはZen 6を採用する次期アーキテクチャ「Medusa Point」も準備しているが、Gorgon Pointによって移行時期は後ろ倒しとなる可能性がある。
チップレット化やARM採用の「Sound Wave」構想なども含め、AMDのノート向け戦略は多層的な進化を見せている。
Gorgon Pointの技術的進化と市場投入の背景
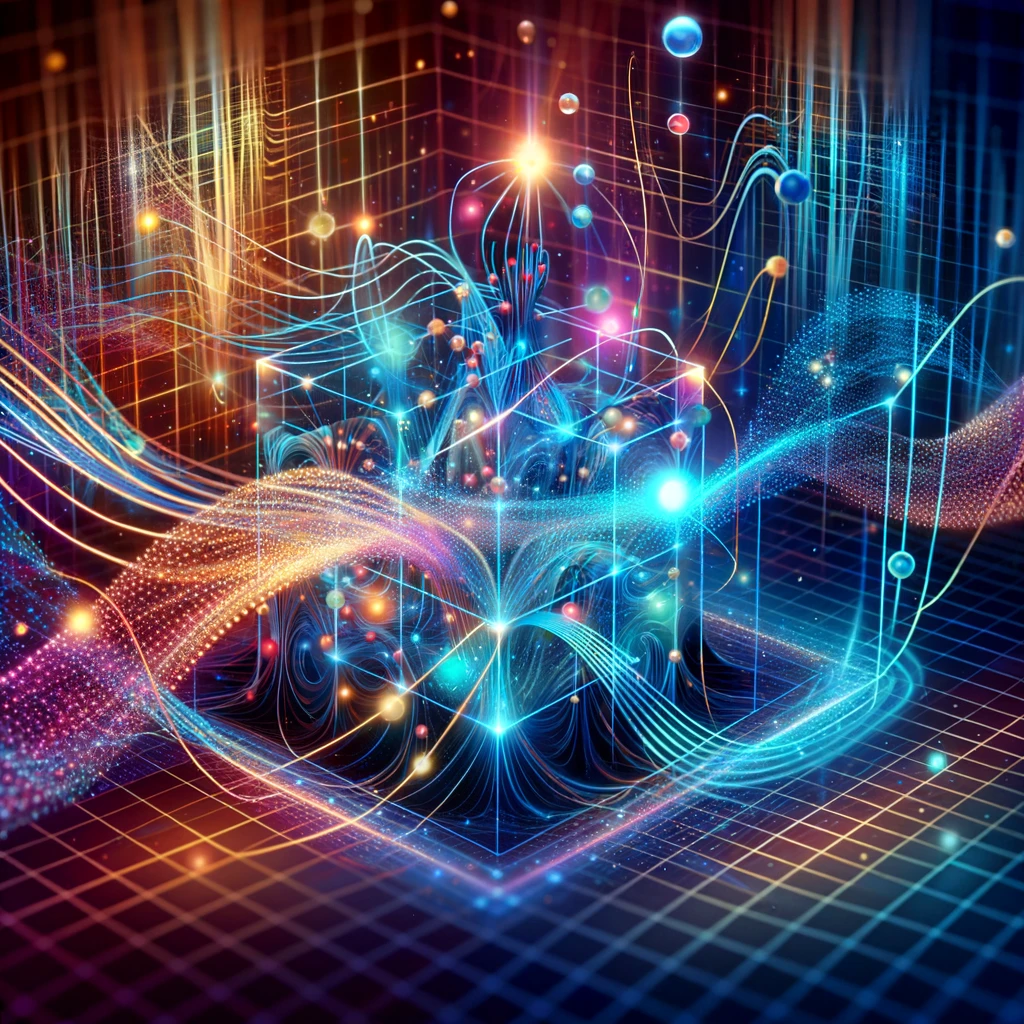
AMDが公開したGorgon Pointは、Ryzen AI 300(Strix Point)のリフレッシュ版であり、Zen 5アーキテクチャを基盤にしつつ、クロック周波数の向上やAI演算性能の微細な強化が施されている。
最大12コア構成やRDNA 3.5 GPUといった主要スペックは維持されたまま、1秒あたり55兆回の演算を可能とするNPUが一部モデルに実装され、Ryzen AI 9 HX 375と同等の処理性能が期待される。2026年までの製品展開が示唆されており、製品群は「Ryzen AI 400」として整理される見込みだ。
このリフレッシュ戦略は、かつてのPhoenixおよびHawk Pointの関係性を彷彿とさせるもので、AMDは過去にも最適化による展開延命を図ってきた経緯がある。
今回のGorgon Pointも、Strix Pointを基盤とした製品寿命の延長と、Copilot+対応を視野に入れた性能調整の一環と考えられる。これにより、短期的にはAI対応ノートPC市場における競争力維持を狙う一方、Zen 6世代に向けた開発の時間的猶予も確保する狙いが読み取れる。
Zen 6への移行とAMDの戦略的分岐点
Medusa Pointは、Zen 6アーキテクチャを搭載した次世代CPUとして言及されており、最大12コア構成や新たなチップレット設計の導入が予想される。これまでノート向けCPUにおいては一貫してモノリシック構造を採用してきたAMDが、デスクトップ同様にチップレット構成へと舵を切る可能性は、開発コスト削減と製品ラインナップの汎用性向上という観点から注目に値する。
Strix Haloと類似したSoCドッキング型設計によって、デスクトップとノートの部品共通化が進む可能性がある。
ただし、Gorgon Pointの展開が2026年まで継続する見通しであることから、Medusa Pointの投入は2026年の年初ではなく、それ以降になる公算が大きい。名称が「Ryzen AI 500」となるか、再び変更されるかは明らかでないが、Zen 6移行は設計上の転換点ともなる。
AMDにとって、パフォーマンス重視のラインとコスト重視の製品群とを明確に二分化し、それぞれに最適なアーキテクチャを配分する戦略が加速する転機となるだろう。
ARMコア採用のSound Waveが示唆する方向性
AMDが開発中とされる「Sound Wave」は、既存のx86アーキテクチャから離れ、ARM命令セットを採用するという点で異彩を放っている。Mendocinoの後継として位置づけられるこの低価格帯向けプロセッサは、Pコア2基とEコア4基というARM系構成が想定されており、性能よりも価格競争力を優先した設計が見込まれる。
AMDは長らくx86の廉価版Eコアを持たず、同市場における不利を抱えていたが、Sound Waveがその空白を埋める役割を担う可能性がある。
とりわけ、Windows on ARMの普及を視野に入れると、AMDによるARM採用は大きな意味を持つ。QualcommのSnapdragon Xといった競合に対抗する上で、低価格帯から市場を攻略する戦略的足掛かりともなり得る。
現時点で詳細な仕様や発売時期は不明であり、開発は一時的に沈黙しているものの、仮にMicrosoftとのセミカスタム契約に基づく製品化が実現すれば、PC市場のアーキテクチャ競争において新たな潮流を形成することになるだろう。
Source:heise online