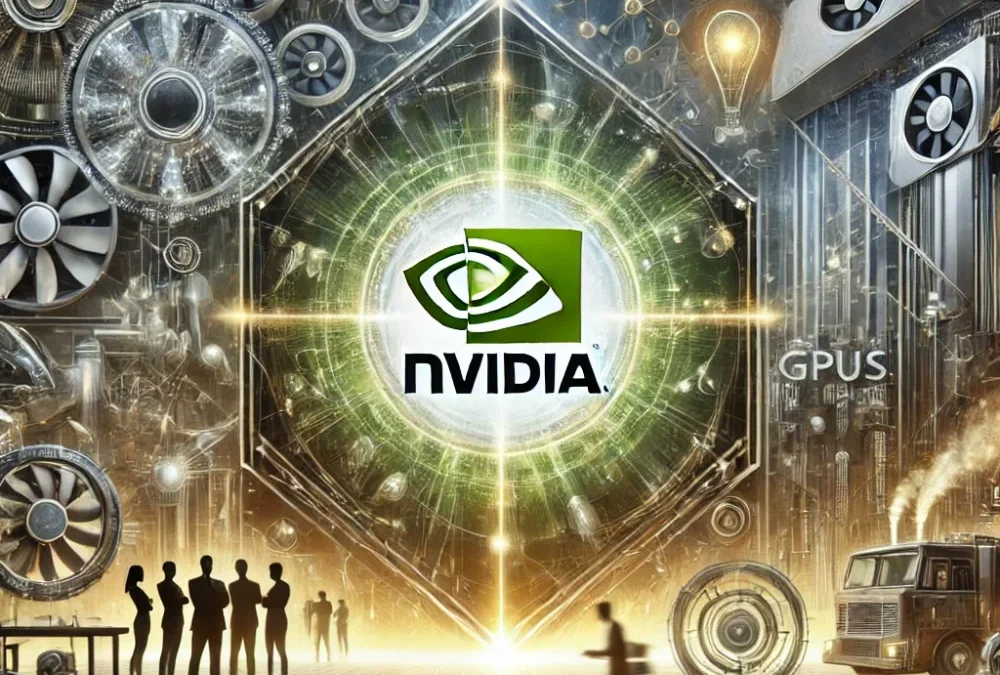スイスUBSのアナリスト、ティモシー・アークリ氏によれば、Nvidiaが将来のゲーミングGPUの一部にIntelの次世代18Aプロセスを採用する可能性が浮上している。18Aは1.8nmクラスに位置づけられる先端製造技術で、電力効率を重視する18APの登場も見込まれる中、IntelにとってはTSMCへの対抗策として大きな意味を持つ動きとなりうる。
アークリ氏は、新CEOリップ・ブー・タン体制下で、Intelがチップ設計への回帰とファウンドリ事業の巻き返しを図り、Nvidiaのような戦略顧客獲得を加速させると見ている。TSMCのCoWoSに対抗し得る独自のパッケージ技術EMIBも鍵となる要素とされ、4月29日の「Direct Connect」イベントでの具体的発表に注目が集まる。
この動向は、Intelがファウンドリ市場で再び存在感を高めようとする兆しとして注目されており、業界再編の一端を担う可能性がある。
NvidiaがIntelの18Aプロセス採用に接近 UBSアナリストが指摘する供給網の再編可能性

UBSのティモシー・アークリ氏によると、Nvidiaは次世代ゲーミングGPUの一部にIntelの18Aプロセス技術を利用する方向で検討を進めているという。18AはIntelが現在開発中の1.8nm級のトランジスタノードであり、低電力仕様の18APも存在することから、高性能と電力効率の両立を志向するGPUメーカーにとって魅力的な選択肢とみられる。
この動きが現実化すれば、長らくTSMCに依存してきたNvidiaのサプライチェーン構造に変化が生じることになり、製造多様化の一環として注目される。Intelにとっても、Nvidiaという大口顧客の獲得は、ファウンドリ事業の信頼性回復における重要な前進と捉えられる。特に、近年技術開発の遅延でTSMCやSamsungに後れを取ってきた同社にとって、競争力の象徴ともなりうる案件である。
もっとも、現時点ではこの情報はアナリストの見解に基づくものであり、具体的な契約や製品ロードマップは明かされていない。4月29日に予定されるIntelのイベント「Direct Connect」での発表が、これらの動向を裏付ける機会となる可能性がある。
新CEOリップ・ブー・タンの戦略的転換点 パッケージ技術EMIBが担う役割
Intelの新たな経営トップに就任したリップ・ブー・タン氏は、ファウンドリ部門の競争力強化を急務とし、顧客基盤の再構築に取り組む姿勢を明確にしている。
氏はかつてCadence Design SystemsでCEOを務めた経歴を持ち、設計と製造の融合に対する理解が深いとされる。その戦略の柱のひとつが、次世代パッケージ技術「EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)」の推進である。
EMIBは複数のチップを高密度に接続する技術であり、TSMCのCoWoS(Chip on Wafer on Substrate)と競合する位置づけにある。NvidiaのようにAIやゲーム処理に特化したマルチチップ構成が進む中で、パッケージ技術の優劣は製品性能と納期の両面で決定的な要因となる。
IntelがEMIBを通じて競合技術に対抗する構えを見せる背景には、単なるプロセス競争だけでなく、トータルなプラットフォーム提供企業としての地位確立がある。
タン氏の戦略は、NvidiaやAppleといった他社の高性能チップを一部でも取り込むことで、Intelのファウンドリへの信頼感を再構築しようとする点に特色がある。UMCとの提携を通じたApple関連の生産についても指摘がなされており、今後の受託生産体制の再編において、台湾勢との新たな力学も視野に入るだろう。
Source:TechSpot