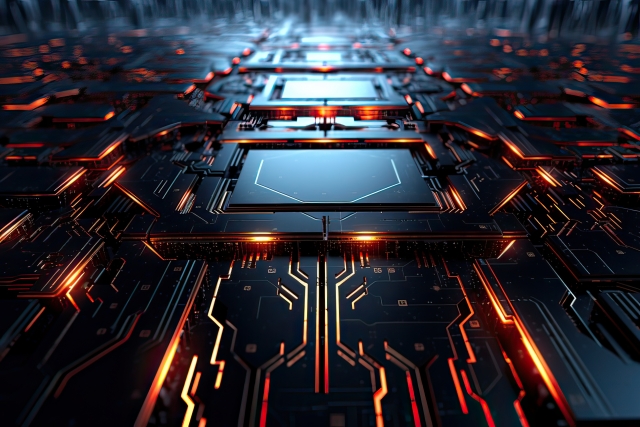インテルが新たに投入したモバイル向けフラッグシップCPU「Core Ultra 9 275HX」が、ゲーミングノートPC「Gigabyte Aorus Master 16」に搭載され、競合各社の最上位モデルとの比較検証が進んでいる。
ベンチマーク結果では、従来の第14世代「i9-14900HX」に対し最大で約10%の性能向上が確認され、AMD「Ryzen AI 9 HX 370」や「Ryzen AI Max+ 395」、さらにはAppleの「M4 Pro」にも肉薄する数値を記録した。
一方で、ハイパフォーマンス志向ゆえにバッテリー寿命ではMacBook Proに及ばないものの、RTX 5080との組み合わせによりゲーム時の駆動時間は前世代比で大幅に改善された。ウェブ閲覧では5時間31分、ゲーム時は2時間54分と、ライバル機種を上回る持続力も見せた。
今回の「Arrow Lake HX」世代は、特に第11世代以前のユーザーにとって明確な買い替え動機となる性能向上を提示しており、Apple Siliconとの直接対決においても一定の存在感を放ち始めている。
Core Ultra 9 275HXが示した性能向上の実態と主要競合との比較分析

Intelの最新モバイル向けCPU「Core Ultra 9 275HX」は、14世代Raptor Lake Refresh HXと比較してシングルスレッド性能で5.7%、マルチスレッドでは9.8%の向上を記録した。
Geekbench 6やCrossMarkなど複数のベンチマークにおいて数値的な優位性が確認され、特に同等クラスの競合機であるRazer Blade 16(Core i9-14900HX搭載)や、Ryzen AI 9 HX 370搭載モデルとの比較では、総合的な演算処理能力の強化が明確に示された。
また、AppleのM4 Proに対してもシングルコア性能で僅差に迫っており、従来のIntelモバイルチップが置かれていた劣勢状況を一定程度打破する内容となった。ただし、今回登場したのはフラッグシップの「275HX」であり、「285HX」が控えている点を踏まえれば、今後の上位モデルにさらなる性能向上が期待される。
現時点でも、Ryzen AI Max+ 395に肉薄するなど、ゲーミング用途に限らず、動画編集やマルチタスクを要求されるワークロードにおいても、確かな戦力として台頭しつつある。
このように、世代間での技術進化が確実に数字として表れたことは重要であり、従来モデルからの買い替え検討を後押しする要因となる。特に第11世代以前のIntel搭載ノートを使用するユーザーにとっては、その性能差は劇的といえる。
高性能ゆえの電力消費と対比されるバッテリー駆動時間の進化
高性能志向のArrow Lake HXシリーズは、電力消費を犠牲にしてでも演算性能を追求する設計思想に基づいており、今回搭載された「Core Ultra 9 275HX」も例外ではない。TDPは55Wと高めに設定され、さらにGPUにはNvidiaのRTX 5080を組み合わせる構成であり、最大消費電力は230Wにも達する。これにより、バッテリー駆動時間は限定的でありながらも、実際のベンチマークでは意外な健闘が確認された。
PCMark 10によるゲーム中のバッテリー持続時間は2時間54分と、同クラスのi9-14900HX/RTX 4090搭載機を大きく上回る結果を出している。ウェブ閲覧においても5時間31分を記録し、ゲーミングノートとしてはまずまずの結果となった。これは、RTX 5080が搭載する「Battery Boost」技術の効果によるものであり、消費電力の効率化が進んだことを意味する。
一方で、Ryzen AI Max+ 395を搭載するAsus Flow Z13がウェブ閲覧で10時間超を記録するなど、省電力設計を優先した競合との間には依然として明確な差が残る。AppleのMacBook Pro 16(M4 Pro)の長時間駆動性能と比べると、その差はさらに顕著である。
ただし、Arrow Lake HXはArmベースの設計とは異なるカテゴリに属しており、純粋な比較は難しい。現段階では「性能重視だが、省電力技術にも一歩踏み込んだ」転換点と捉えるのが妥当であろう。
Source:LaptopMag