AMDは、次世代APU「Strix Point」をRyzen 9000Gシリーズとして2025年第4四半期に投入する見通しとなった。リーク情報では、AM5ソケットに対応し、Zen 5アーキテクチャを採用した12コア24スレッドCPUと、統合型RDNA 3.5 GPUを搭載するという。
従来のデスクトップ向けAPUが最大8コア16スレッドであったのに対し、大幅なスペック強化が図られる形となる。冷却性能や電力供給の余裕があるデスクトップ環境において、GPUクロックは3.0GHz超も視野に入る。
Strix PointがもたらすRyzen APUの進化点
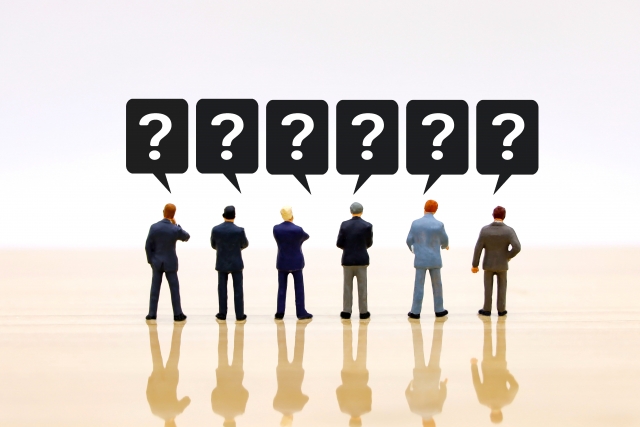
Ryzen 9000Gシリーズは、これまでのAMD製APUの常識を覆す仕様となっている。Zen 5アーキテクチャを採用し、CPUは12コア24スレッドというスペックを実現。従来の8コア16スレッドを上限としていたAPUの性能を大幅に押し上げる構成となっており、単なる内蔵GPU搭載の省電力モデルという枠を超えた存在になりつつある。
加えて、RDNA 3.5世代のGPUを統合しており、モバイル版Ryzen AI 9 HX 370で搭載されているRadeon 890Mと同等のグラフィックス性能が期待されている。モバイルでは最大2.9GHzで動作するこのGPUは、デスクトップ向けではさらに高クロックが見込まれており、3.0GHz超の動作も可能とされる。冷却性能や電力供給に余裕のあるデスクトップ環境において、このアドバンテージは無視できない。
この構成から見えてくるのは、APUが補助的な役割ではなく、フルスペック構成の主力CPUとしての地位を狙いに来ている点である。ゲーミングから軽量なAI処理まで、単体GPUに依存せず一定水準のパフォーマンスを出す選択肢として、Ryzen 9000Gシリーズは新たな選択肢となる可能性がある。
デスクトップ版Strix Pointの戦略的意義と冷却設計の余地
Strix Point APUがデスクトップ向けとしてRyzen 9000Gシリーズの名で登場する背景には、AMDのプラットフォーム戦略と電力設計の柔軟性がある。これまでノートPC向けに開発されてきたStrix PointアーキテクチャをAM5ソケットに対応させることで、従来のデスクトップ用APUとは異なる性能域に踏み込む狙いがあるとみられる。
特に、Strix Pointの性能を引き出す上で鍵となるのが電力と冷却である。モバイル環境では制限のあったTDPも、デスクトップではより高い電力供給が可能となる。これにより、CPU・GPUのブーストクロックが一段と引き上げられ、たとえばRadeon 890Mの2.9GHzという上限も、冷却次第では3.2GHz前後まで到達する可能性が考えられる。
加えて、フォームファクターの自由度が高いデスクトップでは、水冷や大型空冷による冷却強化も容易であり、クロック制限の緩和や高負荷時の安定性向上につながる。Strix PointのようなAPUがパフォーマンス面で妥協のない設計へと進化することで、内蔵GPU搭載モデルに対する認識が大きく変わる可能性もある。
Ryzen 9000G登場によるラインアップの棲み分けと選択の幅
Ryzen 9000Gシリーズの登場は、既存のRyzenラインアップとの棲み分けに注目が集まる。これまでのAPUは、エントリー~ミドルレンジ帯でのGPUレス運用や、スリムPC用途が中心だったが、12C/24Tというスペックは、従来のRyzen 7クラスを上回るものであり、Ryzen 9シリーズとの重複も意識せざるを得ない。
現時点でStrix Point APUに外部GPUとの併用を前提とした高帯域I/O構成が含まれるかは不明だが、単体でのグラフィック性能が向上することで、ミドルレンジ帯のdGPU搭載構成を選ぶ意味合いが薄れるケースも考えられる。価格次第では、グラボ不要のハイパフォーマンスPC構成が現実味を帯びてくる。
一方で、APUが高性能化すればするほど、ユーザーはCPU単体での運用か、外部GPUとの組み合わせを取るかの選択を迫られることになる。Ryzen 9000Gシリーズは、その中間に位置する「捨てずに済む性能」を備える存在として、構成の自由度を高める役割を担う可能性がある。
Source:TweakTown

