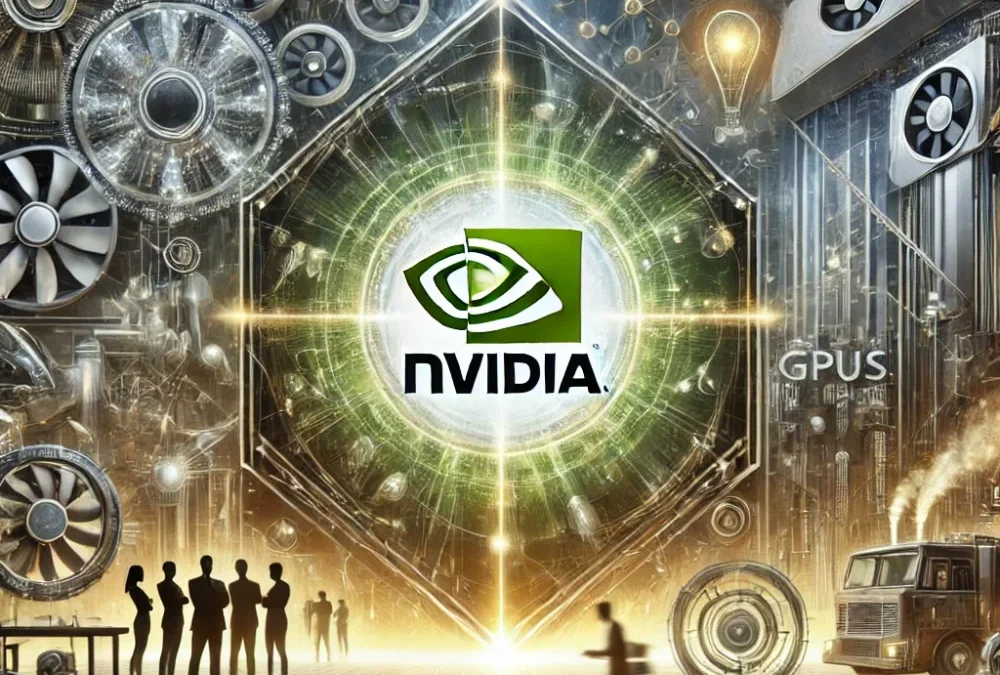かつての王者インテルが、Nvidiaの新たな製造パートナー候補として浮上している。UBSのアナリストが指摘するように、Nvidiaはゲーム用GPUの一部製造をTSMCからインテルに移す可能性がある。背景にはTSMCの供給逼迫があり、省電力型「Intel 18A」ノードが代替先として注目を集めている。
新CEOリップ・ブー・タンの下、インテルは製造受託事業の強化に注力し、次世代チップ技術と西側諸国からの巨額支援を武器に再起を図る。業績にはまだ課題が残るが、ファウンドリとしての転機となるかが焦点である。競争力回復と市場再定義の鍵を握る数年が始まろうとしている。
NvidiaがIntel製造ノードに関心 供給リスク分散が狙いか
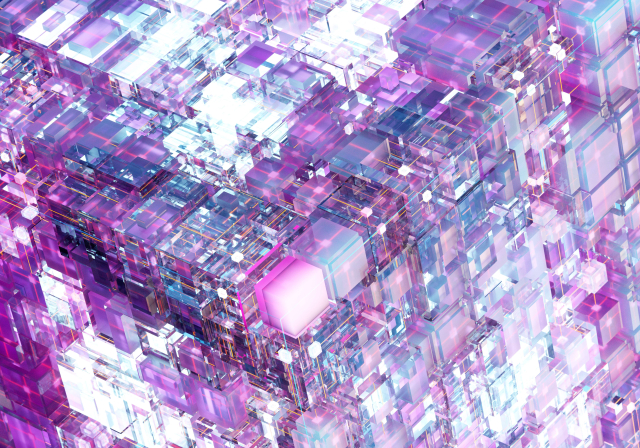
UBSのティモシー・アークリ氏によると、Nvidiaはインテルの次世代製造技術「Intel 18A」に注目しており、特にゲーム用GPUの製造に関して提携が検討されているという。これまでTSMCが一手に担ってきた製造ラインだが、急増するAI需要により供給能力に限界が生じている。NvidiaはAIチップ製造をTSMCに維持しつつ、ゲーム分野においては他の製造先を模索しており、その有力候補としてインテルが浮上している。
この動きは、単なる製造委託先の変更にとどまらない。TSMCへの依存度を引き下げることで、地政学的リスクの回避や供給安定性の向上といった戦略的意味合いを持つ。TSMCの台湾集中型の体制は、中国との緊張が続く中で中長期的なリスクと捉えられており、欧米の顧客にとっては多様な製造パートナーを確保する必要性が高まっている。Intel 18Aが実用段階に達すれば、性能面でも代替可能な水準にあるとされ、選択肢として現実味を帯びてきた。
インテル再建のカギを握る「Intel 18A」とリップ・ブー・タン体制
Cadence Design Systemsを飛躍的に成長させた実績を持つリップ・ブー・タン氏が、再建を託されたインテルで最重視しているのが「Intel 18A」ノードである。リボンFETと呼ばれる新トランジスタ技術を採用し、TSMCのN2ノードに匹敵、あるいはそれを上回る電力効率が期待されている。外部顧客向けのファウンドリ事業を軸に据える姿勢は、かつてのCPU主導モデルからの転換を意味し、同社の事業構造を根底から見直すものとなる。
ファウンドリ市場参入は、インテルにとって莫大な設備投資という負担と隣り合わせである。2024年の設備投資額は239億ドルに達し、軽資産型の競合と比べてキャッシュフローに不利な構造を抱える。ただし、米国CHIPS法による78.6億ドル、ドイツからの約110億ドルといった補助金は、財務的なリスク軽減に寄与する。Intel 18Aの商業化とパートナーシップ拡大が進めば、単なる一製品技術を超え、同社の成長軌道を描き直す可能性が生まれる。
市場の反応と株価評価に見られる慎重な期待感
インテルの株価は2024年初来で13%の上昇を見せ、NvidiaやAMDを上回るパフォーマンスを記録している。ただし、アナリストの見解は依然として慎重であり、37人中31人が「ホールド」と評価している点からも、回復への確信には至っていないことがうかがえる。目標株価の平均も現行水準とほぼ一致しており、今後の動向を見極めようとする市場の姿勢が反映されている。
直近の決算では、売上高143億ドル(前年同期比7%減)、EPS0.13ドル(同76%減)と前年からの減少が続いているにもかかわらず、市場予想を上回ったことで一部に安心感も生まれた。とはいえ、2025年Q1のガイダンスでは売上がさらに減少する見込みであり、業績回復には時間を要する可能性がある。製品簡素化や次世代CPUの投入など明るい材料もあるが、株式市場は今のところ、それを確かな成長シナリオとは見ていない。
Source:Barchart