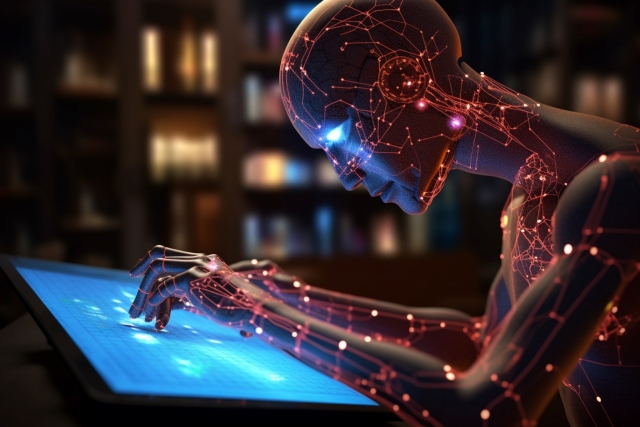Samsung Foundryの低迷が鮮明となった。3nmプロセスでの受注獲得失敗に続き、2nmプロセスでも同様の課題に直面しており、歩留まりの低さが致命的な弱点と化している。特に、TSMCの60〜70%という高い歩留まりに対し、Samsungは約30%にとどまっている状況だ。
この技術的な差が顧客流出を招き、GoogleはPixel 10向けのTensor G5をTSMCへ、Qualcommも次世代Snapdragonを引き続きTSMC製に委ねるなど、主要企業がSamsung離れを進めている。市場シェアも2024年第4四半期には8.1%まで低下し、TSMCの67.1%と大差がついた。
唯一の起死回生策とされるのが、自社のExynos 2600による2nm市場への先行投入である。ただし、競合AppleもTSMC製A19シリーズで追随する構えであり、Samsungの巻き返しには精度と安定性の飛躍的な改善が不可欠となる。
歩留まり30%の壁 Samsung Foundryの競争力低下が顕在化

Samsung Foundryが直面する最大の課題は、歩留まりの低さにある。2nmおよび3nmプロセスでの歩留まりが約30%にとどまり、TSMCの60〜70%という実績と比較すると明確な技術的劣位が浮き彫りになっている。シリコンウェハーから切り出されるチップのうち、品質基準を満たす割合が低ければ、製造コストが増加し、顧客にとってのリスクも高まる。
特にファブレス企業にとって、製品の安定供給が脅かされるという懸念が大きく、調達先を安定性の高いTSMCへと切り替える判断が続いている。実際に、GoogleがPixel 10に搭載するTensor G5チップをTSMC製に変更したことは象徴的である。加えて、QualcommもSamsungへの回帰を見送り、Snapdragon 8 Elite 2においてTSMC製造を継続する方針を取った。
こうした動きが連鎖的に広がれば、Samsung Foundryの競争力回復は一層困難になる。歩留まりの改善なしに、2nm世代の戦いを優位に進めることは極めて厳しい。製造技術と品質管理体制の抜本的な再構築が急務である。
市場シェア8.1%への急落 顧客流出が及ぼす収益構造への影響
2024年第4四半期、Samsung Foundryの市場シェアは8.1%にまで落ち込んだ。前期の9.1%から1.0ポイントの減少であり、競合TSMCが同時期に67.1%を維持したことと比較すれば、その差は歴然である。この背景には、顧客からの信頼喪失がある。ファウンドリ業界では、不良チップのコストを設計企業が負担するケースが多く、歩留まりの悪化は顧客側の経済的負担を直撃する。
これにより、大口顧客が確実性とコスト効率を重視してTSMCへ移行する構図が定着しつつある。Samsungにとって、収益構造の維持には受注規模の確保が不可欠であるが、低歩留まりがこのサイクルを崩している。
さらに、自社製スマートフォン向けのExynosシリーズの開発・製造に注力せざるを得ない状況は、外部顧客を獲得できない構造的な限界を露呈している。Exynos 2600が2nm世代で先行投入されたとしても、それが収益改善に直結するかは不透明である。競争力回復には、市場信頼の再構築と広範な製品群への対応力が不可欠となる。
Exynos 2600による巻き返しは可能か 先行投入の意義と限界
Samsung Foundryの次なる戦略的鍵を握るのが、2nmプロセスで製造予定のExynos 2600である。この製品は、AppleがTSMCのN3Pプロセスで開発中とされるA19シリーズに先駆け、市場投入が可能な唯一のSamsung製2nmチップとされている。これが実現すれば、プロセスノードの競争で再び業界をリードできる可能性も残されている。
ただし、Exynos 2600は外部顧客向けではなく、Samsungのモバイルデバイスに限定される用途であることが想定され、製造ラインの商業的広がりには限界がある。また、トランジスタ密度や消費電力といった技術的利点が理論上どれほど高くとも、実際の歩留まり改善が伴わなければ、量産体制の信頼性は得られない。
Appleは過去にも5nm、3nm世代でTSMCと協業し先行実績を築いてきた。Exynos 2600が市場投入されたとしても、それが歩留まりと安定性を裏付けるものと認識されるには時間を要する。競争環境が激化する中で、技術的先行だけでは決定打にはなり得ず、供給体制の確立と顧客獲得戦略の両立が不可欠となる。
Source:PhoneArena