米RetymがSpark Capital主導のシリーズDで7,500万ドルを新たに調達し、累計資金は1億8,000万ドルに到達した。注目すべきは、同社がAI演算そのものではなく、データセンターの高速通信を担うDSPチップを開発している点である。
Marvell Technologyが支配する市場に挑む形で、RetymはTSMCの5ナノ製造プロセスを採用し独自チップの試験を進行中だ。創業者ロニ・エル=バハールは、既存巨頭に風穴を開けるという使命を明言している。AIの計算需要が急増する中、演算の裏側を支える通信技術への注目は今後さらに高まる可能性がある。
Retymが挑む次世代DSP市場の構造と資金調達の意義
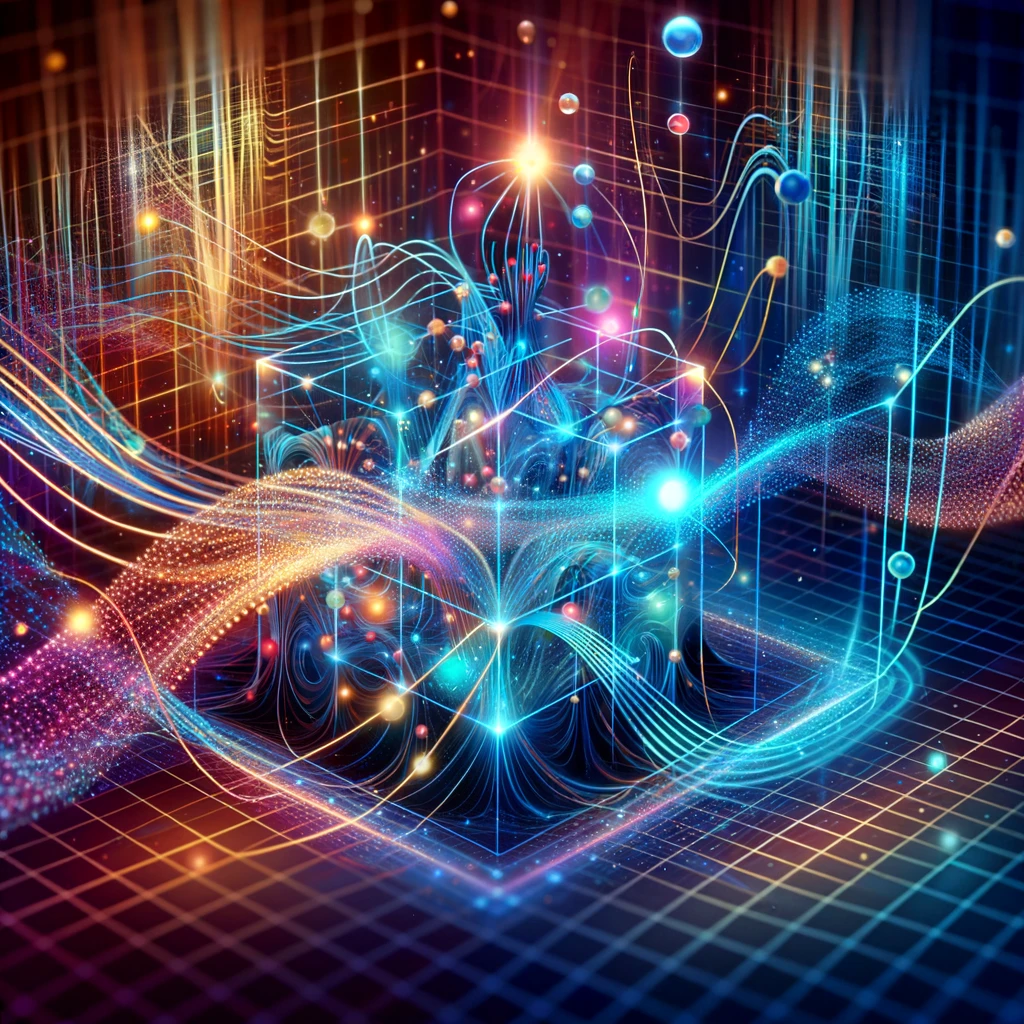
Retymは2021年に設立されたばかりの新興企業ながら、2025年3月のシリーズDで7,500万ドルを確保し、累計調達額は1億8,000万ドルに達した。資金の出所はSpark Capitalのジェームズ・ククリンスキーを筆頭に、Mayfieldのナビン・チャッダ、Kleiner Perkinsのマムーン・ハミドといったベンチャー投資の大物たちである。この構図は、同社が単なるハードウェア企業ではなく、成長可能性の高い戦略的インフラプレイヤーとして認識されていることを示す。
Retymの製品はAI演算そのものではなく、データセンター内部や外部との通信を効率化するためのプログラム可能なコヒーレントDSPチップである。これはNvidiaのようなGPUベンダーとは異なる軸での技術貢献であり、むしろGPU間通信やAIの学習環境全体の処理効率に大きく関与する分野だ。従来この領域はMarvell Technologyが支配していたが、TSMCの5nm技術を用いた新アーキテクチャにより、Retymは市場への切り込みを図る。
通信負荷の増大に直面するクラウド事業者やハイパースケール企業にとって、単なる演算能力だけでなく、膨大なデータの高速処理能力が今後の競争力を左右する。こうした状況下で、Retymが提供する新しいDSP技術は、既存の常識を揺るがす可能性を内包している。
技術的独自性と既存大手への挑戦が示す業界構造の変化
Retymの共同創業者兼CTOであるロニ・エル=バハールは、自らのブログで「大手半導体企業によって支配されてきたDSP市場に競争をもたらすために創業した」と述べている。ここで言及されているのは、現在の業界を牛耳るMarvell Technologyであり、同社はNvidiaやJuniper Networksなどとの連携で強固な市場地位を築いてきた。その中でRetymは、可変性と柔軟性に優れる独自のDSPチップで、制御と演算の通信層に新たな選択肢を提供しようとしている。
注目すべきは、Retymのチップが汎用的な演算処理ではなく、極めて限定的かつ専門的な信号処理に特化している点である。これは高性能AIが求める「周辺環境の最適化」というニーズと合致し、今後のAIインフラを支える不可欠な基盤技術と見なされる可能性がある。これまで可視化されづらかった「通信の壁」こそがAIの性能を制限するボトルネックとなっており、同社のアプローチはその核心に踏み込んでいる。
一方で、現時点ではチップはまだテスト段階であり、実用化には技術的ハードルが残る。とはいえ、TSMCの5nm製造技術を活用している事実は、製品の完成度や量産性において既に一定の期待を集めている。主戦場が演算装置から通信装置へと拡大しつつある現代において、Retymの存在は今後の半導体業界再編の起点となり得る。
Source:TechCrunch

