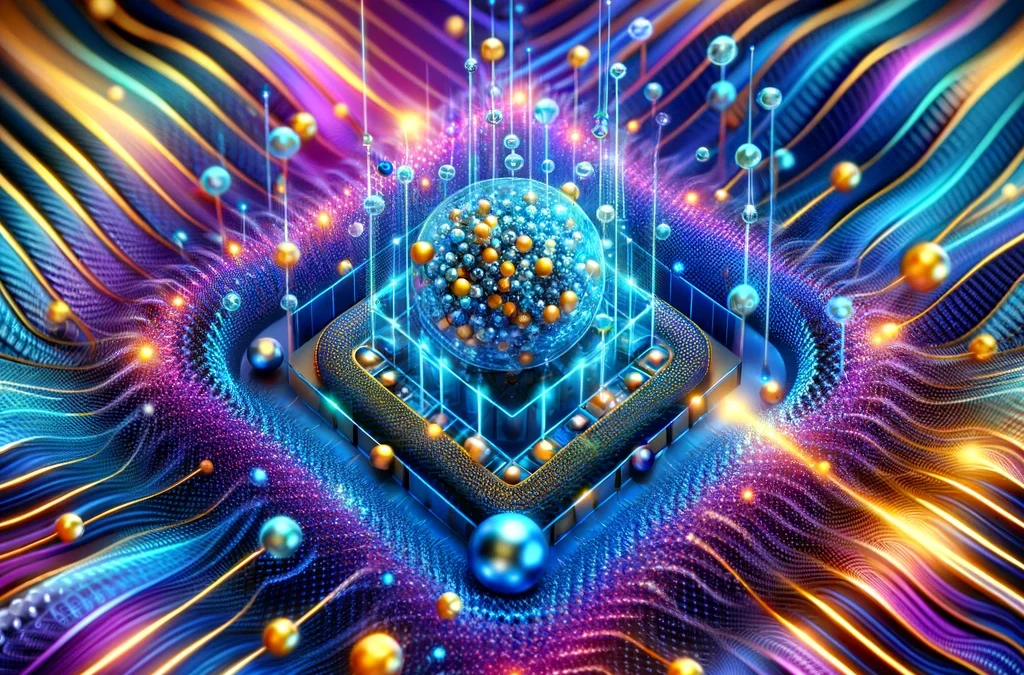量子コンピューティングの進化が加速する中、業界の主役とは目されてこなかったHoneywellが急浮上している。同社は、量子部門Quantinuumの今後2年以内の上場を計画しており、これが量子関連で最大規模のIPOとなる可能性を秘める。Quantinuumは既に、従来の計算機では不可能な乱数生成に成功するなど、現実世界での応用を示している。
2026年までに素材、オートメーション、航空宇宙の3部門へ分社する計画も進行中で、量子分野の成長がHoneywellの企業価値を左右する要因となりつつある。2025年にはEPS最大10.5ドルと堅調な成長が見込まれ、アナリストの評価も「やや買い」に集約されている。
クァンティニュームが切り拓く量子実用化の現在地

Quantinuumは、2021年にHoneywell Quantum Solutionsと英国のCambridge Quantumの合併により誕生した量子コンピューティング企業である。最近では同社が開発した「Model H2」システムにより、従来のコンピューターでは不可能とされてきた真性乱数の生成に成功した。これは単なる技術デモンストレーションではなく、量子コンピューティングが実用領域に足を踏み入れつつあることを裏付ける事例である。
さらに、Honeywellはこの量子部門を2年以内に上場させる意向を示しており、これが業界における大型IPOとなる可能性がある。近年では「QCaaS(Quantum Computing as a Service)」市場が急拡大しており、その文脈においてQuantinuumは民間利用に適した応用性と実績を備える稀有な存在である。業界の有力プレーヤーが技術力と商業性を両立させる中、Quantinuumはその両軸で成果を積み重ねつつある点に注視すべきである。
Honeywellの分社化と量子投資が示す成長構造の再定義
Honeywellは2024年2月に、先端素材、オートメーション、航空宇宙の3分野を柱とする事業再編計画を発表し、2026年後半の分社完了を目指している。従来の複合型産業モデルから脱却し、それぞれの分野で競争力を持つ独立事業体へと再編成する動きであり、市場ではこの戦略転換に対する評価が分かれている。一方で、この再編の背後には、Quantinuumを軸とした量子分野への資本集中という長期的視野も見て取れる。
配当利回り2.1%、配当性向44.32%という安定した株主還元を維持しつつ、Honeywellは成長分野への投資に舵を切っている。特に、予想PERが20.5倍と過去5年平均を下回っている点は、量子事業の拡大余地を織り込んでいない現状を示唆する。企業構造を再設計しつつ、技術革新の最前線で価値創出を狙うHoneywellの動向は、旧来の重厚長大型企業の成長像に一石を投じる可能性がある。
Source:Barchart