Microsoftは、Windows 11 Enterprise 24H2を対象に、x64(AMD/Intel)システム上でのホットパッチ機能を提供開始した。これにより、再起動を伴わずにセキュリティ更新を適用できるようになり、業務中の中断やダウンタイムを最小限に抑えることが可能となる。
更新はMicrosoft Intuneコンソール内のWindows Autopatchを通じて管理され、ホットパッチに対応するデバイスには、四半期ごとに更新が配信される。1年のうち8か月間は再起動不要で脆弱性への対応が可能となる点も注目される。
四半期ごとの更新で再起動なし Windows 11 Enterprise 24H2が実現する新たな運用モデル
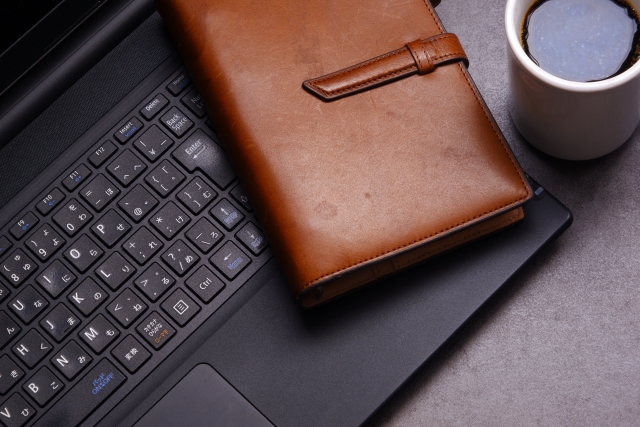
Microsoftが導入したホットパッチ機能により、Windows 11 Enterprise 24H2では四半期ごとに提供されるセキュリティ更新を、OSの再起動なしで適用できるようになった。これは、実行中のプロセスのメモリ空間に直接パッチを適用する仕組みによるもので、通常の再起動を伴う従来の更新方式とは一線を画す。Microsoft Intuneを通じた管理体制により、自動でホットパッチ対応デバイスを検出し、対象にのみ適切な更新を適用することも可能だ。
対象となるのは、Windows 11 Enterprise E3/E5、Education A3/A5、またはWindows 365 Enterpriseのサブスクリプションを持つx64システムで、仮想化ベースのセキュリティ(VBS)が有効であることが前提条件となっている。現在、Arm64デバイス向けの対応はパブリックプレビュー段階にとどまり、CHPE関連の設定変更が必要な状況だ。
この新機能により、定期的な再起動による作業中断を避けられる環境が整い、日常的な操作性や利便性に直結する改善が期待できる。ただし、システム要件を満たすか否かによって導入のハードルは異なり、最新機能を享受するには環境の整備が不可欠となる。
従来の更新方式に変化をもたらす可能性とその注意点
再起動不要での更新は、表面的には利便性の大幅な向上と受け取られがちだが、実際には運用面での考慮事項も存在する。たとえば、四半期単位でのホットパッチ提供というサイクルは、毎月のセキュリティ更新が常態だった従来方式に比べ、更新頻度が減る印象を与える可能性がある。ただし、Microsoftは1年のうち8か月をホットパッチ運用とし、残りの期間にベースラインの更新が必要になるという運用ポリシーを明示しており、この点は理解を要する。
また、再起動が不要なことによる心理的な安心感とは裏腹に、パッチ適用の内容によってはデバイスの一部動作に影響が出るケースも考えられ、すべてが無停止で完結するわけではない点も重要である。さらに、ホットパッチ方式が採用されたとはいえ、Windows 10や旧バージョンのWindows 11では引き続き従来型の月例更新が適用されるため、混在環境における管理の複雑化は避けられない。
利便性の高さと裏腹に、更新方式の多様化による把握・管理の難度が増すことも視野に入れておく必要がある。ホットパッチが提供する「再起動しない更新」は確かに革新的だが、運用を安定させるには導入前の十分な検証と、環境に応じた対応が不可欠となる。
Source:BleepingComputer

