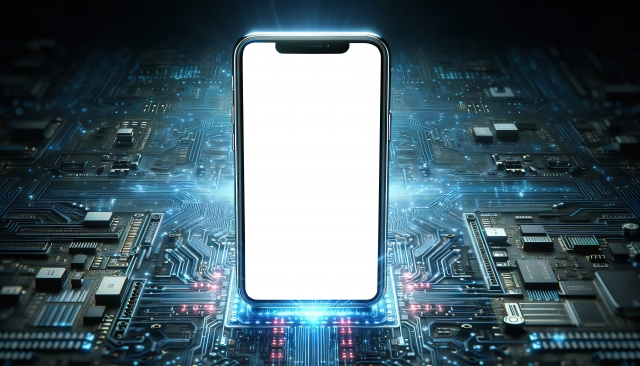GoogleはGeminiアプリにおける「Astra Liveカメラ」および「画面共有」機能の展開を欧米のPixelスマートフォンを中心に拡大している。対象となるAndroidユーザーには、「カメラまたは画面をGemini Liveで共有しますか?」とのプロンプトが表示される仕組みで、Gemini Advanced登録者が優先される。
Liveカメラ機能では、映像を通じてアイデアの表現や周囲の認識支援が可能となり、UI上の新たなビューファインダー操作も導入された。画面共有機能も全画面またはオーバーレイから簡便に起動できるようになり、利用中はステータスバーにLive表示が現れる。
段階的な展開は依然として続いており、同一アカウントでも端末によって利用可否が分かれる事例が報告されている。導入確認にはアプリの強制停止後の再起動が推奨されており、今後の対応機種拡大が注視される。
Gemini Liveの段階的展開とAstraカメラ機能の仕様

Googleは3月に発表したGemini Liveの「Astraカメラ」機能を、米国および欧州を中心に一部のPixelスマートフォンへ段階的に展開している。初期導入は一部のGoogleアカウントに限定されており、同一アカウントでもデバイスによって利用可能か否かが異なる現象が確認されている。
サポート文書によれば、Android端末でGemini Advancedへ登録していることが利用条件であり、アプリ内でプロンプトが表示されることで使用開始が可能となる。
Astraカメラは、ビューファインダーを通じた映像認識機能に対応しており、利用者の語りかけに応じて周囲の情報や視覚的対象への理解を支援する。UI上では、カメラ起動ボタンが画面下部に追加されており、前面カメラへの切り替えも即座に可能となっている。ユーザーが撮影対象を安定して映すことが求められ、AIによる認識の正確性を確保する設計が見られる。
この展開は、スマートフォンカメラの利用価値をコミュニケーション手段へと拡張する試みと位置づけられる。ビデオ通話やSNS用途とは異なる次元で、リアルタイム視覚情報の分析とフィードバックを通じた支援の実用化が進められており、今後の多用途化への布石とも受け取れる。
画面共有機能とプライバシー設計の相克
Gemini Liveには、Astraカメラ機能に加えて、スマートフォンの「画面共有」機能が搭載されている。全画面インターフェースやGeminiオーバーレイから起動でき、「Googleと画面を共有しますか?」という確認プロンプトを経て開始される。この操作により、ステータスバー横にLive中を示すピル型インジケーターが出現し、現在進行中の共有状態が明確化される仕様となっている。
画面共有は、ユーザーの操作状況やアプリの表示内容に応じた支援を可能にする一方で、機密情報や個人データへのアクセスを含む可能性も孕む。Gemini Liveが個々のインターフェースに深く関与する設計である以上、プライバシーへの配慮は欠かせず、Googleが設ける確認プロンプトは最低限の防波堤に過ぎない。利用者側に求められる注意と判断は依然として大きい。
このような機能設計は、AIによるアシストの進化と並行して、「利便性とリスクのバランス」という古くて新しい課題を浮き彫りにしている。特に業務用スマートフォンや多機能化が進む端末環境において、どのレベルの共有を容認すべきかという判断基準が今後重要性を増すと見られる。
Source:9to5Google