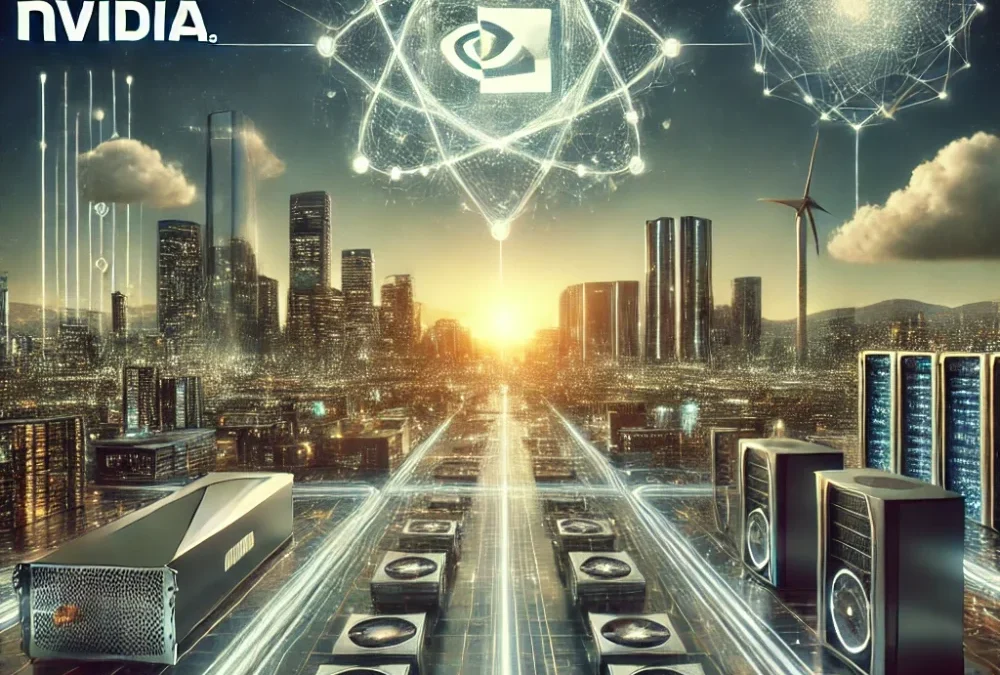Nvidiaの株価が揺れる中、5月15日が注目を集めている。バンク・オブ・アメリカは、米国政府が導入を予定するAIチップの新たな輸出規制「AI拡散ルール」が市場に波紋を広げる可能性があるとし、規制の影響を受ける中国市場へのエクスポージャーに言及した。
売上の約10%を占めるH20 GPUが規制対象となれば、業績への懸念が現実味を帯びる。ただし、NvidiaはGMとの提携やBlackwell Ultraへの旺盛な需要といったポジティブ要因も抱えており、株価には上下双方の圧力がかかっている。
年初来で23.1%下落しているものの、ウォール街は依然として強気の評価を維持。売上高予想やバリュエーション指標から見ても、短期の不安定さを乗り越えた先に再上昇の可能性を残している。
AI拡散ルールが突きつけるNvidiaの対中リスクと株価への影響

米バイデン政権が5月15日に導入を予定する「AI拡散ルール」は、Nvidiaの事業展開に重大な影響を及ぼす可能性がある。これは、18のTier1国以外へのAIチップ供給を制限するという内容であり、中国市場への依存度が一定程度存在するNvidiaにとって、直接的なリスクとなり得る。Nvidiaの売上の約10%は、中国向けH20 GPUの供給に依存しており、この規制によってその収益源が断たれるリスクが現実味を帯びる。
BofAのヴィヴェック・アリヤ氏は、過去に中国懸念で一時的に売り込まれた半導体関連銘柄が、投資家の理解が進むことで回復を遂げた例を引き合いに出し、今回も同様のパターンが起こる可能性を指摘する。ただし、今回の規制は技術安全保障の文脈に根差した恒常的な措置であるため、単なる一時的な調整と見るには時期尚早とも言える。
今後数週間にかけて、地政学的なノイズと企業の実績が交錯し、NVDA株は高いボラティリティを伴う展開が続く可能性がある。投資家にとって重要なのは、短期的な価格変動に翻弄されるのではなく、構造的な成長力と外的リスクのバランスを冷静に見極める視座である。
業績好調でも株価は下落 市場が織り込む先行き不透明感とは何か
Nvidiaは第4四半期において、売上393億ドル、前年比78%増という極めて力強い業績を示し、ウォール街の予想も上回る結果を残している。特にデータセンター部門の売上は356億ドルと総売上の9割以上を占め、Blackwellチップの立ち上がりが前例のない速度で進行している。一方で株価は年初来で23.1%の下落を記録しており、業績と市場評価の間に乖離が生じている。
この矛盾は、短期的な外部要因が市場心理を強く左右していることを物語っている。関税、中国の新興AI企業DeepSeekの台頭、そしてAIチップ規制といった不確実性が、Nvidiaの将来に対する期待感を一時的に曇らせている。加えて、ゲーミング部門の不調や供給の逼迫といった実務的課題も、市場のリスク評価を引き上げる材料となっている。
とはいえ、現在のフォワードP/Eは過去平均を大きく下回り、PEG比率も1倍未満と、成長余地に対して株価が割安であるとの見方も存在する。過熱感を冷ました現在の水準は、長期的視点を持つ投資家にとってはむしろエントリーポイントと捉えられる余地がある。市場の短期的な悲観は、構造的な成長力を過小評価している可能性がある。
Nvidiaに対する市場評価と5月15日以降の焦点
BofAはNvidia株に対して「買い」評価を維持し、目標株価を200ドルと提示している。これは、現行水準から大きな上昇余地を示唆するものであり、同社の持つ技術的独自性と成長力が評価されていることを意味する。アナリスト44名中、38名が「強く買い」、4名が「ホールド」という構成も、同様の強気姿勢を裏付けている。
ただし、この評価が現実化するか否かは、5月15日を起点とする政策決定の内容と市場の反応にかかっている。仮にAI拡散ルールの内容が市場の想定内に収まり、事業構造への深刻な影響が避けられるなら、株価は地政学的リスクの緩和を背景に再浮上する可能性がある。一方で、想定を上回る規制強化や中国側の報復措置があれば、逆風が強まる可能性も否定できない。
その意味で、5月15日は単なる規制発表日ではなく、今後数四半期における成長戦略の現実性を市場が判断する分水嶺となる。評価を見極める上では、政策の行方と同時に、Nvidiaが構造転換にどう応えるかが問われる局面である。
Source: Barchart