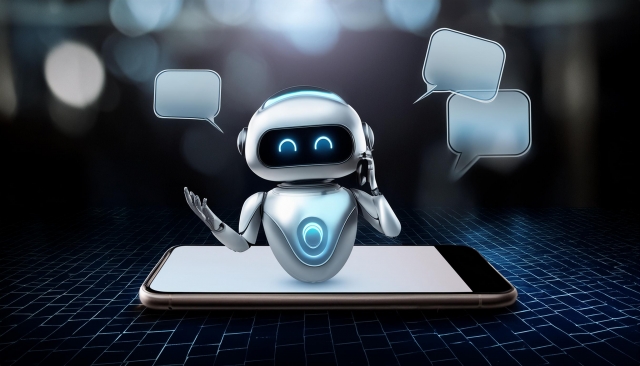OpenAIは、2019年のGPT-2以来となるオープンソースの言語モデルを数か月以内に公開する計画を明らかにした。GPT-3以降は一貫してクローズド戦略を採ってきたが、MetaのLlamaや中国DeepSeekの台頭を受け、潮流の変化に応じた動きとみられる。
Microsoftとの130億ドル超の提携を背景に独占的なモデル展開を進めてきたOpenAIにとって、今回の決定は戦略の再考を意味する。Azureとの契約終了もタイミングと無関係ではない可能性がある。
一方、中国ではアリババ、バイドゥ、テンセントが3月に最新AIモデルを相次ぎ発表。オープンソース化を含む各社の姿勢は、グローバルな開発競争と産業構造の再編を加速させる契機となり得る。
OpenAIの戦略転換が示す開発環境の変化

OpenAIは、数年にわたりクローズドな開発体制を堅持してきたが、2019年のGPT-2を最後に封印していたオープンソース方針を再び選択した。この変化は、MetaのLlamaや中国DeepSeekなどのオープンソースモデルが急速に評価を高めている状況を背景にしている。
とりわけMetaは、2023年に公開したLlamaのダウンロード数が10億件を突破したと公表し、商用・研究用双方で広く浸透した。SpotifyがLlamaを用いたレコメンド機能を導入した事例からも、市場での実用性が証明されている。
また、DeepSeekの低価格かつ高性能なモデルは、米中の主要クラウド企業に迅速に採用され、AWS、Google Cloud、Azureといったプラットフォームへの統合も進んでいる。
OpenAIのサム・アルトマンCEOは、Redditフォーラムで「異なるオープンソース戦略の検討」を示唆しており、実質的な方向転換の予兆といえる。こうした流れから、オープンソースはコスト面だけでなく、柔軟な開発環境を重視する潮流を象徴しており、かつての競争優位が見直されつつある。
中国勢の台頭とグローバルAI地図の再構築
2025年3月、中国のアリババ、バイドゥ、テンセントは相次いで新たなAIモデルを公表し、技術競争の主導権争いが一段と激化した。アリババの「Qwenb 2.5-Omni-7B」は、テキスト・画像・音声・動画といった複数のメディアを扱えるマルチモーダルモデルであり、GitHubおよびHugging Face上でオープンソースとして公開された点が注目に値する。
バイドゥは「Ernie 4.5」と「Ernie X1」の二本立てで、前者については2024年6月にオープン化予定と明言。テンセントも「Hunyuan T1」を市場に投入し、DeepSeekと同水準のコストパフォーマンスを打ち出している。
このような動きは単なる技術発表に留まらず、オープンソースを戦略的武器とする国家間競争の一環と捉えられる。特に中国勢は、従来の閉鎖的開発モデルから一転し、グローバルな開発者層への訴求を強化している。これにより、西側テック企業の独占状態は揺らぎ始めており、各国におけるAIモデルの標準化や技術主権をめぐる議論が再燃する可能性がある。世界のAI地図は、いま再構築の渦中にある。
Source:PYMNTS.com