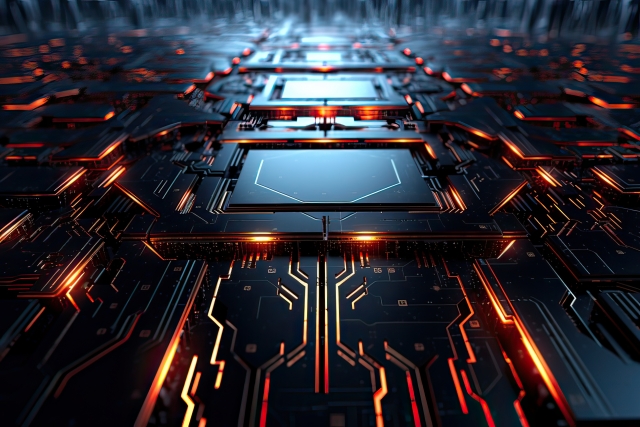著名なオーバークロッカーであるYouTuber・der8auerが、AMDのRyzen 9 9950X3Dプロセッサに対して殻割り(IHS除去)を実施し、冷却性能の劇的な改善を実証した。Thermal Grizzly製のダイ直冷式水冷ブロックと液体金属を組み合わせた結果、標準構成と比較して23℃もの温度低下を達成した点は注目に値する。
さらに、PBO(Precision Boost Overdrive)を最大限に活用することで、Cinebench R23では最大9%の性能向上、ゲームにおいても1%低下フレームレートで9%の改善が確認された。ただし、電力消費は最大で73%増加しており、実運用にはアンダーボルテージや定格設定との併用が推奨される。なお、殻割りはCPUに深刻な損傷を与えるリスクを伴うため、慎重な対応が求められる。
Ryzen 9 9950X3Dの殻割りがもたらす熱設計の革新

YouTuberでありオーバークロック界で名を馳せるder8auerは、Ryzen 9 9950X3DのIHS(統合型ヒートスプレッダー)を除去し、ダイに直接冷却を施すという試みで注目を集めた。Thermal Grizzlyの水冷ブロックと液体金属の組み合わせにより、フル負荷時の温度を従来構成より23℃も低下させることに成功した。この温度差は、冷却設計の見直しを迫るほどのインパクトを持つ。
AM5ソケット世代のIHSは、前世代よりも明確に厚みを増しており、熱伝導経路の長さが冷却効率に影響を与えていた。IHSを外すことで熱源と冷却機構の間に介在する素材が減り、熱移動が格段に効率化された格好だ。液体金属の使用も重要な要素であるが、主因は物理的構造の簡素化にあると見られる。
こうしたアプローチは従来、極端なオーバークロックを狙う一部の熱心な層に限られていたが、9950X3Dのような高密度キャッシュ搭載CPUにおいては、熱制御が性能の足かせとなるケースも多く、合理性が増している。リスクはあるが、発熱に悩む高性能ユーザーにとって一考の価値はあるだろう。
PBO活用による性能拡張と電力消費のトレードオフ
殻割りによって冷却性能に余裕を得たder8auerは、Precision Boost Overdrive(PBO)の設定を最大に引き上げ、CPUの潜在性能をさらに引き出した。Cinebench R23においては9%のスコア向上、またゲーム環境でも1%低下フレームレートが9%向上するなど、実用面でも一定の成果が見られた。PBOの最適化は、冷却能力の増強と組み合わせることで、効果的に機能することが改めて示された。
ただし、この性能向上は無償ではない。CinebenchおよびCounter-Strikeでの検証では、電力消費が最大73%増加しており、発熱と消費電力のバランスが極めて重要となる。冷却に余裕があるからこそ許される設定であり、システム全体の設計が問われることになる。
実際、200Wの電力制限を維持した状態でも、殻割り後の温度は最大51℃に抑えられたという報告があり、パフォーマンスと消費電力の適切な折り合いをつける設計が可能であることも示唆される。電力効率と安定性を重視する観点からは、あえてPBOを控えめに設定する戦略も選択肢となる。
殻割りの可能性と避けられない構造的リスク
殻割りによる冷却性能の飛躍的改善は明白である一方、その作業が持つリスクも無視できない。IHSの除去には高度な技術と専用工具が必要であり、わずかな手順の誤りがCPUの破損につながる恐れがある。der8auer自身も、適切な知識と経験が不可欠であると明言しており、安易な模倣は避けるべきだ。
特にAM5世代のCPUはIHSが強固に固定されており、過度な力を加えるとダイ自体に物理的な損傷を与える危険が高い。これにより、保証対象外となるリスクも顕在化するため、作業にあたっては自己責任が前提となる。冷却性能や性能向上の利得と、取り返しのつかない損害の天秤は常に意識されるべきである。
とはいえ、制御された条件下で殻割りが行われれば、熱対策が難しい高性能CPUに新たな選択肢を提供する可能性はある。とりわけ、アンダーボルテージや定格運用との組み合わせにより、安全性を確保しつつ効率を高める手法が今後注目されると考えられる。殻割りは単なる改造ではなく、熱設計の再構築に他ならない。
Source: Club386