中国の著名リーカーDigital Chat Stationによると、Qualcommの次世代チップ「Snapdragon 8 Elite 2」は、GPUキャッシュを16MBに拡張することで、従来モデル比で約30%の性能向上が見込まれているという。
同チップは、AnTuTuベンチマークにおいて約380万ポイントを記録するとされ、これまでの最高スコアを大幅に上回る可能性がある。また、Oryon第2世代コアによるCPU性能も最大25%の改善が示唆されている。
製造にはTSMCの3nm N3Pプロセスが採用される見通しで、LPDDR6などの最新メモリ規格やARM v9アーキテクチャへの対応も報じられている。正式発表は2025年10月頃になると予測されるが、今回のリークは技術動向に敏感な業界関係者の関心を大いに集めている。
GPUキャッシュ拡張とAnTuTuスコアから見る性能向上の実態
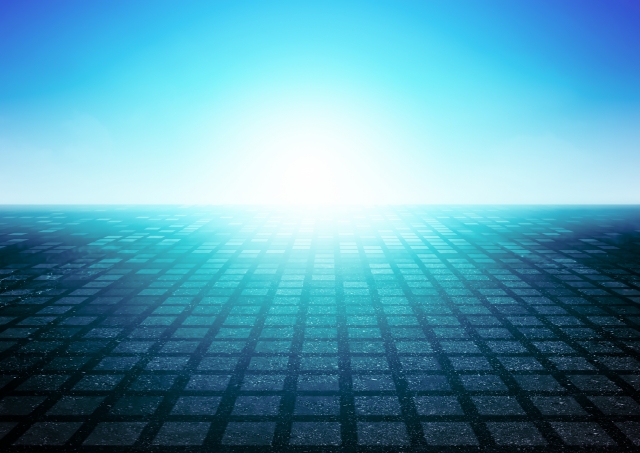
Snapdragon 8 Elite 2は、GPUキャッシュを従来の12MBから16MBへと拡大することで、グラフィックス性能の大幅な向上が示唆されている。
Digital Chat Stationによれば、初期のベンチマークテストでは最大で約30%の性能向上が観測されており、GPU処理における高速化が数値としても裏付けられている。AnTuTuスコアにおいては約380万ポイントを記録するとされ、これは現行のSnapdragon 8 Eliteと比較しても約30%の飛躍となる。
この性能向上は、GPUキャッシュの増加によるメモリ帯域の最適化が主因と考えられるが、同時にチップ全体の設計刷新が進んでいることも推察される。TSMCの3nm N3Pプロセスが採用されると伝えられており、より高密度かつ低消費電力の製造技術が性能向上の一端を担っている可能性が高い。性能だけでなく、効率性の観点からも次世代チップとしての成熟度が垣間見える。
性能評価はベンチマークスコアにとどまらず、実際のアプリケーション負荷下でのレスポンスにも影響を与える。30%という数字が示すのは単なる数値の向上ではなく、より重厚なグラフィック処理やAI演算を必要とする用途において新たな基準を打ち立てる可能性である。
Oryon第2世代と2+6コア構成が示すアーキテクチャの進化
Snapdragon 8 Elite 2では、Qualcommの独自設計による「Oryon」コアの第2世代が搭載されるとされており、CPU全体としては約25%の性能向上が報告されている。構成はプライムコア2基とパフォーマンスコア6基からなる2+6構成で、従来の設計と比してバランスと効率性を両立した設計が採用されていることがうかがえる。
この構成は、処理負荷の高いタスクを担うプライムコアと、持続的なパフォーマンスを担保するパフォーマンスコアによって、可変的な電力制御と発熱管理に貢献する設計と考えられる。モバイル向けSoCにおいては、消費電力と処理性能のトレードオフが常に課題となるが、この2+6構成は両者の最適解を模索した結果とも言える。
また、Oryonアーキテクチャの改良により、単純なクロック数の引き上げではなく、命令スループットやパイプライン効率の最適化が追求された可能性も否定できない。高性能アプリケーションの同時実行やAIタスク処理への適応において、この改良が与える影響は計り知れない。
メモリ規格と命令セット対応が示すARM v9への戦略的移行
Snapdragon 8 Elite 2は、LPDDR5Xおよび次世代規格のLPDDR6メモリに対応する設計とされており、SME1およびSVE2命令セットの採用を通じて最新のARM v9アーキテクチャに準拠する方向が明らかとなった。これにより、同チップは将来的なモバイル向け演算処理の高度化に備えた準備がなされていると見るべきである。
LPDDR6は、帯域幅の拡大と低電力化の両立を図る次世代メモリ規格であり、AI処理やグラフィックス用途において極めて重要な役割を果たす。また、ARM v9に含まれるSVE2命令セットは、ベクトル演算や機械学習処理の効率化に寄与する構造であり、今後のスマートフォンやモバイルPCの演算能力を根本から変える基盤となる。
Qualcommがこのような命令セット対応を早期に実装する姿勢は、単なる性能向上だけでなく、開発者向けの柔軟性と拡張性を強く意識した戦略と解釈できる。これは、エンドユーザーの体感性能の向上のみならず、開発環境やエコシステム全体への波及効果を狙った布石ともいえる。
Source:Gizmochina

