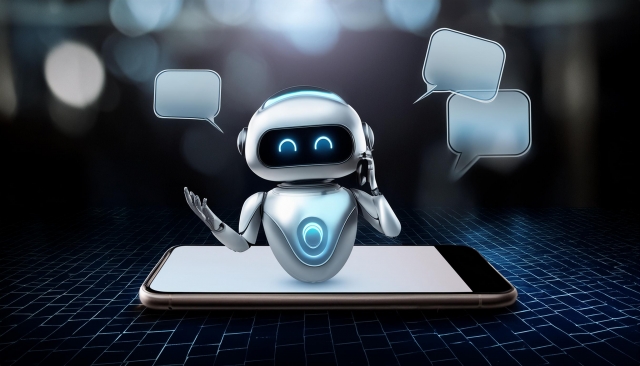マイクロソフトは2025年4月4日、創業50周年イベントにてAIアシスタント「Copilot」の進化版「Copilot Vision」をモバイルアプリに実装したと発表した。Edgeブラウザ限定だった同機能は、音声モードを通じてスマートフォン上のリアルタイム映像や画像を解析するマルチモーダルAIへと拡張された。対象は米国内のCopilot Pro加入者に限定され、無料ユーザーは利用不可となっている。
一方、Googleはすでに「Gemini Live」を用い、PixelやGalaxy S25といった特定端末への映像解析機能を無償で展開している。Copilot Visionと同様、カメラや画面共有によるAI対話を可能にしており、技術仕様も極めて近い。
こうした動きは、両社がスマートフォン市場におけるAI主導権の確保に向け、製品投入のスピードと独自性を競っている構図を浮き彫りにしている。
Copilot Visionのモバイル展開が示すマイクロソフトの戦略的意図

マイクロソフトは2025年4月、創業50周年の節目に合わせて「Copilot Vision」をモバイルアプリへと正式展開した。
2024年10月にEdgeブラウザ限定で公開された同機能は、Webページの内容を即時に理解し、関連する質問に回答するという構成で登場したが、今回のモバイル対応ではカメラや画像データの解析を含むマルチモーダル対応が新たに加わった。対象は米国内のCopilot Pro加入者に限定され、音声モードを経由して提供されている。
この技術的進化により、ユーザーはスマートフォンに保存された静止画や動画を通じて、文脈に即したAIからのフィードバックを受けることが可能となる。
たとえば、部屋の写真を提示しながら内装のアドバイスを求めたり、会議中に記録された映像から要点の抽出を試みたりといった実用的な応用が視野に入る。マイクロソフトはCopilotを単なるAIチャットではなく、現実世界と接続された次世代アシスタントへと進化させようとしている。
この動きは、生成AI競争における時間軸の主導権を奪う試みと見るべきだろう。2023年2月のAIチャットボット公開以降、マイクロソフトは立て続けに新機能を投入してきた。機能発表の頻度を高めることで、プロダクトの鮮度と存在感を保ち、Googleをはじめとする他社との差異化を図る姿勢が明確に表れている。
Gemini Liveとの類似性と異なるビジネスモデルの構図
Googleが展開する「Gemini Live」は、今回のCopilot Visionのモバイル機能と極めて類似する構成を持つ。GeminiはPixel 9やGalaxy S25シリーズといった特定端末において、ユーザーのスマートフォン画面やカメラ映像をリアルタイムでAIに接続し、対話形式でのサポートを実現している。Googleはこの機能を一部デバイス向けにすでに提供を開始しており、費用を伴わず無料でのアクセスを許可している点が特徴である。
一方のマイクロソフトは、Copilot Visionの提供をProプラン契約者に限定し、無料ユーザーへの開放を見送っている。この選択は、機能の希少性と価値を維持するための施策であると同時に、サブスクリプションモデルの収益構造強化を狙った布石と見ることができる。機能の類似性が顕著である中で、両社が打ち出すビジネスモデルは明確に分岐している。
GoogleはハードウェアとOSの統合によるユーザー体験の最適化に主軸を置く傾向があり、その延長線上でGemini Liveのような高度機能も無償提供される形となっている。
これに対してマイクロソフトは、クラウドと有料サービスを軸とした戦略を展開しており、AI機能の進化を定額課金の文脈で囲い込もうとしている。結果として、表面的には酷似する技術であっても、企業の成長戦略と収益設計が根底から異なることが明らかとなる。
Source:Android Police