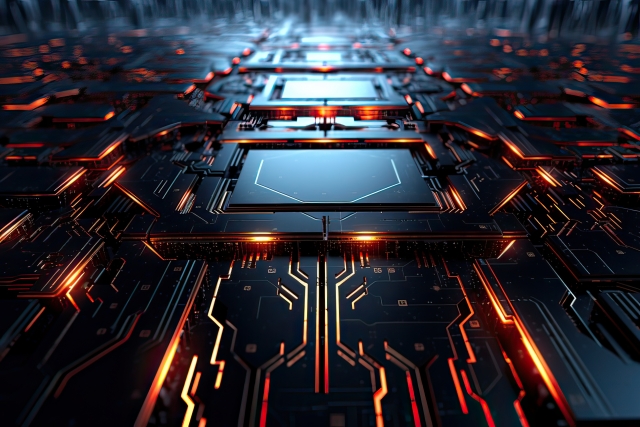AMDは、Dragon Rangeシリーズの刷新として、最大5.4GHzで動作する16コア搭載のRyzen 9 8945HXを発表した。同チップは新製品としての体裁を保つために型番を「8945HX」としているが、アーキテクチャはZen 4のままで、キャッシュ構成や製造プロセスもRyzen 9 7945HXと同一である。
統合GPUには旧世代のRDNA 2ベースのRadeon 610Mを引き続き採用し、コア数・スレッド数も変わらず、差異は一部モデルでのクロック向上のみと限定的である。AMDは市場向けマーケティングの一環として刷新を図ったと見られるが、実態はネーミングの更新にとどまり、根本的な技術刷新は次世代Zen 5まで持ち越される可能性が高い。
Ryzen 9 8945HXは名前以外の刷新が見られない

AMDが発表したRyzen 9 8945HXは、名称上は新世代モデルと位置づけられるが、アーキテクチャには引き続きZen 4を採用し、L1・L2・L3キャッシュ構成もRyzen 9 7945HXと同一である。16コア32スレッドというスペックも変更はなく、製造プロセスや統合GPUも旧来のまま据え置かれている。
統合グラフィックスには、旧世代のRDNA 2アーキテクチャを採用したRadeon 610Mが継続搭載され、演算ユニット数も2基と変化はない。
唯一、最大クロックが5.4GHzへと向上している点は性能面の差異といえるが、これは微調整の域を出ず、劇的な処理能力の向上にはつながらない。
Ryzen 9 8940HXやRyzen 7 8745HXも同様に、ベースとなる仕様は前世代のRyzen 9 7940HXおよびRyzen 7 7745HXを踏襲しており、わずかなクロック変更にとどまっている。これらの事実は、今回の刷新が性能面よりもマーケティング上の整合性に重点を置いた措置であることを示唆している。
型番刷新の裏に見える製品サイクルと市場戦略
AMDがRyzen 9 8945HXなどの新型番を投入した背景には、製品サイクルの維持とノートPC市場へのプレゼンス強化という意図が透けて見える。次世代アーキテクチャであるZen 5への本格的な移行が控える中、既存のZen 4ベースの製品に新たな型番を与えることで、継続的な販売促進と最新モデルとしての認知を維持しようとする姿勢がうかがえる。
実際、これらの新モデルはハードウェア仕様に実質的な進展が見られないにもかかわらず、「Ryzen 8000シリーズ」という響きにより、購入者に新しさを印象づける効果がある。
また、統合GPUに旧RDNA 2を据え置く点は、コストパフォーマンスの最適化と製造上の合理性を優先した判断と考えられる。ノートPC市場においては、外部GPUを前提とする構成も多く、統合GPUの進化を急がない戦略は理にかなっている。
ただし、このような刷新は技術革新というより製品寿命の引き延ばしという印象を与えるため、今後のZen 5世代で本質的な飛躍が期待される。今回の動きは、AMDが市場の反応と競合の動向を見据えた上での過渡的措置と見るべきである。
Source:PCGamesN