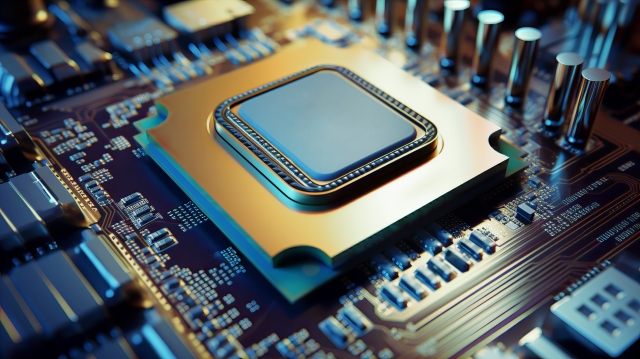AMDは、従来のDragon Rangeアーキテクチャをベースとした新型モバイル向けCPU「Ryzen 8000HX」シリーズを静かに公開した。旧世代Zen 4コアを採用しつつ、最大75Wの高消費電力設計や16コア32スレッド構成のRyzen 9 8945HXなど、ゲーミングノートPC向けの高性能仕様が特長である。
これらは専用GPUとの併用を前提とし、iGPU性能はAI 300シリーズに劣るが、最新Nvidia製GPUとの組み合わせが見込まれている。一方、米国での輸入関税強化により、供給や価格への影響が懸念される状況にある。
Dragon Rangeは既にZen 5ベースのFire Range 9000HXに置き換えられていたが、8000HXの投入はコスト重視の製品構成を目指す動きと見られ、ベンダーにとって戦略的選択肢となる可能性がある。
8000HXシリーズの技術仕様とラインナップ構成

Ryzen 8000HXシリーズは、TSMCの5nm FinFETプロセスを採用し、RDNA 2アーキテクチャに基づくRadeon 610M iGPUを搭載している。消費電力は最大75Wに達し、ハイエンドノートPC向けの設計であることがうかがえる。
上位モデルのRyzen 9 8945HXは、16コア32スレッドという構成を持ち、マルチスレッド性能を重視する用途にも対応する。一方で、Ryzen 5グレードの構成は存在せず、エントリークラスとしては8コア16スレッドのRyzen 7 8745HXが最下位モデルとして位置づけられている。
この構成から読み取れるのは、Ryzen 8000HXが量産性よりも性能面を優先し、特定のハイエンド用途に最適化されているという点である。特にゲーミングやクリエイティブ作業など、外部GPUとの協調を前提とするシナリオに焦点を当てている可能性がある。Ryzen AI 300シリーズとの機能差も明確で、AI処理や電力効率では劣る一方、クラシックなCPUパワーと構成柔軟性で差別化が図られているようだ。
米国関税政策がもたらす高性能ノートPC市場への影響
米国政府が発表した新関税政策により、中国から輸入されるノートPC製品には最大125%の関税が課される可能性が浮上している。これにより、RazerやFrameworkをはじめとするPCメーカー各社は、新モデルの販売・予約を一時的に停止する動きを見せている。ホワイトハウスは日本やベトナムなどのテクノロジー供給国を一部対象外としているが、それでも高性能ノートPCのコスト構造には大きな影響が出る恐れがある。
Ryzen 8000HXシリーズの登場は、このような地政学的な不安定要因と時期を同じくしており、製品戦略に複雑な判断を求められる状況にある。専用GPUを前提とした設計と、コストを抑えたZen 4アーキテクチャの再活用は、関税下での価格競争において一定の優位性を提供する可能性もある。ただし、製品出荷の流動性や販路の不確実性は依然として高く、各社の動向には慎重な注視が必要となる。
Source:TechSpot