2025年に入り、米中間の関税強化やMicrosoftによるデータセンター投資の減速が影響し、NVIDIA株は年初から28%下落した。しかし現在の株価は、2028年の予想利益の16.3倍という水準にとどまり、過去と比較して極めて割安である。こうした中、同社はGoogle Cloudとの提携を通じて「エージェンティックAI」領域への展開を加速させ、セキュアなAI活用を求める医療・金融・公共分野で新たな需要を開拓している。
さらに、物理AIやロボティクス分野でもGTCカンファレンスにて高度な応用例を披露し、2035年には世界のロボット市場が6倍以上に拡大するとの予測を背景に成長余地を広げる。CUDAプラットフォームによる高い参入障壁と、AIスタック全体を網羅する技術基盤の厚みは、同社の地位を揺るがぬものにしており、長期保有を前提とした投資家にとって今が好機と捉える見方も根強い。
NVIDIAとGoogle Cloudが推進するエージェンティックAIの事業化
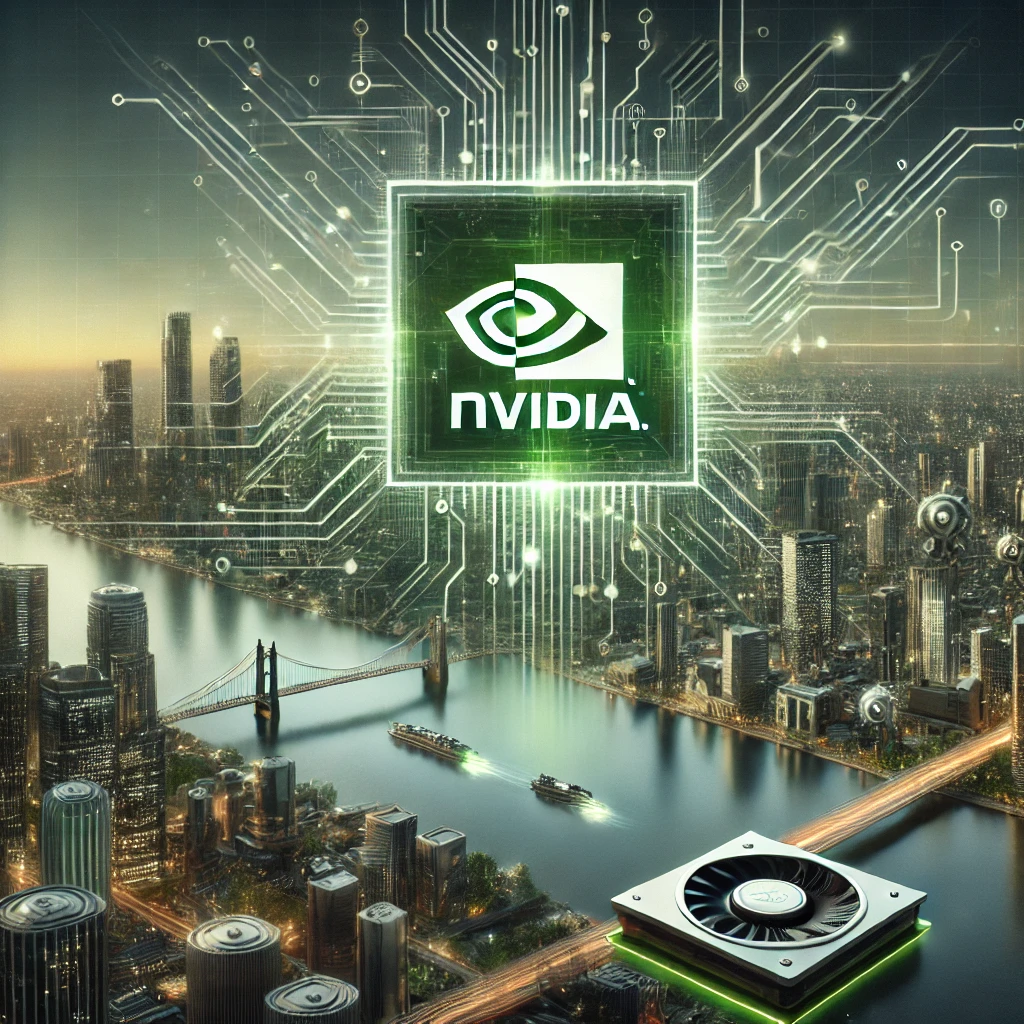
NVIDIAはGoogle Cloudと連携し、エージェンティックAIの商用展開を加速させている。これは従来のプロンプトベースAIとは異なり、自律的に意思決定を行いタスクを遂行する高度なAIシステムであり、エンタープライズ分野での活用を前提とした戦略的パートナーシップである。具体的には、GoogleのGemini AIモデルをNVIDIAのBlackwellプラットフォーム上で運用することで、各企業が自社環境内において機密性と規制準拠を維持したまま生成AIを導入できる体制が構築された。医療や金融、公共機関といった高い情報保護水準が求められる業界では、クラウド依存を最小限に抑えつつ高機能AIを実装できる点が重要な差別化要因となる。
この動きは、生成AIの産業利用におけるセキュリティと独立性という矛盾した要求に対し、一つの解決策を提示している。GPU性能だけでなく、NVIDIAの提供する包括的なAIエコシステムが業界標準として浸透しつつある現状を踏まえると、同社のAIインフラとしての優位性は当面揺るがないと見られる。ただし、AI活用が特定領域での囲い込みに繋がる懸念も残されており、今後の規制環境の変化が影響を及ぼす可能性にも注意が必要である。
ロボティクス市場で台頭するNVIDIAの物理AI戦略
NVIDIAはGTCカンファレンスにおいて、物理AIとロボティクス領域での先進的な開発成果を披露した。展示されたのは手術支援ロボットや自律配送機などで、同社のGPUとIsaac Simソフトウェアを活用したシミュレーション学習が中心に据えられている。この技術により、開発者は現実世界に投入する前に仮想空間での検証が可能となり、コスト削減と安全性の確保を両立させている。特に、遠隔操作において人間の動きを高精度で模倣するロボットアームは、製造・医療の現場における即時応用が期待されている。
また、グローバルな市場予測では、ロボティクス分野の市場規模が2024年の650億ドルから2035年には3,760億ドルに拡大するとされており、中でもヒューマノイド型ロボットの成長率は顕著である。こうした物理AIの進展は、データセンター依存のAI展開とは異なる成長ドライバーとして機能し、NVIDIAの事業多角化を支える要素となる。とはいえ、ロボティクスの社会実装は技術だけでなく、法整備や倫理的問題への対応も問われる局面に入りつつあり、同社の成長が社会との整合性の中で進むかが問われるだろう。
NVIDIAのAIスタック支配と割安感がもたらす投資妙味
NVIDIAはGPUによる演算処理能力に加え、CUDAソフトウェア基盤による圧倒的な囲い込みで市場の主導権を握ってきた。特にCUDAは、開発者にとって他の環境への乗り換えを困難にするスイッチングコストを生み出し、競合他社の台頭を抑える役割を果たしている。さらに、ハードウェアからネットワーキング、ソフトウェア、クラウド連携に至るまで、AIスタック全体を網羅する構造が確立されており、単なるGPUベンダーからAIインフラの中核企業へと変貌を遂げつつある。
2025年初頭の株価下落を受け、現在のNVIDIA株は2028年の利益予測に対してPER16.3倍という水準にあり、歴史的な割安水準と見なされている。生成AIとロボティクスという二大成長エンジンを備えた現状では、同社の事業基盤に対する長期的信頼性が再評価される余地は大きい。ただし、AmazonやMetaなどによる社内チップ開発や、オープンソースAIの進展による競争環境の変化がリスク要因として存在する点も無視できない。ゆえに、当面の株価変動は続く可能性があるが、数年単位での視点に立てば、同社は依然として最有力の投資対象と位置づけられる。
Source:msn

