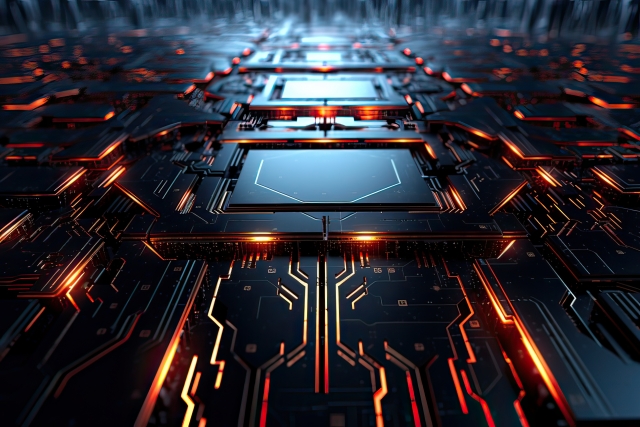インテルの最新CPU「Core Ultra 200S」シリーズが期待を下回る性能に終始したことにより、中国市場での存在感が急速に低下している。性能面での失望と相次ぐ技術的問題が消費者離れを招き、RMAの増加や採用率の低下を招いている。こうした背景から、AMDがZen 5やRyzen 9000シリーズを武器に市場を席巻し、2025年第1四半期には市場シェア50%に到達したと報じられる。
中国国内でのAMDの台頭は、インテルにとって構造的な打撃となりつつある。とりわけ、マザーボード市場にも影響が及んでおり、かつての主導権を維持することが困難な局面にある。今後の展開次第では、中国市場でAMDが完全に優位に立つ可能性も否定できない。
インテルの技術的失策が中国市場に与えた影響

インテルは「Core Ultra 200S」シリーズの投入により市場の巻き返しを図ったが、実際には期待を大きく下回る性能が露呈し、中国国内での評価を著しく損なった。
発売後の各種レビューでは、事前に公表されたパフォーマンス指標と乖離があり、多くのユーザーから失望の声が上がった。さらに、「ラプター・レイク・リフレッシュ」では不安定な挙動が報告され、これに起因して大量のRMA(返品・交換)が発生したことが、同社への信頼低下を加速させた。
これによりインテル製品の採用率は記録的な低水準にまで落ち込み、特にデスクトップCPU市場での優位性を維持することが困難になっている。同時に、マザーボード市場においてもインテル対応製品の需要が急減し、サプライチェーン全体への影響が広がり始めている。
このような状況は、製品品質と企業対応が市場シェアに直結することを改めて浮き彫りにしており、インテルのブランド戦略そのものに修正を迫る契機となるだろう。
AMDの戦略的展開と市場動向の変化
一方、AMDは中国市場においてZen 5アーキテクチャを採用したRyzen 9000シリーズやX3D搭載モデルを順次投入し、消費者層の支持を着実に獲得している。
性能面とコストパフォーマンスの両面で優位性を確保し、2025年第1四半期には市場シェア50%を達成したとの報道も出ている。これは、従来インテルが独占的に支配してきた領域での著しい変化を意味しており、今後のシェア構造に大きな影響を与える可能性がある。
加えて、AMDは新製品の安定性と供給体制においても一定の評価を得ており、不具合やパフォーマンス詐称といった問題が少ない点も市場拡大の一因となっている。
こうした状況を踏まえると、AMDの戦略的製品投入が単なる技術優位ではなく、市場心理や流通の動向まで的確に捉えた動きであったことがうかがえる。ただし、市場の流れは常に変動を伴うものであり、今後のインテルの対抗施策次第では再逆転の余地が残ることも否定できない。
Source:Wccftech