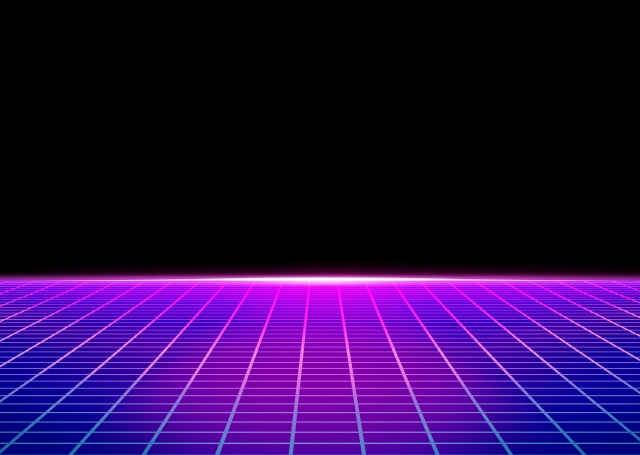1995年にリリースされたMicrosoft Bobは、PC初心者向けにカートゥーン風の家庭的なUIを採用したにもかかわらず、わずか3万本の販売にとどまり、わずか1年で市場から姿を消した。しかしこの失敗作は、2001年登場のWindows XPに思わぬ形で復活していた。元Microsoft開発者によれば、XPのインストールCDに余った30MBのスペースを埋めるため、Bobのディスクイメージが暗号化された上で“ノイズデータ”として利用されたという。
当時のダイヤルアップ環境では、この余計なデータが不正コピー対策として一定の効果を発揮していたとのこと。この逸話は、巨大ソフトウェア企業に潜むユーモアと皮肉を象徴するエピソードといえる。
Bobの大胆な設計思想と市場からの拒絶反応

Microsoft Bobは1995年に登場し、デスクトップの代わりに“デジタルの家”を構築するというユニークな設計で注目された。部屋の中にカレンダーやメールといった機能を配置し、犬のRoverといったアニメキャラクターが案内役を担う構造は、PCの敷居を下げる試みとしては画期的だった。しかし実際には、ユーザーからの支持は得られず、わずか3万本しか売れなかった。必要メモリが8MBと当時としては高負荷だったことも、導入の妨げとなった要因の一つである。
この結果、Bobは1年足らずで市場から姿を消すこととなったが、その背景には新たなOSであるWindows 95の登場も影響していたと考えられる。Bobが抱えていた問題は、見た目や親しみやすさに偏った構造設計にあり、実用性や拡張性を重視する従来のPCユーザーには受け入れられなかった。誰にとっても使いやすい設計を目指すという思想自体は否定されるべきではないが、ソフトウェアの成功にはバランスの取れた機能設計が必要であることを浮き彫りにした事例といえる。
Windows XPに仕込まれたBobの“亡霊”とその意味
Microsoftは2001年、Windows XPのインストールCDに空いた30MBの容量を埋めるため、暗号化されたBobのディスクイメージを利用した。これは不正コピー対策の一環で、追加のデータを含ませることで、当時主流だった56Kbpsのダイヤルアップ接続では違法コピーが現実的でなくなるという考えによるものだった。この試みについて、当時の開発者レイモンド・チェン氏はTechNet Magazineにて詳細を明かしている。
Bobのデータは乱数性に欠けていたため、暗号化してシャッフルされた上で利用された。CryptGenRandomなどの関数でランダムデータを生成する代わりに、あえて過去の失敗作を用いたことには、開発者の遊び心や皮肉が含まれていた可能性もある。この判断はセキュリティ技術というよりも、ユーモアを含んだ技術者的な演出として印象深い。かつて「史上最悪のソフト」と評されたソフトウェアが、何年も後に別の役割で静かに復活していたという事実は、技術の歴史における興味深い逸話として語り継がれていく価値がある。
Source:PCWorld