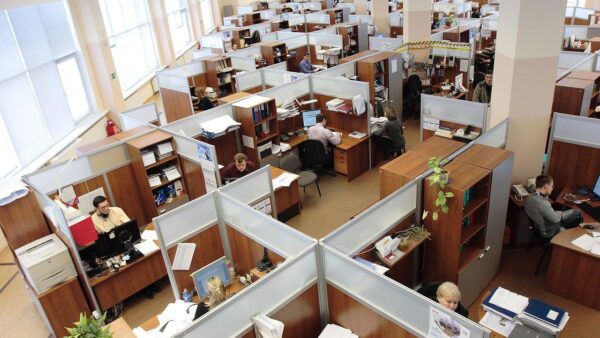Googleは、AndroidやPixel、Chromeなどの主要プロダクトを手がける「Platform and Devices」部門で、数百人規模のレイオフを実施したとThe Informationが報じた。レイオフの理由についてGoogleは「より機敏かつ効率的な運営体制の構築」と説明しており、同部門のトップであるリック・オステルロー氏の下で再編が進められている。開発対象にはAndroid AutoやWear OS、Nest、Fitbitなども含まれるが、どの製品やチームが影響を受けたのかは明かされていない。
今回の人員削減は25,000人以上が在籍する大規模組織の一部で行われたに過ぎず、Googleはサービスの継続に支障はないと強調する。ただ、ハードウェアやOSの開発に携わる重要部門での動きであるだけに、今後の機能展開や製品計画への影響が懸念される。
AndroidからPixelまで広範囲に及ぶ開発部門の再編とその背景

Googleが実施した数百人規模のレイオフは、Android、Chrome、Pixelをはじめとする主力製品を担当する「Platform and Devices」部門で行われた。The Informationによると、これは同部門の機敏性と効率性を高めるための措置とされており、Google側も正式にこれを認めている。再編の具体的な対象は明かされていないが、Android Auto、Wear OS、Nest、Fitbit、そしてChromeOSやGoogleフォトといった多岐にわたるソフト・ハードウェアが同部門に含まれている。
この部門は上級副社長リック・オステルロー氏の指揮下で構成され、従業員は25,000人を超える巨大な開発組織である。そのため、仮に一部のチームに削減が及んでも、Google全体としてのプロジェクト遂行には即座の影響が出にくい構造と考えられる。一方で、今後の新製品展開やアップデートのリズムに変化が出る可能性も排除できない。特にPixelシリーズのように年間更新を前提とする製品にとって、開発体制の微調整はそのままユーザー体験の質に繋がるため、注視が必要である。
見えないところで進行する変化とGoogleの狙い
Googleは今回の人員削減について、「エンドユーザーにとって目に見える変化はない」と明言している。これはサービス提供自体に支障は出さないという姿勢を示すものであるが、裏を返せば内部の体制変更が既にある程度想定内で進められていたことを意味する。実際、Googleは近年、AI事業を担うGeminiチームや検索、マップといった他部門と開発を切り分けており、効率的なリソース分配と分業体制の最適化を推し進めてきた。
今回の再編もその延長線上にあると考えられ、組織の柔軟性や開発サイクルのスピード向上を目指す流れに沿った動きと読み取れる。ただし、ソフトウェアとハードウェアの垣根が曖昧になりつつある現代の製品開発において、各部門の連携をどう維持するかは引き続き重要な課題となる。目に見える機能ではなく、裏側の開発構造にメスを入れた今回の判断が、今後のPixelやAndroid OSの完成度にどのように影響するかは、時間とともに明らかになるだろう。
Source:GIGAZINE