Windows 11の最新リリースプレビュー版「ビルド26100.3902」において、アップデート完了までのおおよその所要時間を事前に表示する新機能が確認された。この予想時間(ETA)は、Windows Updateの設定画面やスタートメニュー内の電源ボタン付近に表示され、ユーザーがアップデートを開始するタイミングを判断しやすくする狙いがある。
マイクロソフトはこれまで、ETAの表示について精度の問題などから導入を見送ってきた可能性があるが、今後正式実装される可能性も高いとされている。ETAが的確であれば、限られた時間の中でアップデートを行う際の不安を軽減し、ユーザー体験の向上につながるだろう。
現時点では一部テスト段階にとどまるものの、特にモバイルPCや持ち運び用途で活用するユーザーにとっては、実用的なアップデートになるかもしれない。
アップデート前に把握できる「ETA表示」がついに実装段階へ
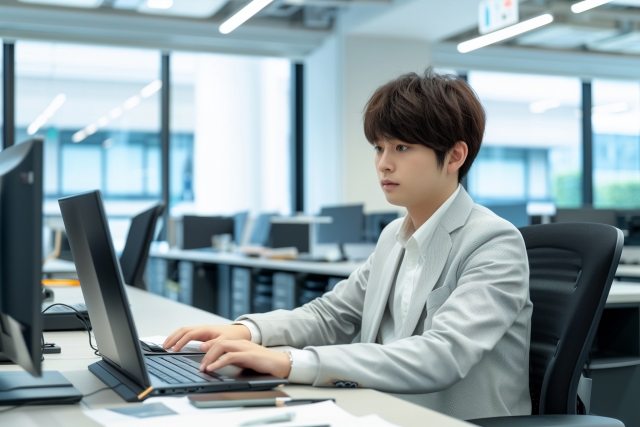
Windows 11の最新リリースプレビュー版「Build 26100.3902」にて、アップデート所要時間の予測表示機能が発見された。Windows Updateの設定画面とスタートメニュー内の電源オプションに表示され、ユーザーがインストール開始前に目安を知ることができる仕組みだ。これは、マイクロソフトの公式ブログ投稿においても紹介されており、ユーザーからの期待も高まっている。
このETA(Estimated Time of Arrival)表示は、システムがアップデート中にPCをオフラインにする時間を推定して表示するもので、例えば外出直前のタイミングや業務終了前の判断材料として有用だ。これまではアップデート開始後でないと所要時間の目安が得られなかったため、時間管理が難しかった背景がある。
ただし、マイクロソフト側もこの機能の導入を慎重に進めており、現時点では精度についての詳細な説明はなく、見積もりの正確性が課題として残されている。表示された時間と実際の所要時間に大きな乖離が生じれば逆効果になりかねず、その点に関する評価が今後の正式導入に影響する可能性がある。
時間を意識するユーザー層にとっての利便性と課題
このETA表示機能は、PCを主に持ち運び用や外出先で使うユーザーにとって特に歓迎される変更となる可能性がある。ノートPCをカフェや出張先で使っているとき、限られたネットワーク環境や電源の確保が難しい状況でアップデートに時間がかかると大きなストレスになる。事前に所要時間の目安が得られれば、無理のないタイミングで更新を開始しやすくなる。
また、アップデートが長引いた経験のあるユーザーほど、今回の変更には関心を持つはずだ。例えば、再起動を伴うアップデートで20分以上待たされた経験がある場合、「あと何分かかるのか」が分かるだけでも心理的な負担が大きく軽減される。
ただし、その期待が裏切られれば、マイクロソフトに対する不信感にもつながるおそれがある。予想時間が大きく外れれば、「信頼できない機能」として扱われる可能性もあるため、今後はユーザーの検証によって実用性の評価が進んでいくことになるだろう。現段階ではあくまでリリースプレビュー版でのテストであり、正式リリースまでにどれほど精度が高まるかが注目されるポイントとなる。
Source:TweakTown

