Honorが複数市場で投入し、今後欧州でも発売予定の「400 Lite 5G」が、その外観で物議を醸している。カメラハウジングやAIボタンの配置など、iPhone 16 Proを強く彷彿とさせるデザインが随所に見られ、背面のフラッシュまでもが擬似的に三眼構成に見える仕掛け付きだ。Honorはこれを「革新」と称するが、その主張に違和感を覚える声も少なくない。
一方で、他社製品の優れた部分を吸収する姿勢は業界全体に恩恵をもたらすこともある。Appleもまた、Androidの通話機能やマップ機能を模倣しており、こうした“相互参照”は業界の常とも言える。しかし今回のHonor 400 Lite 5Gは、既視感を超えた「模倣」の領域に踏み込んだと指摘されている。
Honor 400 Lite 5Gが採用した“iPhone流”の要素とその模倣性
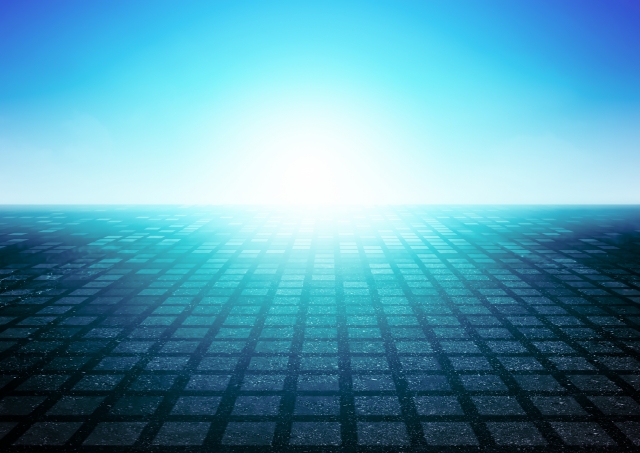
Honor 400 Lite 5Gは、外観から機能面に至るまでiPhone 16 Proを強く意識した設計が際立っている。背面カメラのレイアウトは、iPhone Proシリーズ特有の三眼スタイルを模したもので、実際にはデュアルカメラ構成でありながらフラッシュを3つ目のレンズのように配置することで、高級感の演出を狙っている。また、AIカメラボタンと呼ばれる物理ボタンは、Appleが導入したアクションボタンと非常によく似ており、その配置や見た目もiPhone 16 Proとほぼ一致する。Honorはこのボタンを「革新的」と表現しているが、その主張がiPhoneユーザーからの反発を招く一因となっている。
Android機がiPhoneのデザイン言語や機能を取り入れる例は過去にも多いが、Honor 400 Lite 5Gの場合はそれがあまりに露骨であり、模倣の度合いが一線を越えていると感じられる部分がある。特に、かつては価格帯の中で独自の方向性を模索してきたHonor 200 Liteシリーズなどと比較すると、今回のモデルにはブランドとしてのアイデンティティが希薄である印象を受ける。デザインを真似ること自体が悪とは限らないものの、今回のHonorのアプローチは、単なる「安価なiPhoneの代替品」としての評価に留まってしまう恐れがある。
AndroidとiOSの“相互模倣”がもたらす市場への影響
AndroidとiOSが互いの機能やデザインを取り入れ合う現象は今に始まったことではない。GoogleがPixelシリーズで先行した通話スクリーニング機能を、AppleがiOSにライブボイスメールという形で実装したように、プラットフォーム間の影響関係は常に存在している。また、iOS 17で導入されたオフラインマップ機能も、Androidでは10年以上前から搭載されていたものに近い。つまり、模倣自体は必ずしも否定されるべきものではなく、結果的にユーザー体験を底上げすることに繋がるケースもある。
Honor 400 Lite 5Gが採用したAIカメラボタンやカメラモジュールの演出も、機能や利便性という観点から見れば歓迎すべき要素とも捉えられる。ただし、その実装方法や表現において、既存のiPhoneユーザーが既視感を覚えるほどの類似性があることは否定できず、「独自性を感じさせないAndroid機」の烙印を押されるリスクもある。模倣が市場全体に与える正負の両面を踏まえたとき、重要なのは“何を真似たか”よりも、“どのように昇華させたか”という点にある。今回のHonorのアプローチがそれに成功しているかは、今後の評価に委ねられることになる。
個性を失ったことで見えたHonorブランドの課題
過去のHonor 200 Liteや300シリーズでは、カラーバリエーションや背面加工、UIの細かな工夫などによって、低価格ながらも独自性ある製品として注目を集めていた。しかし、Honor 400 Lite 5Gではそうした独自の路線が後退し、「iPhoneの外観を持った安価なAndroid」としての色が濃くなっている。特に、背面カメラのトリック的デザインや、iPhone風のボタン設計に対し、目新しさよりも「またか」という印象を持つ層も一定数存在すると見られる。
この変化が意味するのは、コストパフォーマンスを重視しすぎるあまり、ブランドの“らしさ”が置き去りになってしまったという点である。模倣と差別化の境界線は常に曖昧だが、Honorはこれまで「安くて個性的」という立ち位置を確立してきたメーカーであるだけに、今回の方向転換はブランドとしての軸のブレを露呈する形となった。もし今後、他のモデルでも同様の戦略が続けば、Honorに対する期待値や評価が変わってくる可能性もある。模倣に頼るのではなく、過去の強みを活かした進化が求められる局面にある。
Source:Android Central

