2025年1~3月期における中国の経済成長率は年率換算で5.4%と発表された。背景には、トランプ政権による対中関税の大幅引き上げ前に、輸出企業が駆け込み出荷を加速させたことがある。とりわけ3月の輸出は前年比12%超の急増を記録し、EVや産業用ロボットなど先端製造分野が成長を牽引した。
一方で、四半期成長率は前期比で1.2%と減速傾向にあり、不動産投資の不振と物価の低迷が経済回復の足かせとなっている。中国政府は広交会などを通じて輸出市場の多様化を推進し、対米依存の低下を図るものの、トランプ政権の関税政策次第では今後の輸出に深刻な影響が及ぶ可能性がある。
アジア開発銀行やIMFは成長率を約4.6%とする見通しを維持しているが、UBSは関税が長期化すれば輸出が最大3分の2まで減少し、2026年には成長率が3%にまで落ち込むと警鐘を鳴らしている。
輸出主導型成長の構造的限界と短期的要因の交錯
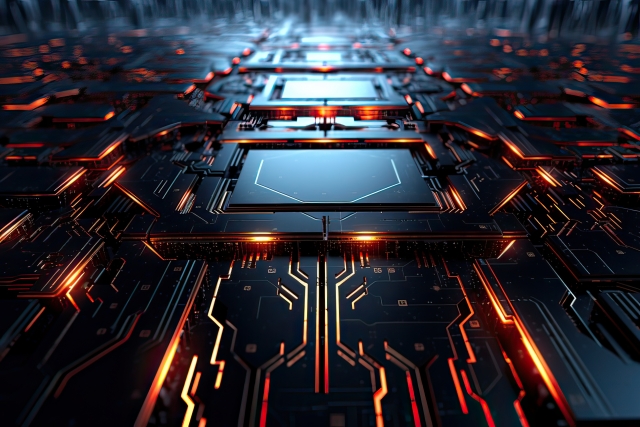
2025年1~3月期の中国経済は年率5.4%成長を記録し、製造業と輸出が成長を押し上げた。中でも電気自動車や産業用ロボット、3Dプリンターといった先端分野の工業生産は前年比で大幅な増加を示した。特に3月の輸出は前年同月比12%以上の急増となり、米国による関税発効を前にした駆け込み出荷が主因とされる。トランプ政権は中国製品の大半に最大145%の関税を課す意向であり、これにより短期的な輸出急増が発生した形である。
国家統計局は経済基盤の強さと潜在力を強調しているが、実質的には成長の構成要素は一過性の外的要因に依存しており、構造的な安定とは言い難い。四半期ベースでは成長率が1.2%と前期(1.6%)から鈍化しており、駆け込み需要の反動が次期に及ぶことは避けられない。UBSは中国のアメリカ向け輸出が今後数ヶ月で3分の2まで減少しうると見ており、対米貿易依存の調整と産業転換の進捗次第で今後の成長持続力が試される状況である。
関税戦争下の経済運営と政策対応の限界
中国は米国との対立激化を受け、輸出市場の多角化と内需拡大に政策の舵を切っている。広州交易会では輸出業者が「西が暗ければ東は明るい」と述べ、アジア諸国など他地域への展開意欲を強調した。また、政府は自動車・家電買い替え補助の倍増、不動産や資金難企業への支援強化など内需振興策を継続している。こうした対策は一見すると積極的に見えるが、実体経済の底上げには至っていない。
実際、消費者物価は前年同期比で0.1%下落しており、需要の低迷が顕著である。不動産投資も依然として弱く、前年比約10%の減少が報告されている。失業率の上昇と支出への慎重姿勢が続く中で、経済回復のエンジンとしての内需の信頼性は不透明である。IMFやADBは2025年の成長率を4.6%程度とするが、UBSは3.4%まで下方修正しており、2026年には3%を割る可能性にも言及している。関税政策の影響を完全に吸収するには、より抜本的な経済構造の改革が不可避である。
Source: Barchart.com

