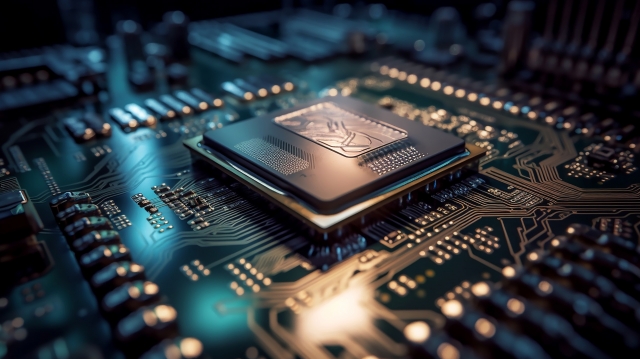AMDの次期ワークステーション向けCPU「Threadripper 9000」シリーズに、12コア構成の新モデル「9945WX」が加わる可能性が出てきた。出荷記録に基づき、同シリーズは64コアの「9985WX」や16コアの「9955WX」と並び、12コア版を含む複数のSKUが確認されている。
コードネーム「Shimada Peak」に基づくこれらのモデルは、TDP 350Wで統一され、Zen 5アーキテクチャおよび4nmプロセスを採用する見込みである。なお、96コア構成の最上位モデルの存在も指摘されており、全体として過去最大級の多様性を持つ製品群となる可能性がある。正式発表は2025年後半、Computexでの発表が期待されているが、3D V-Cacheの搭載を含む技術仕様の全容は未だ明らかではない。
Shimada Peakに見るZen 5 Threadripperの実装構成と設計方針

AMDが展開予定のThreadripper 9000シリーズは、コードネーム「Shimada Peak」として64コアから12コアに至る複数モデルを備え、サーバー用途とワークステーション向けの多様なニーズに対応する構成であることが出荷記録から確認された。
Ryzen Threadripper 9985WX(64コア)、9955WX(16コア)、9945WX(12コア)という3種のモデルはいずれもTDPが350Wで統一されており、これは高いクロック性能と電力制御の両立を意識した設計思想を物語っている。Zen 5アーキテクチャおよび4nmプロセス技術の採用によって、前世代との比較でIPC向上と省電力性のバランスが期待されるが、詳細仕様やベンチマーク結果は現時点では不明である。
特に12コアモデルの登場は、Threadripper史上初めての構成であり、エントリーから中負荷向け市場への拡張を意識したラインナップ戦略の一端とみられる。
これらの構成に共通するのは、プラットフォームとしてTRX50およびWRX90チップセットが採用される点である。Threadripper 9000とPRO 9000はいずれも同一ソケット(SP6)を用い、PCIe Gen 5対応、最大128レーン接続など、ハイエンド帯のデータ処理能力を前提に設計されている。
加えて、3D V-Cacheの搭載が一部で取り沙汰されているものの、現段階では正式な仕様としては示されていない。搭載の有無によっては、HPC分野やコンテンツ制作業務におけるパフォーマンスの差異が大きく変動する可能性がある。構成の広がりは歓迎すべき要素であるが、性能・価格・消費電力の三要素がどのような市場バランスをもたらすかは今後の公式発表に委ねられている。
Threadripper 9945WX登場が示唆する市場戦略の変化
Threadripper 9000シリーズにおける12コア構成の「9945WX」は、従来のThreadripperラインにおいて見られなかった新しい試みであり、これが意味するのは単なるSKUの追加以上の戦略的意義である。これまでのThreadripperは24コア以上の高負荷処理向けが主力であったが、今回の9945WXは4基のCCDに各3コアを割り当てるという構成が想定され、比較的軽量なワークロードを想定した設計と解釈される。
TDPは他モデルと同様に350Wであり、高密度CCD活用によるスレッドバランス最適化を重視している姿勢が読み取れる。L3キャッシュやメモリ帯域の詳細は不明であるが、Zen 5世代としての基本仕様を踏まえると、単なる下位互換製品ではなく、用途特化型の性能バリエーションと捉えるべき構成といえる。
この12コアモデルの追加は、Threadripperシリーズが従来の「最大性能」一辺倒から、より多様な業務環境への適応を意識し始めた兆候ともとれる。例えば、中規模の建築設計、映像編集、科学シミュレーションなどでは16コア以上のスペックが過剰となる場合も少なくない。そうしたニーズに対し、Threadripperの安定性やI/O性能を保ちつつ、コア数を抑えた構成が提供される意義は大きい。
また、同一プラットフォームでの拡張性確保という設計思想も明確であり、用途や予算に応じた柔軟な選択肢を提示することが可能となる。本モデルの市場投入は、これまで手の届かなかった層への浸透を促し、結果としてThreadripperブランド全体の認知と普及を押し広げる効果をもたらす可能性がある。
Source:Wccftech