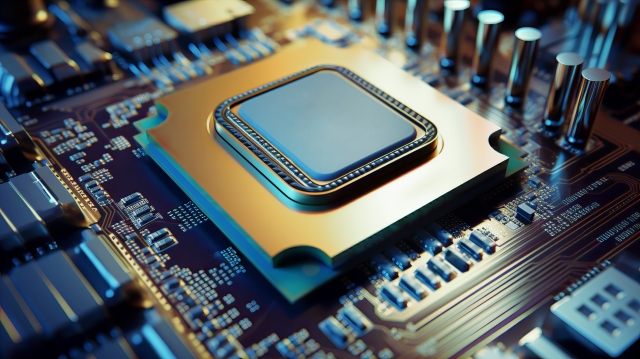Intelの次世代デスクトップCPU「Nova Lake」は、LGA1954ソケットへの移行が示唆されている。これは出荷明細から明らかとなったもので、専用インターポーザーやリボーリング治具など、新プラットフォーム向けテストキットが各地に配布されている。
また、Nova Lakeの初期構成は、Coyote Cove Pコア8基、Arctic Wolf Eコア16基、SoCタイル内にLPEコア4基を含む、最大52コアのハイブリッド構成となる見通しである。正式な投入は2026年とされるが、900シリーズPCHとの連携や、従来より小型のサウスブリッジ設計も検討されている。現時点では試験段階にあるが、LGA1954がRaptor Lake以来の抜本的刷新となる可能性に注目が集まる。
LGA1954ソケットへの移行とテスト用ハードウェアの存在

Intelは次世代デスクトップ向けCPU「Nova Lake」において、新たにLGA1954ソケットの導入を検討している可能性が出荷書類から浮上した。NBD.ltdの資料には「NVL-S」向けのテスト機材が記されており、完全なマザーボードではなく、主に電圧調整用のインターポーザーとみられる部品が含まれている。
さらに、888ボールのBGAチップに対応したリボール治具の存在も確認されており、Nova LakeのPCH設計が進行中であることを示唆している。これらの試験用部材が世界各地に送られているという事実は、LGA1954プラットフォームの実装に向けた工程が静かに進んでいる証左と捉えることができる。
一方で、出荷書類に記載されているからといって即座の市場投入を意味するわけではなく、製品化に向けた初期段階に過ぎないとの見方が妥当である。特に、2026年登場とされるNova Lakeの正式リリース時期を踏まえれば、現段階は開発フェーズの中でも検証工程に位置づけられよう。
LGA1954が採用されれば、1,954ピンのアクティブ接点を含む新しいソケットアーキテクチャが導入され、プラットフォームの刷新が確実視されるが、実装が最終決定されたかどうかは依然不明である。
52コア構成を視野に入れたNova Lakeの設計戦略
IntelがNova Lakeで描く構成は、既存製品とは一線を画す野心的なアプローチを示している。初期の設計では、8基のCoyote Cove高性能Pコアと、16基のArctic Wolf高効率Eコアによる2クラスタ構成に加え、SoCタイル内にさらに4基のLow-Power Efficient(LPE)コアが組み込まれる見込みであり、最大で52基のハイブリッドコアを搭載する構成となる。
ただし、この全構成が最終製品に反映されるかどうかは不確定であり、現在は複数の設計案を並行して検証している段階とみられる。
このコア構成は、パフォーマンスの向上と電力効率の両立を追求するIntelの最新アーキテクチャ戦略の一環であると考えられる。特に、省電力用途に特化したLPEコアの搭載は、デスクトップ環境におけるアイドル時やバックグラウンド処理の最適化を意図している可能性がある。
アーキテクチャの刷新と組み合わせたこの大胆な構成が、2026年以降のPCパフォーマンス競争における差別化要因となるかは、今後の詳細な仕様開示に委ねられるだろう。
LGA1851の短命とArrow Lake Refreshの位置付け
現在のLGA1851プラットフォームは、LGA1700の後継として導入されたものの、その寿命の短さが自作市場では懸念材料となっている。
Intelのソケットは通常2世代にわたり活用される設計思想を採っていたが、LGA1700ではAlder LakeとRaptor Lakeのアーキテクチャが大きく変化せず、リフレッシュモデルに留まった経緯がある。LGA1851も同様に、Arrow Lake Refreshの登場が計画されているとの観測が存在し、これがLGA1954導入までの一時的措置である可能性を示している。
このような背景から、自作ユーザーやシステムインテグレーターの間ではプラットフォームの将来性に対する不透明感が広がっている。頻繁なソケット変更は、互換性や投資対効果の面で慎重な判断を迫る要因となる。
とはいえ、LGA1954が本格導入されれば、性能・機能両面での飛躍が期待されることから、Arrow Lake Refreshは一定の過渡期的な役割を果たす存在となる可能性がある。その意義は、次世代の布石としてどこまで市場に納得されるかにかかっている。
Source:Tom’s Hardware