伝説的投資家ベンジャミン・グレアムは、その名著『証券分析』の中で、ウォール街では「熱意」がしばしば破滅を招くと警鐘を鳴らした。グレアムの指摘によれば、市場の熱狂は合理的判断を鈍らせ、投資家を過信と群衆心理の渦に巻き込む。
この洞察は、ウォーレン・バフェットの投資哲学の根幹にも強い影響を与えた。特にバブル相場では、損失を回避できるという誤信と高揚感が相まって、冷静な分析よりも欲望が支配する構造が生まれる。その結果、優秀な頭脳を持つ者でさえ、大きな損失を被る危険性をはらんでいる。
成功の象徴「熱意」が市場で裏目に出る理由
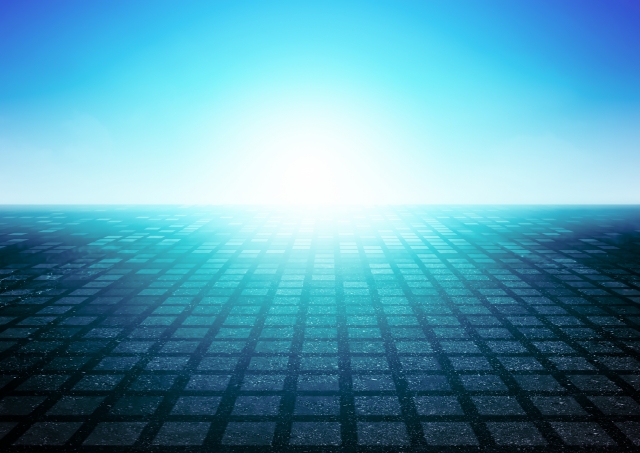
ベンジャミン・グレアムは、投資の世界においては「熱意」が危険な感情であると繰り返し説いてきた。ウォーレン・バフェットの師として知られるグレアムは、他分野での成果を生む原動力である熱意が、金融市場では過信と群衆心理を刺激し、損失の引き金になると指摘する。特に、上昇相場では市場参加者の期待が自己増殖的に膨らみ、価格が実体価値を離れて暴走しやすい。このような状況では、理性的な分析が感情にかき消され、客観性を失った判断が繰り返される。
事実、サウスシーバブルにおけるアイザック・ニュートンの失敗は、いかに優れた知性をもってしても市場の熱狂には無力であることを示している。バフェットも、投資と投機の境界が曖昧になりやすい環境では、成功体験がかえって判断力を鈍らせると警告する。利益が続くと、人は自らの行動を正当化し、リスクを過小評価する傾向を強める。この構図が、バブル崩壊の構造的な土台となる。
一方で、熱意そのものが悪ではないという見方も成り立つ。問題はその熱意を制御できるかどうかにある。市場という感情の集合体を相手取る投資では、冷静さこそが最大の武器であり、むしろ熱意を持たないことが生き残るための戦略となる。
評価の歪みを生む「物語」と市場心理の危うい関係
市場が過熱すると、投資家は従来の評価基準を棚上げし、成長ストーリーや流行語に魅了される傾向を強める。グレアムが「本質的価値から目を逸らすもの」として批判したのは、PERが50倍や100倍という水準まで正当化されるような状況である。こうした環境下では、「今回は違う」「革命的なビジネスモデル」などの言説が力を持ち、定量的分析よりも感情や流行が価格を押し上げていく。
このような「おとぎ話」への依存は、評価の秤が壊れる瞬間を意味する。市場参加者は次第に合理的思考を放棄し、群衆行動に同調することを優先する。こうした動きは、熱意に駆られたトレンド追随が支配的になった状態であり、評価の本質を無視する姿勢といえる。また、SNSやメディアの情報が増幅装置として機能することで、バブル構造が加速する側面も否定できない。
冷静に考えれば、「成長しているから高い」という論理は、価格と価値の混同に他ならない。価格の上昇が価値の証明だとするなら、それはもはや投資ではなく投機である。こうした誤認を防ぐためには、熱狂の渦中でこそ、数字に立ち返る態度が求められる。感情に流されず、物語ではなくファンダメンタルを見つめる視点が不可欠となる。
グレアムが説く「秤」と「投票機」の違いに学ぶべき教訓
グレアムは「市場は重さを量る秤ではなく、票を投じる投票機である」と述べ、市場価格が常に真の価値を反映するものではないことを示した。この視点に立てば、投資における成功とは知識量の差ではなく、感情を律する姿勢の有無にかかっているといえる。実際に、行動ファイナンスの研究でも、上昇相場における投資家の判断力の低下と過信の拡大が確認されている。
過熱相場では、短期的な成功体験が心理的バイアスを助長し、「自分だけはうまく立ち回れる」という幻想に浸る傾向が強まる。こうしたバイアスを打破するには、あらかじめ設定した明確な投資ルールや利益確定の基準を守り抜くことが重要である。例えば、自動利確ルールや上限バリュエーションの設定は、感情に依存しない判断を下す手段として有効である。
また、取引の都度その理由を記録する習慣も、後の振り返りを可能にし、感情的判断を見抜く助けになる。懐疑的かつ逆張り的な視点を育てることも、市場の歪みに巻き込まれないための有効な手段である。バフェットの「他人が貪欲なときには恐れ、他人が恐れているときには貪欲であれ」という名言にある通り、市場との距離感が投資家の明暗を分けるのである。
Source:Investopedia

