IntelのフラッグシップCPU「Core Ultra 9 285K」が、Linux環境における再テストで平均6%の性能向上を記録した。注目すべきは、最新の「200S Boost」BIOSによるオーバークロック機能を用いずに達成された成果である。Ubuntu 25.04上でのPhoronixによるベンチマーク結果は、特にシングルコアおよびゲーミング性能の改善が顕著であり、Arrow Lakeアーキテクチャの持つポテンシャルが徐々に開花しつつあることを裏付けた。
こうした進展の背景には、Intelが推進するパフォーマンスコアと効率コアの役割を最適化する設計思想がある。Linuxカーネルのスケジューリング改善やドライバ更新の効果も見逃せず、特定のコアにタスクを割り当てる制御の洗練が、性能底上げに寄与していると考えられる。さらに、オーバークロック機能に保証が適用される新BIOSの登場は、潜在的な性能向上の余地をユーザーに広げる可能性を示唆している。
Core Ultra 9 285Kの性能がLinuxで6%向上 新BIOS未適用下で確認された実質的進化
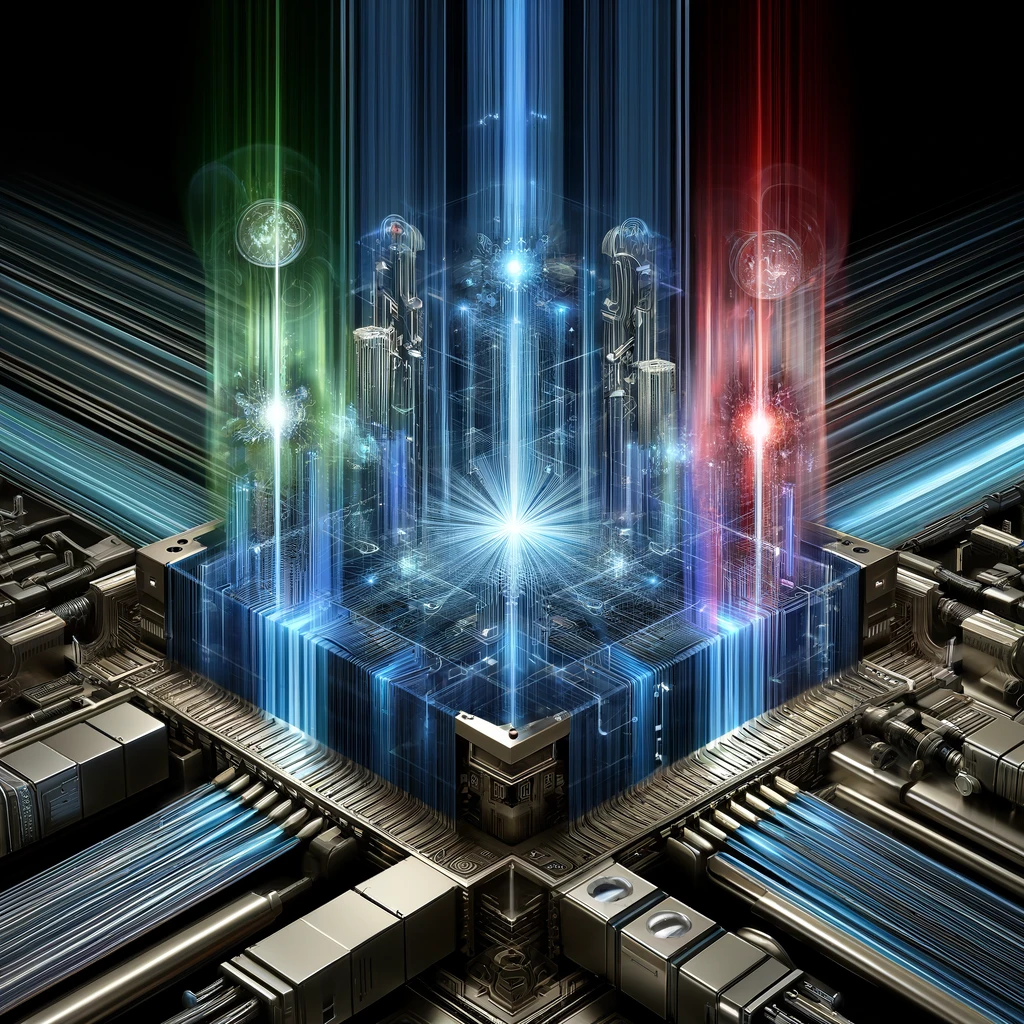
IntelのArrow Lake世代に属するCore Ultra 9 285Kが、Phoronixによる再検証で平均6%の性能向上を示した。注目すべきは、この改善が最新の「200S Boost」BIOS機能を用いない状態で達成されている点である。Ubuntu 25.04上でのLinuxベンチマークにおいて、特にシングルコア処理とゲーミング分野で顕著な改善が確認された。これにより、初期段階で酷評された同CPUの評価が、一部の分野において見直されつつあることが示唆される。
この性能向上の要因には、Intelが推進する「ビッグコア/スモールコア」構成の設計最適化が大きく関与している。Linuxカーネルにおけるスケジューリング精度の向上と、ドライバの継続的な調整が、より効率的なコア使用を実現した結果である。また、Intel自身が行ったBIOS更新も特定の作業負荷に対するパフォーマンス分配の改善に貢献しており、ハードウェアの物理仕様に依存しない進化が進行している現状が読み取れる。
Arrow Lake設計思想とLinux最適化の融合が性能向上を後押し
今回の再テスト結果からは、単なるクロック周波数やコア数の増加では説明しきれない、設計思想とソフトウェア最適化の融合による性能向上が見て取れる。とりわけ、PコアとEコアのタスク割り当てに関する制御精度が、Linux上で著しく改善されていることが明らかとなった。これにより、リソース分配が動的かつ効果的に行われ、結果として全体的な処理性能の向上へとつながっている。
このアプローチは、従来の「スケールアップ」的な進化とは異なり、ハードウェアの構成そのものよりも制御アルゴリズムやスケジューラの成熟度に依存するものである。特にLinuxにおける最適化は、ソースコードへの直接的な介入が可能であるため、カーネルレベルでの高度なチューニングが行われやすい環境にある。こうした条件が、Intelの設計戦略と合致する形でポテンシャルの引き出しに貢献している。
200S Boost BIOSの登場が暗示する今後の性能進化の方向性
Intelが同日に発表した「200S Boost」BIOS機能は、オーバークロックによるパフォーマンス向上に加えて、その適用範囲に保証が付くという点で従来とは異なる意味合いを持つ。この機能では、メモリとファブリックのオーバークロックを行っても保証対象外とならない設計が施されており、これまで高リスクとされていた設定を、より多くのユーザーが試行可能となる。Phoronixによる初期テストでは、200S Boost適用時に約7.5%の速度向上が確認されている。
とはいえ、今回の再検証ではこの新機能を適用せずとも一定の性能向上が実現されている点に注目すべきである。これは、ハードウェア単体での限界性能を追求する段階から、ソフトウェアとファームウェアの継続的進化によってシステム全体の最適化を図る段階へと移行しつつある兆しと捉えることができる。200S Boostのような機能が一般化すれば、今後のCPU性能評価は単なるスペック比較ではなく、エコシステム全体の統合性能という視点がより重視されることになるだろう。
Source:Tom’s Hardware

