IntelがTSMCの最先端2nmクラス「N2」プロセスに基づく製造契約を結んだとの報道が浮上した。対象となるのは、次世代CPU「Nova Lake」のハイエンドモデルとされており、Arrow Lakeの後継として最大52コア構成が見込まれている。Intelは18Aプロセスを進める一方で、社内製造能力やパッケージング問題を理由に、一部ダイの外部委託を進めている。
過去にもTSMC製ノードを活用してきた同社だが、今回は18Aの生産負荷軽減とローンチスケジュールの遵守が背景にある。N2採用により、Intelは技術的優位性よりも供給安定性を優先した可能性が高く、製造戦略の柔軟性が問われる局面にある。
TSMCのN2プロセス受託により明らかになったIntelの製造分散戦略
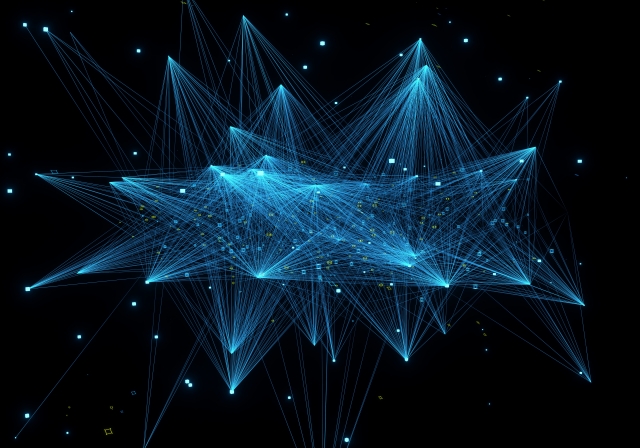
IntelがTSMCの2nmクラス「N2」プロセスに製造を委託する動きは、次期Nova Lakeプロセッサに関するデュアルソーシング方針を体現するものである。Nova Lakeは、最大52コアという異例のハイブリッド構成を持つとされ、Coyote CoveやArctic Wolfなどの先端マイクロアーキテクチャを組み込む。こうした高性能製品は、確実な量産能力が求められる。Intelは従来、自社開発の18Aプロセスでの内製を軸としていたが、昨年11月の時点で一部製品の外部生産を正式に表明していた。
今回のN2活用は、AMDが同プロセスをZen 6「Venice」で採用する発表と時を同じくしており、競合との技術主導権争いにも影響を与える。一方で、TSMCはNova Lakeだけでなく、過去にもArrow LakeやLunar Lakeなどに対しN3BやN6など複数ノードを提供してきた実績があり、Intelの信頼を得ている。18AについてはClearwater ForestやDiamond Rapidsでの活用が予定されており、パッケージングの課題も指摘されている。TSMCとの協業によって、量産リスクの分散と製品投入のスピード確保が期待されている。
製造の外部委託によるコスト増という側面も否定できないが、Arrow LakeにおいてもIntel 3と外部ノードの並立運用が行われており、今回の動きはその延長線上にある。Intelの製造ポートフォリオは、今後さらに多層的な構造を取る可能性がある。
先進パッケージングと製造能力の限界が招くアーキテクチャ選別の現実
Nova Lakeに関しては、Pコア・Eコア・LPEコアを含む三層構造の実装が見込まれているが、その中でも高性能帯の製品がTSMCのN2プロセスで製造され、低性能帯はIntelの18Aで賄われる可能性が示唆されている。この構成選択は、単なる性能指向ではなく、プロセスの量産歩留まりやライン供給能力の違いに起因するものと考えられる。特に、18Aは高い集積度と先進的なパッケージング技術を必要とするClearwater Forest向けに最適化されており、コンシューマー向け製品との両立が難しい局面に直面している。
TSMCのN2を高性能ダイに充てることで、製品群全体の最適なバランスを図る狙いがあると見られるが、この配分は単に技術力の問題ではなく、量産体制という現実的制約が背景にある。Nova Lakeが新ソケットLGA1954を採用し、既存の800シリーズマザーボードと互換性を持たないとされている点からも、従来製品との差別化が明確に意識されている。
このような製造上の現実を踏まえると、18Aの採用製品は今後も限定的となる可能性が高く、Intelは社内製造能力のボトルネック解消に向けて、外部ファウンドリとの連携を戦略的に強化せざるを得ない状況にある。特に2026年に見込まれるNova Lakeの市場投入時期を考慮すると、複数ノードの並行運用は必然の選択肢となる。
Source:Tom’s Hardware

