世界のAI市場は2033年までに4.8兆ドルへと急拡大する見込みであり、その成長の中心にはGPUを提供するNvidiaが存在する。現在、NvidiaはAI用GPU市場の70〜95%を掌握し、CUDAによる開発者囲い込み戦略が競争優位性を支えている。
しかし今、アナリストは新たにIntelとAMDの2社に注目している。特にAMDはNvidiaの最新チップと互角以上の性能を持つ製品を展開し、データセンター依存度の高さが将来的なレバレッジとなる。一方、Intelは米軍やAmazonとの契約獲得によりAI向けチップ市場での巻き返しを狙う構えである。
2030年にNvidiaを超える可能性は高くないものの、両社は長期的な成長を期待できる存在として、慎重な投資家の関心を集めつつある。
AI用GPU市場におけるNvidiaの絶対的優位とその要因
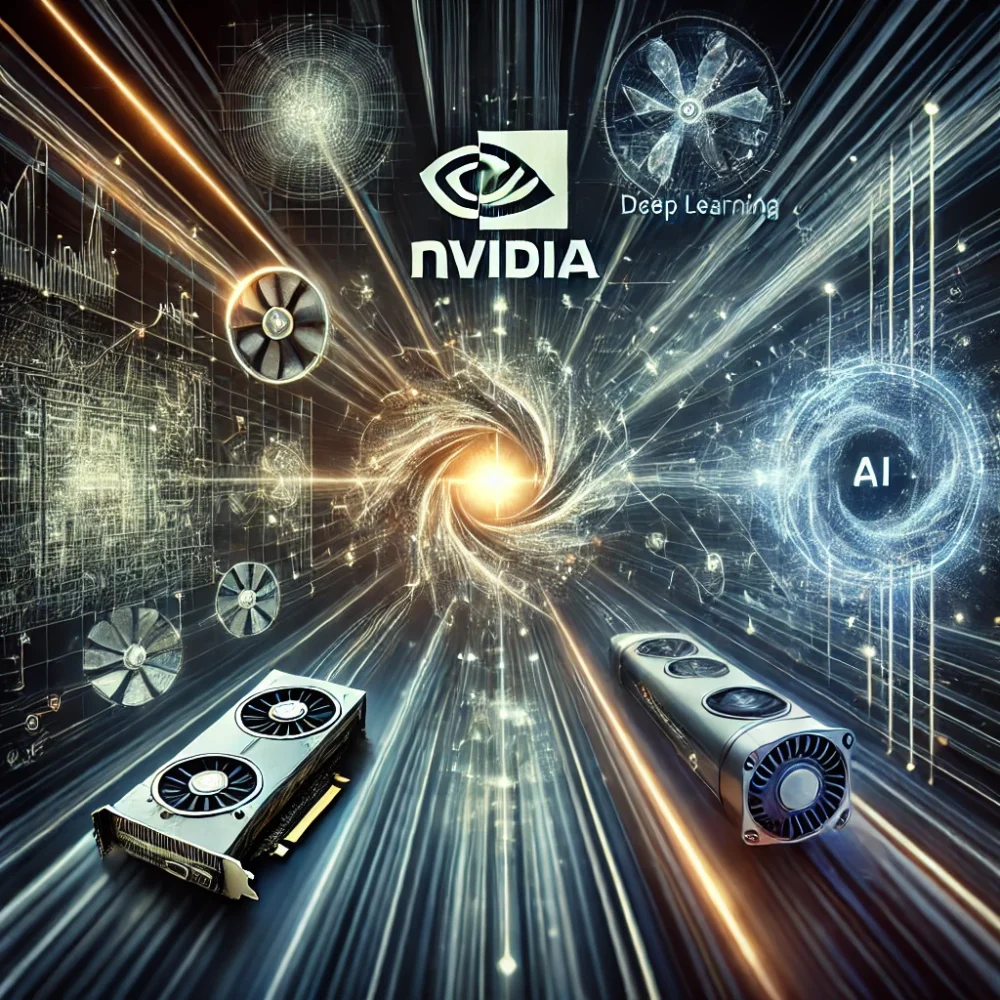
NvidiaはAI向けGPU市場の70〜95%という圧倒的シェアを有している。AIモデルの学習と推論を支えるこれらのGPUは、同社が2006年に発表したCUDAアーキテクチャによって飛躍的に最適化されてきた。このプラットフォームにより開発者は自社製品に特化したアプリケーションの構築が可能となり、ソフトウェアとハードウェアの密接な結びつきが生まれた。これが事実上の囲い込みを生み、競合の参入障壁として機能している。加えて、NvidiaはクラウドベンダーやAIスタートアップとの提携を通じ、供給網の確保と市場支配を同時に実現してきた。これらの取り組みが現在の評価額数兆ドルという企業価値を支えている。
しかし、この優位性は永続的なものではない可能性がある。CUDAに依存するソフトウェア設計は柔軟性を欠くという声もあり、オープンソース型の並列処理アーキテクチャが進展すれば、囲い込みの力は相対的に弱まる。また、需要過多による供給遅延も競争力の一部に陰りを与えている。こうした状況を踏まえると、Nvidiaの現在の優位は確固たるものである一方で、将来的には競合勢の台頭が現実味を帯びてくることも否定できない。
AMDの技術進化とデータセンター戦略が示す成長余地
AMDはAI向けGPU市場でNvidiaに迫る存在として注目を集めている。最新のベンチマークでは、同社のGPUがNvidiaの「Blackwell」シリーズに匹敵する処理能力を示し、特にAIモデルの大規模データ処理領域で顕著な成果を上げている。さらに、AMDは供給能力の高さにおいても一歩先を行く。Nvidiaが供給遅延に直面している中、AMDは比較的短期間での出荷が可能であり、顧客にとって信頼性の高い代替手段となっている。また、同社は全体収益の52%をデータセンターから得ており、この分野でのAI依存度が非常に高い。これは、AI産業との連動性が強く、今後の市場成長と利益の拡大に直結する構造を持っていることを意味する。
ただし、CUDAのような独自エコシステムを持たない点では依然として劣位であり、ソフトウェア面での汎用性と互換性に課題が残る。また、ブランド力や開発者コミュニティの厚みでもNvidiaに及ばない部分がある。それでも、市場が成長する中で需要が分散し、性能とコストパフォーマンスを重視する動きが強まれば、AMDの存在感は一段と高まると考えられる。現在の時価総額に対して、将来的な収益成長余地は依然として大きいといえる。
Intelの巻き返しと巨大契約が示唆する戦略的布石
IntelはAI用GPU市場では後発ながら、巻き返しを図る動きを加速させている。同社は昨年末、Amazonとの間で数十億ドル規模のAIチップ契約を締結し、さらに米国防総省とも同様の大型案件を獲得した。これは、同社の製造能力と技術が一定水準にあることを市場に示す象徴的な出来事であった。また、Intelの時価総額は約800億ドルとAMDの1400億ドルを大きく下回り、バリュエーション面では割安感が強い。売上高に対する株価倍率も1.5倍と控えめであり、期待値が低く織り込まれている現状は、投資妙味を感じさせる余地を残す。
一方で、現在の技術力では依然としてNvidiaやAMDに及ばないとの見方も根強く、短期的に劇的な成果が出る可能性は高くない。加えて、ソフトウェアエコシステムの欠如やAI専門人材の不足といった構造的課題も横たわっている。とはいえ、国家レベルの支援やクラウド大手との連携によって、戦略的布石は着実に打たれつつある。Intelが技術と製造の両面で突破口を見い出せれば、2030年以降に意外な展開を見せる可能性も視野に入る。
Source:The Motley Fool

