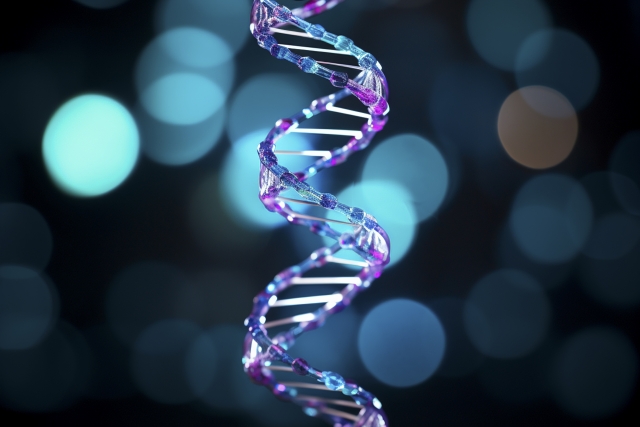AMDは、Instinct MI300X向けGPU仮想化技術「GIMドライバー」のオープンソース化を発表した。これはLinux環境でROCm 6.4を利用する仮想化基盤に対応するもので、Phoronix報道によれば、将来的にはRadeonデスクトップGPUへの対応も見据えているとされる。また、MES(Micro Engine Scheduler)のオープン化も進行中で、技術資料は5月下旬に公開される予定である。
この動きの背景には、Hot AisleやTiny CorpなどAI領域の開発企業からの強い要望がある。とりわけTiny Corpは、オープン化の遅れがGPUの性能活用を阻んでいると批判し、ハードウェアとソフトウェアの緊密な協調を求めていた。
AMDが本格的にソフトウェアスタックのオープン化へ舵を切ったことは、開発者とのエコシステム形成を強化し、NVIDIAとの競争構造において戦略的意義を持つ。ただし、GIMドライバーがLinuxカーネルに統合される時期など、実装上の課題は依然として残されたままである。
GIMドライバーのオープンソース化が示す仮想化対応戦略の深化

AMDは、Instinct MI300X向けに開発されたGIM(GPU IOV Manager)ドライバーをオープンソース化し、Ubuntu 22.04 LTSとROCm 6.4の環境下で利用可能とした。GIMドライバーは、仮想マシン上でGPUを効率的に分割・共有するためのインフラとして位置づけられ、これにより高性能コンピューティング環境におけるGPUリソースの柔軟な運用が可能となる。今回の開示は、Phoronixによれば、RadeonデスクトップGPUへの将来的な展開を見据えているとされ、データセンターとエンドユーザー製品を横断する仮想化戦略の基盤構築とも捉えられる。
AMDが長らくブラックボックスとしてきたソフトウェアスタックに対し、この段階的な透明化の動きは、オープンな技術協調を通じた開発者層の取り込みを狙ったものである可能性が高い。ただし、現時点ではGIMドライバーのLinuxメインラインカーネル統合や、対応製品の具体的な拡大時期などの情報は一切明らかにされておらず、その成熟度は限定的であると言える。今後、AMDが仮想化対応の標準技術としてGIMをどこまで普及させるかが、オープンソース戦略の成否を左右することになる。
AI関連スタートアップの働きかけが促したソフトウェア公開の背景
今回のGIMドライバーのオープンソース化は、AMD単独の技術判断ではなく、外部のAI開発者企業による実務的要請に起因する側面が大きい。2024年2月、ハイパフォーマンスコンピューティング事業を展開するHot Aisleが、開発支援体制とハードウェアアクセスの拡充をAMDに要望。
これを契機として、開発者向けのクレジットプログラムが拡大され、MI300XやDell製ハードウェアへのアクセスが開放された経緯がある。さらに、AIインフラ企業Tiny Corpが、独自サーバー「TinyBox」へのGPU統合で発生した非互換問題を指摘し、ソフトウェア層の非公開が障壁になっていると公に主張したことが、AMDの対応を後押しした。
こうした外部からの圧力は、AMDが持つソフトウェア独自仕様の限界を浮き彫りにしたとも言える。とりわけ、カスタマイズ性やデバッグの自由度が求められる生成AI関連分野においては、NVIDIAのCUDAに比べて選択肢が限られているという不満が、開発コミュニティ内で高まっていた。AMDは今回、開発者側の指摘を受け入れる形で対応を開始したが、これは単なる技術提供ではなく、エコシステム形成を企業戦略に取り込む必要性を認識したことの現れでもある。
Radeon対応とMES公開計画に見るソフトウェア展開の次の段階
GIMドライバーは現時点でInstinct MI300X専用だが、AMDのロードマップ上にはRadeonデスクトップGPUへの展開も記載されている。また、GPUのスケジューリングを担うMicro Engine Scheduler(MES)のオープンソース化も同時に進行しており、ドキュメントとソースコードは2025年5月下旬の公開予定とされている。これにより、GPUリソースの配分や命令制御の細部に至るまで開発者による最適化が可能となり、ハードウェア制御の自由度が一段と高まることになる。
MESの公開は、単なる技術の可視化にとどまらず、AMDアーキテクチャの理解を深めるための知的基盤の提供という意味を持つ。これまで限られたパートナー企業のみに提供されていた低レベル技術情報が、今後は広範な開発者層に開放されることで、サーバー用途やAI推論向けにAMD GPUを選択する動機付けとなる可能性がある。ただし、実際の運用現場では、オープン化されたソフトウェアの品質維持や互換性検証といった新たな課題も生じるため、AMDがそれに対する継続的な責任をどのように果たしていくかが、次の焦点となる。
Source:Tom’s Hardware