IBMは2025年第1四半期決算で、ソフトウェア部門の9%増収とAI契約の累計60億ドル突破を背景に、市場予想を上回るEPSを記録した。生成AI基盤のWatsonxやRed Hatの急成長が、全社収益の約45%を占めるソフトウェア事業を強く牽引している。
一方で、コンサルティング部門は景気敏感な構造が足かせとなり、収益横ばいに留まった。企業支出の慎重化や政策不確実性が重なり、株価は決算直後に6%超下落。全体の構造改革と投資戦略により回復基調も見られるが、市場の信頼は限定的にとどまる。
短期的には株価の上値余地が限られる一方、長期投資家にとっては高収益ソフトウェア基盤と生成AI戦略の深化が魅力となり得る。
ソフトウェア事業の成長が示すIBMの事業構造転換の成果
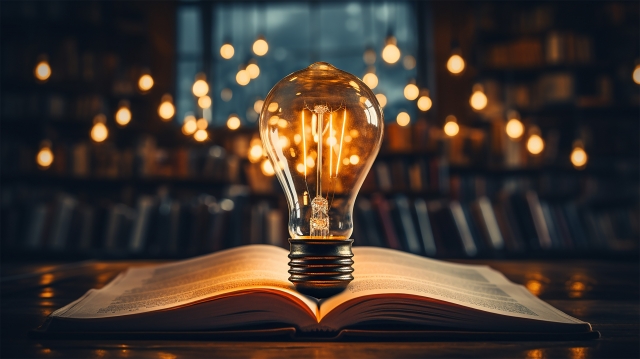
2025年第1四半期決算において、IBMは収益145億ドル、調整後EBITDA34億ドルを計上し、EPSは1.60ドルとアナリスト予想を上回った。その原動力は、全社収益の45%を占めるソフトウェア事業の堅調な伸長にある。前年比9%増収を記録したこのセグメントでは、Red Hatの13%成長や自動化領域の15%増加が目立ち、特にOpenShiftのARRが15億ドルに到達し、四半期で25%成長するなど、事業の柱としての存在感を強めている。
また、生成AI関連の成長が顕著であり、Watsonxプラットフォームなどを含むAI関連サービスの自然成長が全体成長の6ポイント分に寄与した。IBMは生成AI関連の契約総額が60億ドルを突破し、直近四半期だけで10億ドルを新規に獲得している。これらの動きは、同社のハイブリッドクラウドとAI戦略が収益の安定化と成長の両面で機能していることを示している。
継続的収益が全体の80%を占める構造が示すように、IBMはプロジェクト単発型の収益構造から脱却しつつある。クラウドとAIという長期トレンドに支えられたポートフォリオの強化は、今後の業績下支えに寄与する要素といえる。一方で、これらの成長ドライバーが外部環境の変動に対してどの程度の耐性を有しているかについては、今後も慎重な検証が必要である。
コンサルティング部門の伸び悩みが露呈した決算後の株価下落
好調な決算発表にもかかわらず、IBMの株価は2025年4月24日のプレマーケットで6%以上下落した。その背景には、同社のコンサルティング部門が示した収益の停滞と、今後の見通しに対する不安がある。コンサルティング事業の収益は前四半期と比較して横ばいであり、顧客の意思決定の遅れや裁量支出の抑制、さらには米国政府の効率化政策(DOGE)などが影響を及ぼしたとされる。
この部門はプロジェクト型ビジネスであり、企業の資本支出や政策動向に左右されやすい特性を持つため、マクロ経済環境の影響を最も早く受ける。特に関税や政策変更の影響を受ける業界向けの支援では、さらなる成長鈍化も予想される状況にある。ただし、クラウドプラットフォームやアプリケーションの近代化といった高付加価値分野では顧客関心が継続しており、一定の需要は維持されている。
市場はこの脆弱性に敏感に反応しており、全社の収益構造における安定部門と脆弱部門の格差が株価調整の主因となった。投資家の間では、長期的な見通しよりも短期的なリスク要因が重視された可能性が高い。IBMが構造改革を進める中で、この部門がどのようにして再成長の道を描けるかが今後の評価に直結するだろう。
ソフトウェア成長に対する期待と株価の上値余地に対する市場の温度差
過去12か月でIBMの株価は約25%上昇しており、その背景にはAIとクラウドを中核に据えた成長戦略への市場の評価がある。アナリストの平均目標株価は252.28ドルとされており、現在株価からの上昇余地は限定的とみられている。アナリストの評価も「適度な買い」にとどまり、市場全体が同社に対して過度な楽観を抱いていないことを示している。
同社の戦略は明確であり、高収益かつ継続性の高いソフトウェアを軸に、クラウドおよびAI領域の深耕を進めている。しかし、これらの成長ドライバーが他セグメントの不振をどこまで補えるかについては、依然として確信が持たれていない。特に、生成AIなど新規分野の収益性がどの程度持続可能であるかに対する見方は分かれている。
現状の成長加速には、全セグメントでのパフォーマンス強化が不可欠であり、部分的な成功では市場を納得させるには不十分である。したがって、株価上昇を持続させるためには、今後の決算で広範な事業の改善を裏付ける具体的な成果が求められるだろう。現段階では、期待と実績の間に一定の温度差が存在している。
Source:Barchart

