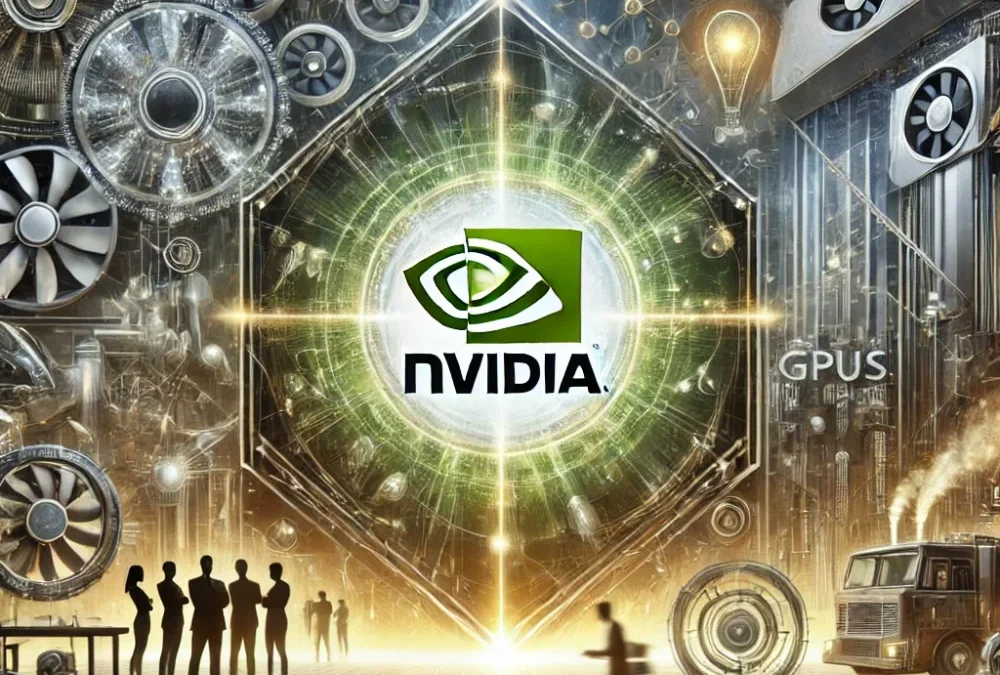過去10年間で株価が18,000%以上も上昇し、世界第3位の時価総額を誇るNvidiaは、AI向けコンピュータチップ市場で圧倒的な地位を築いてきた。しかし、TSMCは製造技術の優位性と顧客基盤の広さにより、今後10年でNvidiaを上回る可能性を持つと指摘されている。TSMCはAppleやBroadcomを含む多様な顧客を抱え、価格交渉力でも主導権を握ることで、安定した成長と収益確保が見込まれる。
Nvidiaのような特定企業への依存リスクを避け、半導体需要全体の拡大から恩恵を受ける戦略を持つTSMCは、長期的により安全かつ確実なリターンをもたらすとみられている。特に、インフレや関税のコスト増を価格に転嫁できる強みは、製造業者としての圧倒的な立場を裏付ける。結果として、TSMCがNvidiaを超える企業価値を築く未来が期待される。
TSMCが築く半導体製造の支配的地位とNvidia依存構造の実態
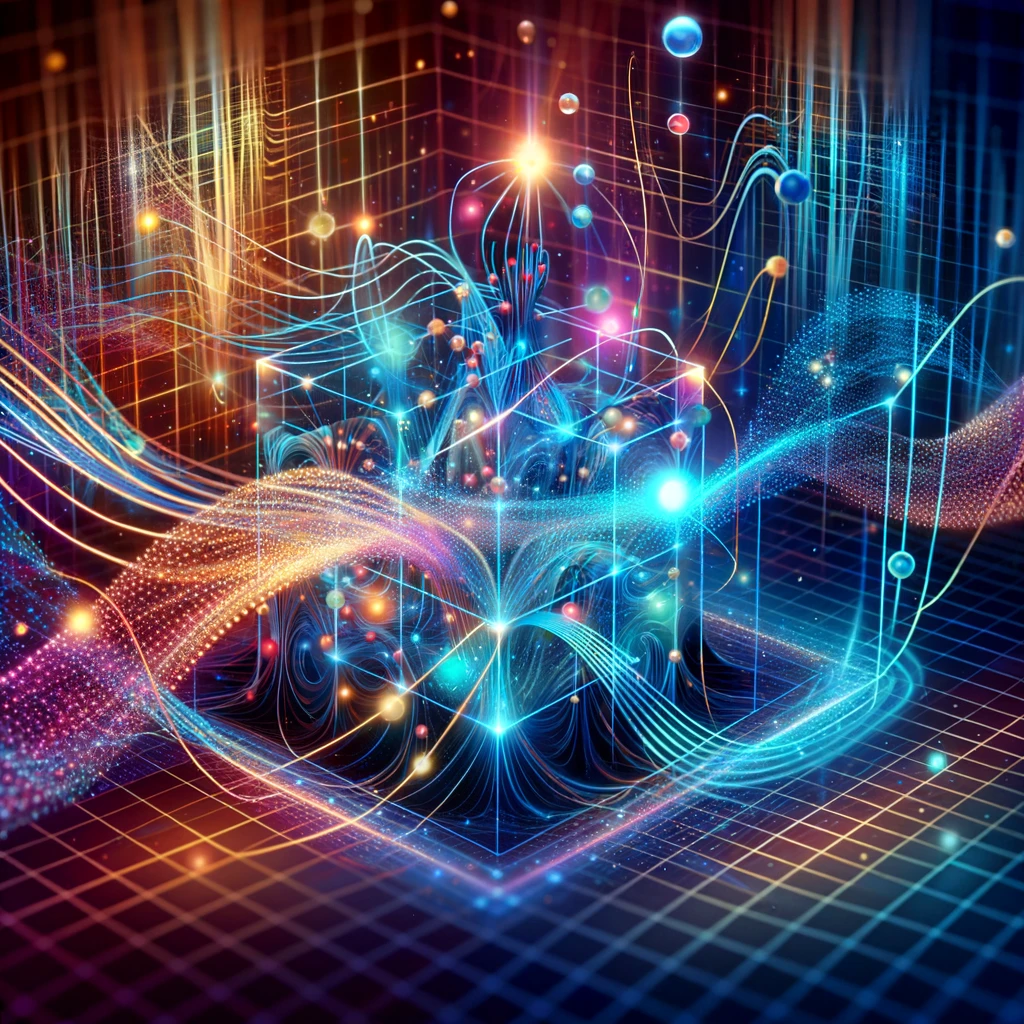
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSMC)は、AppleやBroadcomをはじめとする複数の主要顧客向けに最先端チップを製造し、競合他社との差別化を実現している。サムスンを除けば、AI向けに必要な最新鋭半導体の製造能力を有するのはTSMCのみであり、この技術的優位性が顧客の乗り換えを困難にしている事実は注目に値する。
報道によれば、TSMCはアリゾナ新工場での価格30%引き上げを検討しており、これにより関税負担の一部を顧客に転嫁する可能性がある。AppleやNvidiaにとって、TSMC以外に生産を委託できる現実的な選択肢は存在せず、これがTSMCに圧倒的な価格決定権を与えている。
この構図を踏まえれば、TSMCの製造主導権は今後も維持されると見るのが妥当である。Nvidiaの競争力は、設計力と製品力に依存しているが、その根幹を支える製造基盤をTSMCに委ねざるを得ない状況が続く限り、TSMCの立場は相対的に強固となる。製造設備への膨大な投資と技術進化を背景に、他社が容易に代替できない存在であることは、半導体市場全体におけるTSMCの影響力をさらに高める要素となり得る。
安定成長を支えるTSMCの多様な顧客基盤とリスク分散戦略
TSMCの強みは、単なる規模の大きさだけではない。NvidiaやAppleといった巨大顧客に加え、Advanced Micro Devices(AMD)、Amazon、Alphabetといった企業のチップ生産も担っており、特定顧客への依存度を抑えたビジネスモデルを確立している。世界的な半導体需要の増加という追い風の中で、TSMCは460億ドルの営業利益を過去12か月間で計上しており、同分野で世界最大級の収益規模を誇る。この広範な顧客網と分散されたリスク構造は、景気変動や特定市場の減速による打撃を緩和する仕組みとなっている。
一方で、Nvidiaの収益成長はAIブームに大きく依存しており、将来的に市場シェアを失うリスクも無視できない。これに対し、TSMCは市場構造の変化に柔軟に対応できる体制を築いており、たとえ個別顧客が競争に敗れても、他の新興勢力に対応することで成長を維持できる点が際立つ。長期的な視点に立てば、こうした安定的な成長力とリスク分散こそが、TSMCの企業価値を支える堅固な土台となるだろう。
インフレと関税コストを武器にするTSMCの収益確保戦略
TSMCは、製造工程の卓越性だけでなく、価格決定力をも収益拡大の武器として活用している。アリゾナ工場で検討される30%の価格引き上げは、単なるコスト転嫁ではなく、インフレや関税政策を逆手に取った収益確保策と位置付けられる。
米国市場での半導体需要が高止まりする中、顧客側にはTSMCの提示価格を受け入れる以外の選択肢がほぼ存在しない。これにより、インフレ環境下においても利益率を維持できる独自のビジネスモデルが成立している。
Nvidiaなどの設計企業は、製造を外部委託する構造上、自社単独ではコスト上昇リスクを回避できない。このため、TSMCの価格引き上げがNvidiaなどの利益を圧迫し、結果的にTSMCの利益に吸収される構図が生まれる。こうしたサプライチェーン上の力関係は、TSMCが外部環境の変動を超えて安定した収益を確保できる構造的優位性を証明するものであり、10年後に企業価値でNvidiaを超える可能性を高める要素と見なすことができる。
Source:The Motley Fool