インテルはアリゾナ工場での「Intel 18A」ウェハー初回ロットの製造開始に加え、次世代ノード「14A」に搭載予定の新技術「ターボセル」を正式発表した。これはCPUクロックの引き上げおよびGPUの重要回路速度の向上を目指すもので、「RibbonFET 2」や「PowerDirect」といった革新技術と組み合わせて導入される。
「ターボセル」は、設計ブロック内で性能重視と電力効率重視のセルを用途に応じて最適配置するアプローチを取り、パフォーマンスと消費電力、チップ面積のバランス最適化を図るものである。これにより、微細化の限界が指摘される中でも性能向上の道筋を示すとされている。
インテルは同時に、14Aおよび18Aプロセスの多層接続技術「Foveros Connect」や「EMIB」の進展も発表し、社内製造への転換を通じてTSMCへの依存低減とファウンドリ競争力の回復を図る方針を明示した。
Intel 14Aプロセスが示す次世代製造技術の転換点
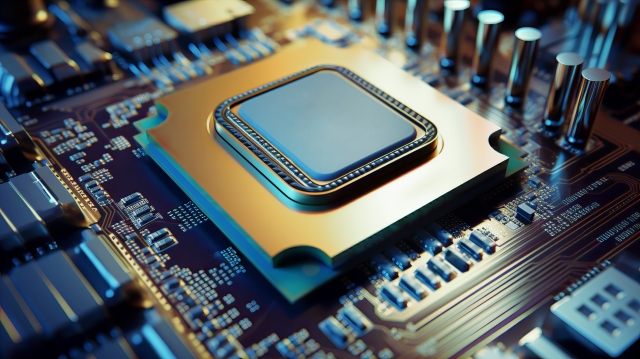
インテルは「Intel 18A」プロセスに続き、2026年登場予定の「Intel 14A」において、半導体性能向上の鍵を握る複数の新技術を搭載する。「PowerDirect」と称される第2世代の裏面電力供給アーキテクチャは、従来の「PowerVia」に代わり、電力伝送効率と熱制御性能を一段と高める狙いを持つ。
また、次世代トランジスタ「RibbonFET 2」によってスイッチング速度とトランジスタ密度の両立が図られる。これにより、トランジスタ単位での性能向上をもたらし、プロセスの根幹部分からの革新が実現される。
さらに注目すべきは、回路ブロックの特性に応じて高性能セルと電力効率重視セルを組み合わせて配置可能とする「ターボセル」の導入である。これにより、クロックの最大値や演算経路のスループットを高めつつ、用途に応じた柔軟な設計最適化が可能になるとされる。
このアプローチは、物理限界が迫る中でチップ設計の自由度を維持する策とも捉えられる。Intel 14Aが提供するこうした構造的革新は、単なるプロセスノード更新ではなく、製造思想そのものの再構築に等しい。
FoverosとEMIBによる次世代パッケージ戦略の展開
インテルは半導体の性能競争において、製造プロセス単体の進化にとどまらず、パッケージ技術の領域でも複数の重要な布石を打っている。今回発表された「Foveros Connect」および「EMIB(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)」の拡張は、異種ダイ間を3次元で高密度に接続する技術革新であり、14Aおよび18A-PTといった異なるプロセスを統合するための基盤となる。
インテルはこの技術を通じて、将来的な高帯域メモリ実装にも対応可能な「EMIB-T」や、「Foveros-R」「Foveros-B」といった新派生技術の開発も進めている。
これにより、従来は個別に設計されていたCPU・GPU・I/Oダイを垂直・水平に最適配置し、全体としての性能密度向上と省スペース化が可能となる。これはモノリシック設計の限界を補完する戦略であり、他社との差別化を図るうえで極めて重要な要素である。
パッケージ技術はもはや補助的存在ではなく、プロセッサ全体の競争力を決定づける中核となっており、インテルはその主導権を握る体制を構築しつつある。
Source:PCWorld

