Nvidiaの新型GPU「GeForce RTX 5060」を搭載したゲーミングノートPCが、GeekbenchのOpenCLベンチマークにおいて、従来モデルRTX 4060比で約18%の性能向上を記録した。テストではColorful製ノートPCが最大109,431ポイントを達成し、Cyberpunk 2077においてもフルHD・最高設定で146fpsという結果を示した。これにはCUDAコアの増強、GDDR7メモリ、DLSS 4のAI処理強化が寄与しており、エントリークラスGPUの域を明確に超えている。
一方で、RTX 4060搭載PCもDLSS 3.5により依然として堅実な性能を維持しており、既存ユーザーにとっての買い替えメリットは限定的との指摘もある。特に最新のIntel Core Ultra 9より旧型Core i9構成のほうが高得点を出すなど、構成次第では必ずしも最新が最適とは言い切れない点も注目すべきである。
RTX 5060が示した性能の実測値と構成別のスコア差異
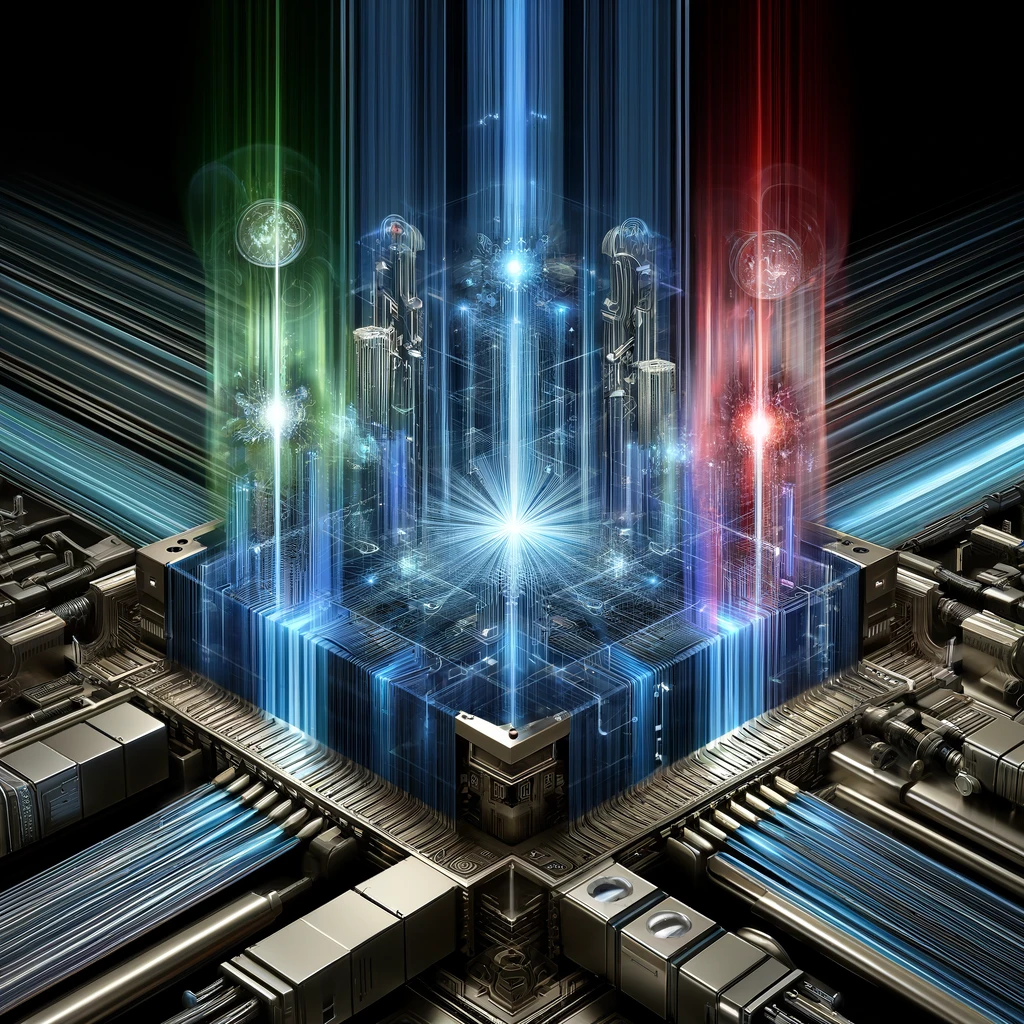
RTX 5060ラップトップGPUは、GeekbenchのOpenCLベンチマークにおいて前世代のRTX 4060に対して明確な性能上昇を示した。Colorfulの2機種、P15 ProおよびiGame M15 Origoに搭載されたRTX 5060は、それぞれ109,431点および102,564点というスコアを記録し、RTX 4060搭載のHP Omen 16の92,756点を上回った。これにより、同一カテゴリ内における新旧世代間の性能差が実証された形となる。
興味深いのは、より新しいIntel Core Ultra 9 285Hを搭載したモデルよりも、従来のCore i9-13900HXを採用した構成の方が高スコアを叩き出している点である。これは、現行のIntel製CPUにおいてもアーキテクチャの刷新が必ずしも性能向上に直結しないことを意味する。加えて、32GBのDDR5 RAMを標準装備とする構成が、GPU性能の最大化に寄与している可能性も考慮すべきだ。
一方で、GeekbenchのOpenCLベンチマークはあくまでGPUの並列処理やレンダリング能力を測定する指標に過ぎず、実際のゲーミング体験全体を代表するものではない。したがって、ベンチマークスコアをもって即座に製品優劣を断定するのではなく、各種使用条件下での挙動の評価も今後不可欠となる。
RTX 5060がもたらすAI対応と次世代ゲーム体験の可能性
Nvidiaによれば、RTX 5060ラップトップGPUはGDDR7メモリと3,328基のCUDAコアを搭載し、DLSS 4およびマルチフレーム生成といったAI技術に対応している。この技術的飛躍により、『Cyberpunk 2077』においては1080p・最高設定で146fpsを達成するという驚異的な数値が示された。これはRTX 4060の60fpsや、さらに旧型のRTX 3060の21fpsと比較しても圧倒的な進化である。
DLSS 4は、従来のDLSS 3.5よりも一層高度なAIアップスケーリングとフレーム生成機能を統合しており、高フレームレートかつ高画質なゲーム体験を実現する鍵を握る。また、8K動画編集への対応を示すNvidiaの見解は、RTX 5060の用途が単なるゲーミングに留まらず、クリエイティブ用途にも拡張される可能性を指し示す。
ただし、AI機能の真価は実際の操作環境やソフトウェアとの統合性に大きく依存する。ベンチマークにおけるスコアや性能説明のみで判断することは避け、実際のゲーミングや編集用途におけるユーザー体験の検証が今後の焦点となる。また、RTX 4060搭載機でもDLSS 3.5により安定した性能が得られていることを踏まえれば、新機種の導入判断には慎重な比較検討が求められる。
買い替え対象としての位置付けと価格戦略の課題
RTX 5060は、旧世代のRTX 2060や3060を搭載したノートPCを使用しているユーザーにとっては有力なアップグレード選択肢となる。特に、DLSS 4によるAI機能の強化やGDDR7への対応は、旧モデルでは得られなかった描画性能と処理速度の飛躍をもたらす。これにより、数年ぶりの買い替えを検討するユーザー層に対しては明確な利点が提示されている。
しかしながら、既にRTX 4060搭載ノートPCを所有している層にとって、性能向上幅は限定的であり、現段階でのアップグレード動機としては弱い。実際に、4060搭載のAsus TUF Gaming A14のようにDLSS 3.5と高い完成度を併せ持つ製品は依然として市場価値が高く、現行機の持続利用を妨げる要素とはなっていない。
さらに、RTX 5060搭載ノートPCの価格は1,099ドルからとされているが、過去のRTX 5060 Tiの販売動向を踏まえると、実売価格がこの水準を大きく上回る可能性は否定できない。価格帯が適正でなければ、想定されるエントリー層への普及は限定的となり、結果として上位モデルとの価格競合を引き起こす懸念もある。市場投入後の価格形成と消費者反応が今後の成否を左右する。
Source:Tom’s Guide

