インテルは「Intel Foundry Direct 2025」において、2027年にリスク生産が予定される新プロセスノード「14A」の性能指標を初公開した。18Aノードと比較し、電力効率は最大35%改善、トランジスタ密度は1.3倍に達する。新技術「PowerDirect」により裏面からの電源供給を最適化し、動作周波数の向上と消費電力削減の両立を実現可能とした。
さらに、CPUおよびGPUのクリティカルパスに特化して高性能を引き出す新設計「Turbo Cells」も発表された。これは標準セルの中でも特に密度が要求されるShortライブラリを基盤とし、駆動電流を増強しつつ高密度化を維持する設計である。
Turbo Cellsは高速・低効率セルと省電力セルを同一設計内で併用可能とし、設計自由度を大幅に高めた。RibbonFET 2や多様なセル構成と組み合わせることで、設計者に新たな最適化手段を提供する技術として注目される。
電力効率とトランジスタ密度で際立つ14Aノードの技術的進展
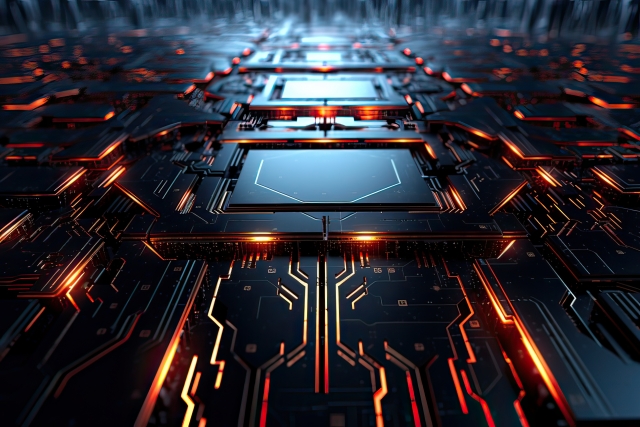
インテルが発表した14Aノードは、18Aノードからの進化形として設計されており、特に電力効率と密度面で顕著な改善が見られる。
パフォーマンスあたりの電力効率が15〜20%向上し、同等の性能を保ちながら最大35%の消費電力削減が可能とされる点は、高性能・低消費電力設計が求められるサーバーやAI向けアプリケーションにおいて大きな意義を持つ。また、トランジスタ密度も1.3倍に高まり、より多くの機能を同一面積内に集約できるようになった。
これらの技術的成果の背景には、インテルが導入した新たな裏面給電構造「PowerDirect」がある。従来の表面からの電源供給とは異なり、電力供給経路を再設計することで信号干渉を抑制し、動作周波数の向上に寄与している。さらに、RibbonFET 2と呼ばれる新世代トランジスタ構造も搭載され、ナノシートを4層に積層することで、スイッチング性能と面積効率を高めている。
これにより、電力密度が厳しく制約される次世代SoCの開発においても、高性能を維持しながら実装可能な設計基盤が整いつつある。プロセスノード単体ではなく、トランジスタ構造、電源供給、設計ツール群の統合的進化が、インテルの製造戦略における中核であることが浮き彫りとなった。
Turbo Cellsが切り拓くクリティカルパス最適化と設計自由度の新次元
Turbo Cellsは、CPUおよびGPUにおけるクリティカルパスの最適化を目的に導入された新型標準セルであり、性能と設計効率の両立を狙う極めて戦略的な要素である。
これまで高速トランジスタの採用は性能向上と引き換えに電力消費やリーク電流の増加を招いていたが、Turbo Cellsは駆動電流を向上させつつも、密度と電力のバランスを保つ構造が特徴である。特にShortライブラリをベースとしながらダブルハイト構成を採用することで、限られた面積内でも設計柔軟性を確保している。
加えて、nmos・pmosリボン幅や構成の調整により、セル単位で駆動能力を制御できる点も見逃せない。設計者は高負荷パスには高速セルを、低負荷パスには省電力セルを組み合わせることで、システム全体のPPA(Performance, Power, Area)を細かく最適化できるようになる。このように、Turbo Cellsは単なるセル設計ではなく、設計思想そのものの変革を促す存在となっている。
これにより、従来はトレードオフとされていた性能と効率の両立が、領域単位での制御により現実的な選択肢となる。高性能SoC設計において、周波数制約や電力制限が並列的に存在する状況下で、Turbo Cellsのような設計資産が提供する柔軟性は、競争優位性に直結する可能性を秘めている。
Source:Tom’s Hardware

