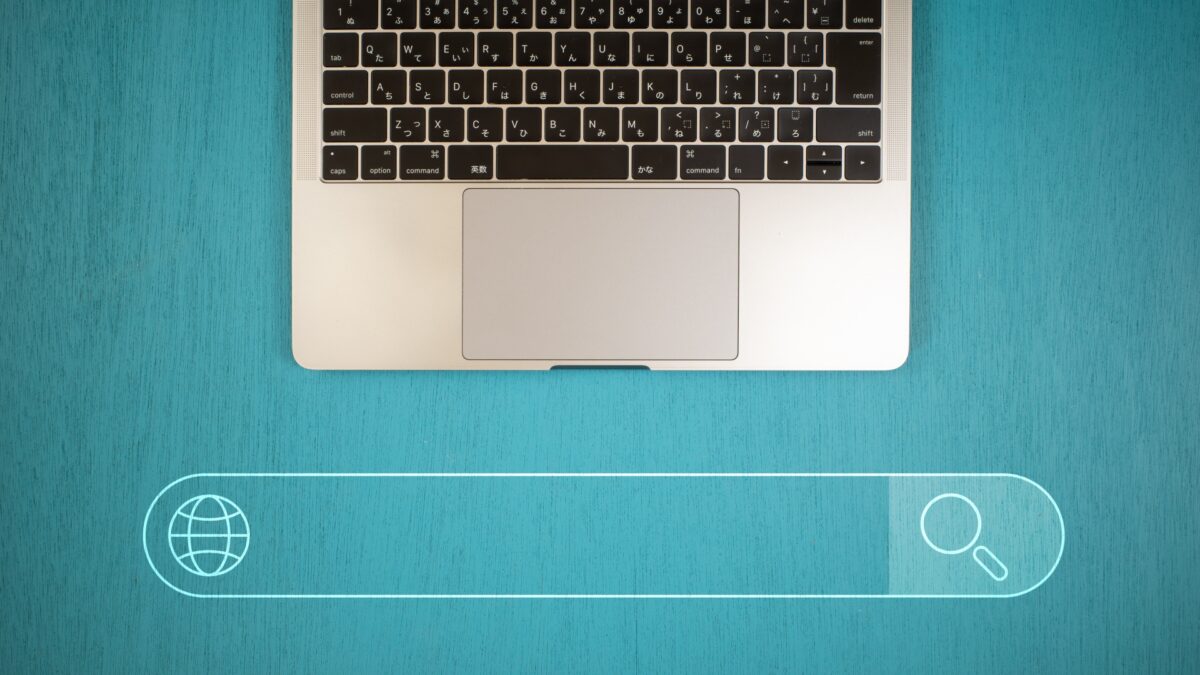IntelはCore Ultra 7 200シリーズのデスクトップ向けプロセッサに対して、最大100ドルの希望小売価格引き下げを正式発表した。たとえば、265Kは399ドルから299ドル、265KFは384ドルから284ドルへと改定されたが、これはあくまで推奨価格であり、市場実勢とは異なる。今回の調整は最上位のUltra 9や主力のUltra 5には及ばず、限定的なモデルに留まっている点が特徴的である。
一方で、同社は第14世代「Raptor Lake」の販売は堅調であるものの、最新の「Arrow Lake-S」や「Meteor Lake」の出足が鈍いことも認めており、この価格戦略がシェア維持の一環である可能性は高い。価格が高めとされるLGA1851プラットフォームの普及を促すためには、選別的な値下げとバンドル施策が不可欠であり、競合AMDへの対抗と再評価が今後の鍵を握る。
Core Ultra 7の大胆な価格改定 265Kは100ドル引きで実質25%の値下げ

Intelは2025年5月、Core Ultra 7 200シリーズの一部モデルに対し最大25%の価格引き下げを公式に実施した。中でもCore Ultra 7 265Kは、希望小売価格が399ドルから299ドルへと100ドル下落し、265KFも384ドルから284ドルに引き下げられた。
これは希望小売価格(SRP)ベースの改定であるため、小売現場の実売価格は地域や販売業者によって異なる可能性がある。また、今回の措置はシリーズ全体ではなく、Ultra 7に限定されたものであり、Ultra 9やUltra 5の価格には一切変更が加えられていない。
今回の発表は、Intel自身が公式に価格改定を表明した点でも注目に値する。通常、半導体業界では価格の変動は市場の動向に応じて暗黙裡に行われることが多く、メーカー側が明示的に引き下げを認めるのは極めてまれである。Intelはこの改定について、販売促進の一環としての立場を取りつつ、同時にバンドル施策や販促キャンペーンとは切り離していることを強調している。これにより、Core Ultra 7を単体でより魅力的な選択肢とし、販路拡大を狙う構図が浮かび上がる。
一方で、希望小売価格の改定が必ずしも市場価格に直結するとは限らない点には注意が必要である。小売業者の仕入れ在庫や地域別の需要格差が影響するため、消費者の体感価格に反映されるかは今後の流通状況次第である。とはいえ、Intelのこのタイミングでの価格戦略は、競争が激化するデスクトップCPU市場において、特定モデルに集中した販促で存在感を維持するための動きと見られる。
Raptor Lakeの健闘とArrow Lake-Sの苦戦が示す市場の選好
Intelは今回の価格改定に関連し、Core Ultra 200シリーズの新プラットフォーム「Arrow Lake-S」への移行が期待よりも鈍いことを認めている。その背景には、同社の前世代製品である第14世代「Raptor Lake」シリーズの継続的な市場支持がある。
特にゲーミング分野においては、Raptor LakeがArrow Lake-Sを上回るパフォーマンスを示しており、ハイエンド志向のユーザーや自作PC愛好家にとって依然として高い評価を得ている。これは新製品が必ずしも旧製品を上位互換として超えるとは限らないという現実を物語っている。
また、Intelの新しいLGA1851ソケットを採用するArrow Lake-Sプラットフォームは、LGA1700やAMDのAM5と比較して高価格帯に位置しており、構成コストの高さが普及の障壁となっている。高性能を求めるユーザー層でも、価格と性能のバランスを重視する傾向が強まる中、既存の構成を維持する選択肢が優位に立ちやすい構造となっている。
さらに、Meteor LakeやLunar Lakeといった他の新アーキテクチャに対する市場の反応も限定的であり、Intelの新世代製品群全体に対する受容の鈍さが浮き彫りになっている。
これらの動向を踏まえれば、今回の価格改定は単なる販促以上の意味を持つ。製品ラインナップの中で選択的に価格を見直すことにより、ユーザーの注目を再び新プラットフォームへ引き戻し、市場での立ち位置を再調整しようとする試みと見ることができる。競合するAMDとの技術力と価格戦略のせめぎ合いが、今後のプロセッサ市場全体の潮流に直結する可能性も否定できない。
Source:Tom’s Hardware