Nintendo Switch 2の未発表SoC「Tegra T239」が、中国のXianyu経由で入手された基板をGeekerwan氏が分解・解析した結果、8基のArm Cortex-A78CコアとAmpereアーキテクチャを採用した1536基のCUDAコアが確認された。Samsungの8Nプロセスをベースに製造され、面積は約207平方ミリメートルと前世代の2倍規模。SK hynix製の12GB LPDDR5xメモリと256GB UFS 3.1ストレージも搭載され、電力供給は最大34.4Wに対応する。
今回のリークにより、従来推測されていた5nmプロセス採用説が否定され、Nvidia Jetson Orinと密接な関連を持つ仕様であることが裏付けられた。一方、Ampere設計の継続採用はコストや再設計リスクを抑える任天堂の戦略的選択と見られる。
Switch 2のSoC構造が判明 Tegra T239はAmpere設計で新境地へ
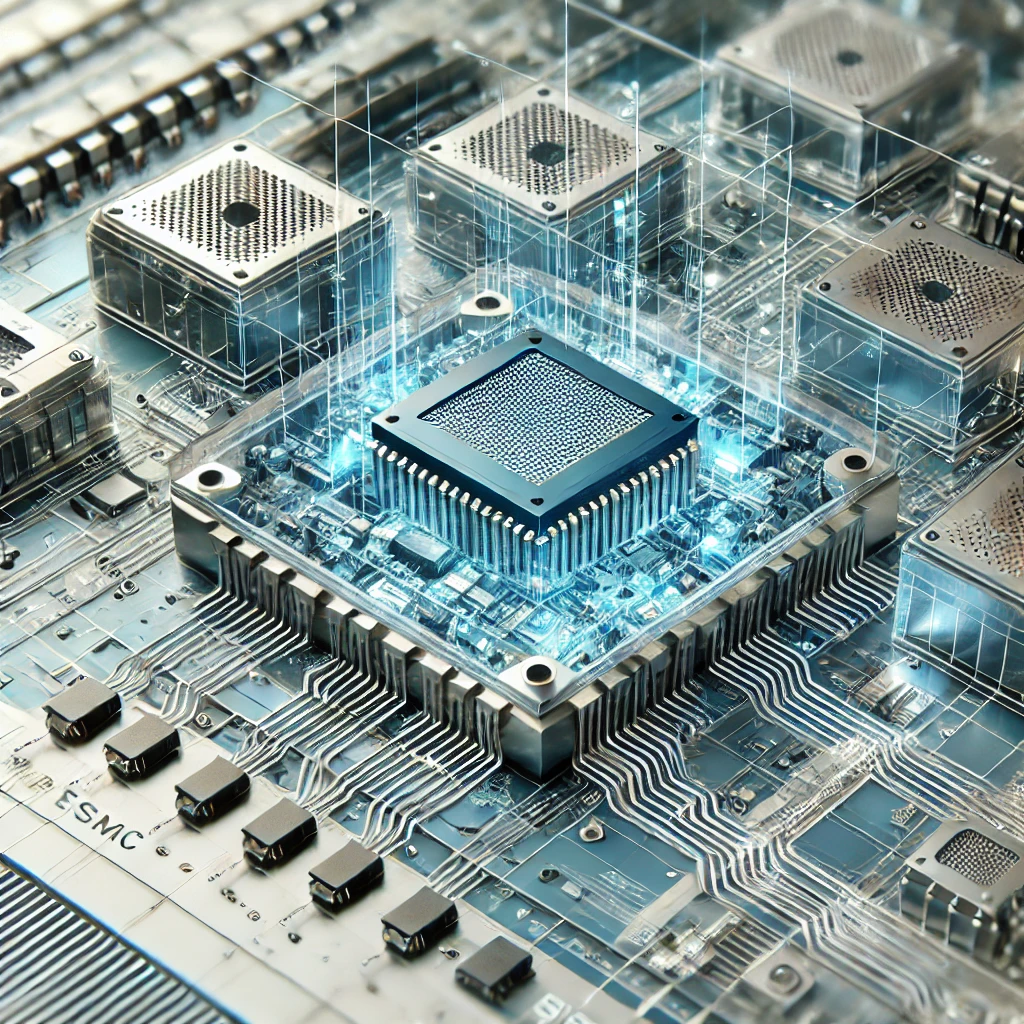
Geekerwan氏がXianyu経由で入手したSwitch 2の基板解析により、Tegra T239 SoCの構成が具体的に明らかとなった。CPUは8基のArm Cortex-A78Cコアを搭載し、それぞれ256KBのL2キャッシュを備えるほか、L3は4MBを共有。GPUはAmpere世代の設計で、6基のTPCが12基のSM(ストリーミングマルチプロセッサ)を形成し、合計1536基のCUDAコアを実装する。チップの総面積は約207平方ミリメートルで、前世代のTegra X1(Mariko/T210)の約2倍に拡張されている。製造はSamsungの8Nプロセスを採用しており、RTX 30シリーズと技術的な近縁性を持つものの、SoC内部の設計はJetson Orin向けのT234と親和性が高い。メモリはSK hynix製12GB LPDDR5x RAM、ストレージは256GB UFS 3.1で、Wi-FiとBluetoothはMediaTek製チップが搭載される。
この設計からは、任天堂がSoCの全体的な性能よりも、バランスと安定性を重視している姿勢がうかがえる。Ampere設計のGPUを維持した理由は、先進的な5nmプロセスへの切り替えよりも、成熟した8Nノードでの確実性を優先した結果と考えられる。T239の開発が2021年頃に完了していた点も、Switch 2のリリース時期が内部的に調整されてきた証左といえ、長期的なプラットフォーム運用を見越した構成と見られる。
Switch 2の性能見通し RTX 2050ベースのシミュレーションで描かれる現実的な姿
Geekerwan氏は、Tegra T239のベンチマーク結果を補完する目的で、アンダークロックしたRTX 2050ラップトップGPUを使い、Switch 2の性能を擬似的に再現した。結果として、ドックモード時にはGTX 1050 Tiに匹敵し、携帯モード時はGTX 750 Tiと同等レベルの性能とされた。Steam Deckよりやや下回る結果であり、次世代ゲーム機としては高性能とは言えないものの、携帯性と低消費電力の両立を優先した設計意図が見て取れる。搭載電源は最大34.4Wに対応しているが、実際の動作時はこれをフル活用するケースは少ないと推測される。
この構成は、短期的なスペック競争よりも、既存のSwitchユーザーが期待する「十分な進化」と「互換性」を確保する意図が強い印象を与える。Ampere設計の継続は将来的なアップデートの余地を残しており、5nm世代へのステップアップが、今回のSwitch 2の寿命をさらに引き延ばす役割を果たす可能性もある。現時点では性能に過度な期待を寄せるより、安定性と完成度に焦点を合わせるべき局面といえるだろう。
Source:Tom’s Hardware

