Intelは、第13世代および第14世代の「Raptor Lake」デスクトップCPUにおける稀なクラッシュ障害「Vmin Shift」への追加対応として、新たなマイクロコード「0x12F」をリリースした。これは、軽負荷時やアイドル状態において発生する異常な電圧変動によるクラッシュリスクを緩和するものであり、既存の修正パッチでは対応しきれなかった未発症個体の保護が目的とされる。
本障害は、電力設定やマイクロコードの挙動に起因する複合的要因によって引き起こされ、最悪の場合、CPUに永久的な損傷を与える可能性があるとされていた。既に発症した場合は交換対応が必要であるが、Intelは保証期間を最大2028年前半まで延長し、RMA申請による交換を可能としている。
各マザーボードベンダーは今後数週間内にBIOS経由で同パッチを提供予定であり、安定運用のためには速やかな適用と、公式推奨の電圧設定を遵守することが求められる。
「Vmin Shift」の構造と再発防止策としてのマイクロコード「0x12F」
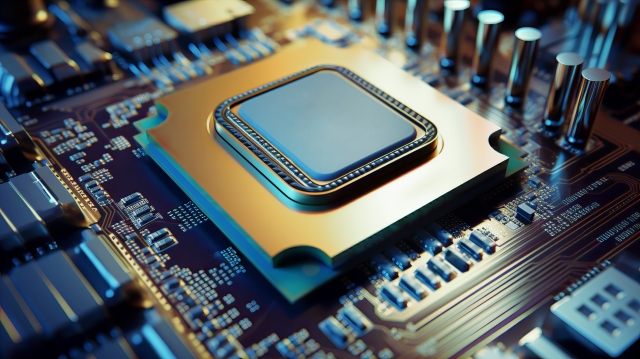
「Vmin Shift」と呼ばれるこの障害は、Intel第13世代および第14世代の「Raptor Lake」「Raptor Lake Refresh」プロセッサにおいて、主にアイドルまたは軽作業状態の長時間稼働中に生じる稀な電圧異常である。
CPUが不適切な最小電圧(Vmin)で動作し続けた場合、クラッシュが発生し、最悪の場合には物理的な損傷に至る可能性がある。Intelは当初、「0x125」「0x129」「0x12B」の各マイクロコードで修正を試みたが、依然として未発症ユニットの完全なリスク排除には至っていなかった。
今回新たに提供された「0x12F」は、さらなる稀な発症条件を対象としており、特にBIOSを通じた適用が必須とされる。各マザーボードメーカーは今後数週間以内に対応アップデートを公開する見通しであり、エンドユーザーはベンダーのサポートページを注視することが求められる。Intelはまた、電圧設定を適切に制御することで再発を防止できるとし、推奨設定の遵守を強く訴えている。
本件は単なる不具合対応にとどまらず、マイクロコードの限界とその更新手段の運用体制に対する再評価を促している。ハードウェア層の深部で発生する現象ゆえ、ソフトウェア的な予防措置だけでは十分でないという教訓が浮き彫りになった。
永続的な損傷リスクと保証延長の背景
「Vmin Shift」による障害は単なる一時的なクラッシュに留まらず、CPU自体の物理的破損を引き起こす例が確認されている。これにより、既に影響を受けたユニットに対してはマイクロコード更新による修復は不可能であり、完全な交換が必要となる。Intelはこのリスクを受けて、対象プロセッサの製品保証を最大で2028年前半まで延長しており、RMA(返品・交換)手続きによる対応を可能としている。
特に、従来のパッチである「0x12B」以前のアップデートではクラッシュ発生の予防効果に留まっており、既に症状が顕在化したCPUには何らの回復措置も講じられなかった。これは、問題がソフトウェア的な不整合ではなく、ハードウェアレベルでの電圧処理の異常に起因していたためである。また、「0x12B」には一部の処理系で性能低下が見られたが、「0x12F」ではその副作用は報告されていない。
こうした対応は、ハイエンド市場における信頼性維持と顧客満足度を確保する戦略的措置とも読める。Intelとしても、長期的なブランド価値の毀損を避けるべく、異例ともいえる保証期間の延長に踏み切ったと考えられる。クラッシュ未発症のユーザーにとっても、今後の運用に慎重さが求められる状況にある。
Source:TechSpot

