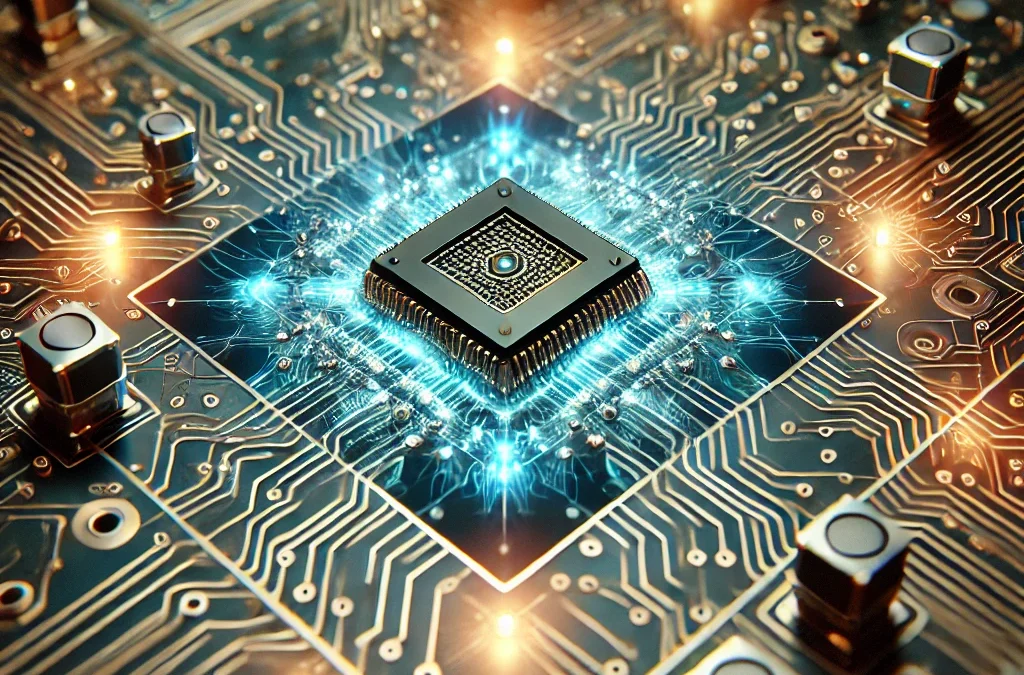Intelは、CPUとArc GPUの連携によってAI処理やストリーミング性能を高めることを目的とした独自技術「Deep Link」の開発と公式サポートを終了した。2020年に導入されたこの技術は、Dynamic Power ShareやHyper Encodeなど4つの機能を提供し、一部アプリでの性能向上が期待されていたが、最新のArc B580やMeteor Lake世代では既に非対応となっていた。GitHub上でのIntel担当者のコメントにより、今後はアップデートや技術サポートが行われないことが明らかとなっている。
開発終了の背景には、機能のニッチ性やベンダー検証の手間に見合うだけの採用実績が得られなかった事情があると見られる。特定の構成に依存する仕様は、長期的な普及や互換性の確保に課題が残ったまま終焉を迎えた形だ。
OBSやDaVinci Resolveを支えた技術に終止符 Intel Deep Linkの実態

Intelが2020年後半に発表した「Deep Link」は、第11世代以降のCore CPUとArc Alchemist GPUを組み合わせることで、映像処理やAI演算などを最適化する独自技術であった。Dynamic Power Shareによる電力バランス制御や、Hyper Encodeによるマルチプロセッサによる動画エンコード高速化、Stream Assistを通じたGPU間のストリーミング処理分散など、実用性を意識した設計が特徴だった。特にOBSやHandbrake、DaVinci Resolveといったアプリケーションでの負荷軽減や処理時間短縮において恩恵が期待されていた。
しかし、現実には環境依存性が高く、期待されたほどの普及は進まなかった。GitHub上では、最新のArc B580とCore Ultra 7 265Kの構成でもStream Assistが正常に動作しないという報告があり、これに対してIntelは開発終了を明言。さらに2023年末に登場したMeteor Lake世代のCPUがDeep Linkに非対応であることからも、同技術はすでに撤退フェーズに入っていたと見られる。
採用の壁となった構成制限と検証コスト 普及に至らなかった理由
Deep Linkの普及を妨げた要因として、限定的な対応環境と高い実装ハードルが挙げられる。機能の恩恵を得るには、第11~13世代Intel CPUに加え、専用のArc GPUを必要とし、さらにソフトウェア側でもベンダーによる動作検証が求められた。この多重の条件は、製品開発の現場において導入障壁となり、特定構成のPCに依存する技術として扱われたことは否めない。
加えて、Intelが位置づけた用途がニッチであったことも無視できない。Deep Linkが強みとするストリーミング支援やAI処理加速は、既にNVIDIAやAMDが展開する他技術と競合しており、ユーザー側がその違いを体感するには構成やソフト環境が整っている必要があった。結果として、Intel側でもコスト対効果が見合わないと判断し、開発の継続は見送られた可能性が高い。
Meteor Lake世代の非対応が示すIntelの開発戦略の転換点
Deep LinkがMeteor Lakeで非対応となった事実は、Intelが統合処理重視の方針に舵を切った証左と捉えることができる。Meteor Lakeはチップレット設計やAI専用エンジンの搭載により、SoC全体での処理最適化を進めるアプローチが特徴であり、CPUとGPUの別々のチューニングに依存するDeep Linkとは設計思想が異なる。つまり、今後はより統合的かつ汎用的な処理基盤の整備が重視されると考えられる。
また、GPU単体としてもArc Alchemist以降の展開が停滞している現状を踏まえると、Intelがコンシューマー向けGPUでの優位性確保に再考を迫られている状況が垣間見える。Deep Linkの終息はその一断面にすぎず、今後の製品戦略や開発資源の再配分に影響を与える転機となった可能性がある。性能よりも柔軟性と持続性を軸に再構築する必要性が浮き彫りになった。
Source:Tom’s Hardware