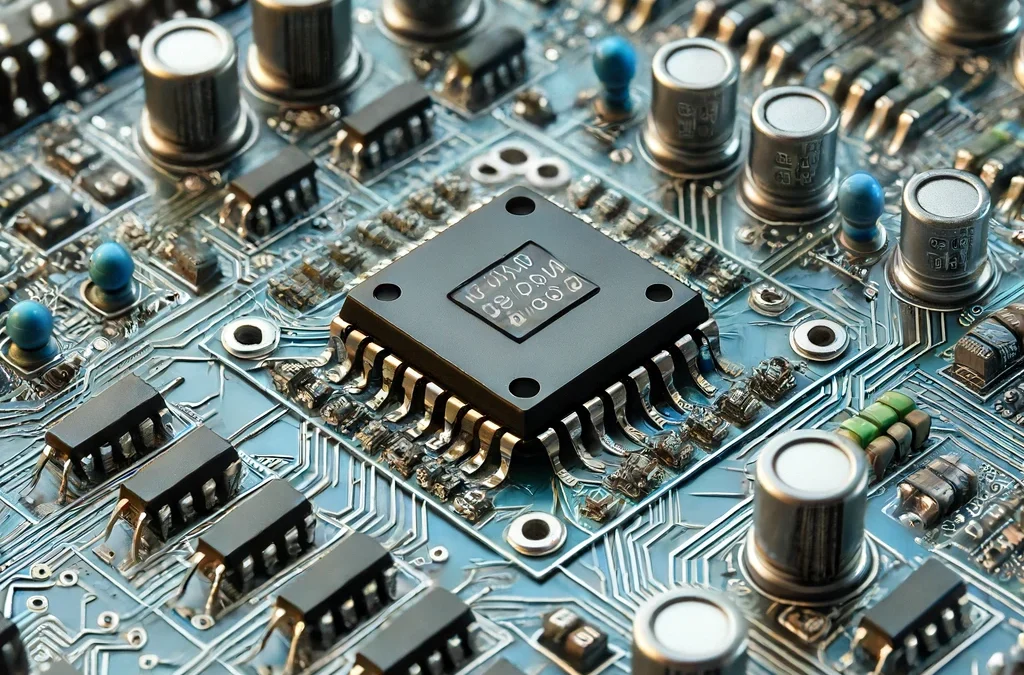Nvidiaの未発売GPU「Titan Ada」がベンチマーク結果とともに公開された。このモデルは、RTX 4090に搭載されているAD102チップの完全版を採用し、CUDAコアは18,432基、メモリは48GB GDDR6Xを搭載。性能面ではRTX 4090を10〜15%上回り、消費電力あたりの効率ではRTX 5090すら凌駕する場面も確認された。
しかし、4スロット仕様の巨大な冷却機構や、既存製品との市場競合、投入タイミングの難しさが重なり、製品化は見送られたと見られる。開発は完了していたにもかかわらず、Titan Adaは戦略と実用性の間で封印されたGPUであり、現在はその存在自体がNvidiaのアーキテクチャ技術の極限を示す象徴となっている。
フルスペックAD102を搭載したTitan Adaの仕様と性能評価

未発売のNvidia「Titan Ada」は、RTX 4090で採用されたAD102チップのフルスペック版を使用し、18,432基のCUDAコアと48GBのGDDR6Xメモリを備える構成となっていた。この数値は、RTX 4090と比較してCUDAコア数で12.5%多く、コンシューマー向けGPUとしては過去最大のメモリ容量である。物理的にも4スロットクーラーとデュアル12VHPWRコネクタを搭載する大型仕様で、冷却性能と安定性に重きを置いた設計だった。
ベンチマーク結果では、3DMark Time Spy ExtremeやSpeedwayにおいてRTX 4090を10〜15%上回るスコアを記録し、『Remnant 2』では平均82 FPS、『Cyberpunk 2077』では最大22%の性能向上が見られた。さらに注目すべきは、ワット単位のパフォーマンスで、RTX 5090と比較しても効率で上回る結果を示したことだ。これにより、電力効率に優れるハイエンドGPUとしての評価も得ている。
性能だけ見ればTitan Adaは明らかに現行世代の上位互換に近い立ち位置にあったが、実際の発売には至らなかった。この構成が製品化されていれば、RTX 40シリーズ内での製品階層が複雑化するリスクを孕んでいたと考えられる。
幻のTitan Adaが製品化されなかった背景とその影響
Titan Adaは設計・試作まで完了していたにもかかわらず、Nvidiaは市場への投入を最終的に見送ったとされる。背景にはいくつかの要因がある。まず、RTX 5090に匹敵するかそれ以上の効率を持つ性能が、次世代フラッグシップの立場を脅かしかねなかったことが挙げられる。また、Titanブランドは元来ワークステーションやプロフェッショナル向けの色合いが強く、コンシューマー市場に投入するには位置づけが難しかった側面も否定できない。
さらに、4スロットに達する本体サイズは、一般的なPCケースには収まりきらない場合も多く、物理的な制約から導入が困難となるシナリオも想定される。また、RTX 4090ですら扱いに苦慮するユーザーが多い中、Titan Adaのサイズや発熱処理への要求は、より限定的な市場に向けた設計であったことが明らかである。コスト面でも、高価な冷却機構や特別な電力要件が、通常製品ラインへの組み込みを難しくしていたとみられる。
このように、Titan Adaの不発売は単なる判断ミスではなく、製品戦略と市場需要、そしてコストバランスの綿密な見極めの結果と言える。その存在が公開された今、開発中止された製品にも多くの技術的知見と戦略的判断が凝縮されていたことが浮き彫りになった。今後のハイエンドGPU設計において、この決断がどのような影響を与えるかも注目される。
Source:NotebookCheck